古時刻と古方位
古時刻
定時法

-
360度を12等分して、「子」から時計回りに2時間(一刻)ごとに十二支を当てたものが定時法。
-
子の時間は「午後11時〜午前1時」とする説が有力で、「午前0時〜午前2時」とする説もあった。基本は前者で考えていい!
-
一刻をさらに4分割し、「子一つ」「子二つ」と呼ぶことがある。2時間を4等分しているので、30分単位を表すことになる。(→ 不吉と言われる 「丑三つ時」 は午前2時から午前2時30分を表すことになる!)
-
宮中では、漏刻という水時計で時間を計っており、そこで太鼓を打っていた。
-
子の刻と午の刻には、太鼓を9回鳴らしたことから、九つ時と呼ばれた。
-
同様に、太鼓を鳴らした数によって「◯つ時」という呼ばれ方がされた。
不定時法

-
奈良時代・平安時代には上のような定時法が使われていたが、江戸時代には不定時法というものが用いられた。これは、日の出(明け六つ)と日没(暮れ六つ)を基準として、それぞれを6等分する方式(不定時刻法)である。
-
季節によって夜の長さが変化するため、時間の長さが一定しない特徴がある。
-
暮れ〜明けまでを5等分して、「初更」「二更」...「五更」と呼ぶこともあった。
古方位

-
360度を12等分して、北を「子」とし、時計回り(右回り)に十二支を当てたものが古方位。
-
北東は艮、南東は巽、南西は坤、北西は乾と、それぞれの干支の中間には特別な名前がついているものがある。
-
古典の時代(昔の人々)の考えでは、方角の良し悪しが重視されることがあり、方角の吉兆を占う方違えが行われていた。艮は鬼門、坤は裏鬼門と呼ばれ、不吉なものであった。(これは、陰陽道によるもの)
関連動画

2:25
【日曜・祝日は】朝から古文常識34「透垣」35「籬」楽しく学ぶ古文チャンネル

2:27
【日曜・祝日は】朝から古文常識19「築地」20「母屋」楽しく学ぶ古文チャンネル

32:32
【源氏物語で古文常識061(常識編32)夢について】古代人と夢・西郷信綱・藤原兼家・蜻蛉日記・藤原道綱母・吉備真備・伴善男・応天門の変・万葉集・小野小町・藤原師輔・光る君へ・大河ドラマ・受験古文国語フレンズ【コクフレ】
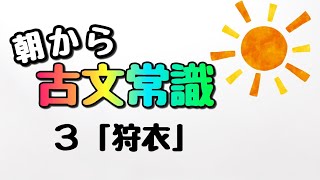
1:38
【日曜・祝日は】朝から古文常識3「狩衣」楽しく学ぶ古文チャンネル

5:28
【テスト対策】覚えておきたい古典常識①「後宮で暮らす女性の役職」【古典Vtuber/よろづ萩葉】よろづ萩葉の万葉ちゃんねる




