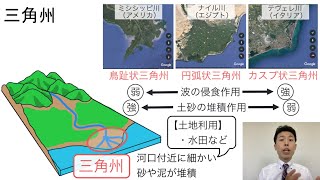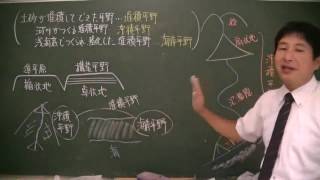液状化
液状化
地震などにより、水分を多く含む土壌が液体のようになってしまう災害。
地盤沈下、土管の浮き上がり、建物が傾くなどの被害が起こる。
原因
地震がおもな要因。
埋立地や三角州など、水分を多く含む軟弱な土壌では、土の粒子の間に水分が入り込んで安定している。
それが地震などによって揺り動かされると、土の粒子の結合が弱まり、遊離してドロドロになる。これを液状化という。
土壌が液状化すると、十分な深さまで杭を打っていない建物が自重で傾いたり、土管が浮力で浮き上がってしまうなどの被害が生じる。
それが落ち着いてくると、水分が浮き上がってきて泥水が吹き出すなどの被害もある。
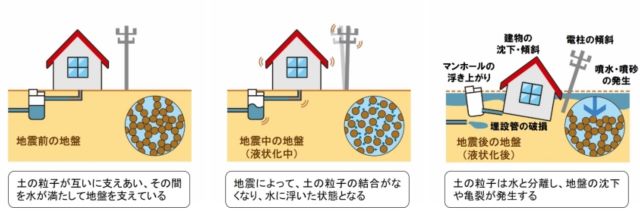 (国土交通省)
(国土交通省)
起きやすい場所
- 埋立地
- 三角州
など、水分を多く含む軟弱な土壌。
実際の被害
2011年の東北地方太平洋沖地震により、関東地方で多く被害が発生した。
東京都~千葉県の海沿いの地域で特に被害が深刻で、建物が傾いたり、マンホールが浮き上がったりといった被害があった。
 (千葉県浦安市)
(千葉県浦安市)
関連動画