細胞性免疫
※細胞性免疫は生物基礎と生物両方で登場するので、2段階に分けて説明します!
細胞性免疫とは
キラーT細胞が主体となり、異常細胞を直接攻撃して排除する。
そう、細胞性免疫の抗原となるのは、「細胞」。だから、細胞性免疫というのだろう。
例) ウイルス感染細胞、ガン細胞、移植の拒絶反応、ツベルクリン反応など。
細胞性免疫のながれ(生物基礎var)
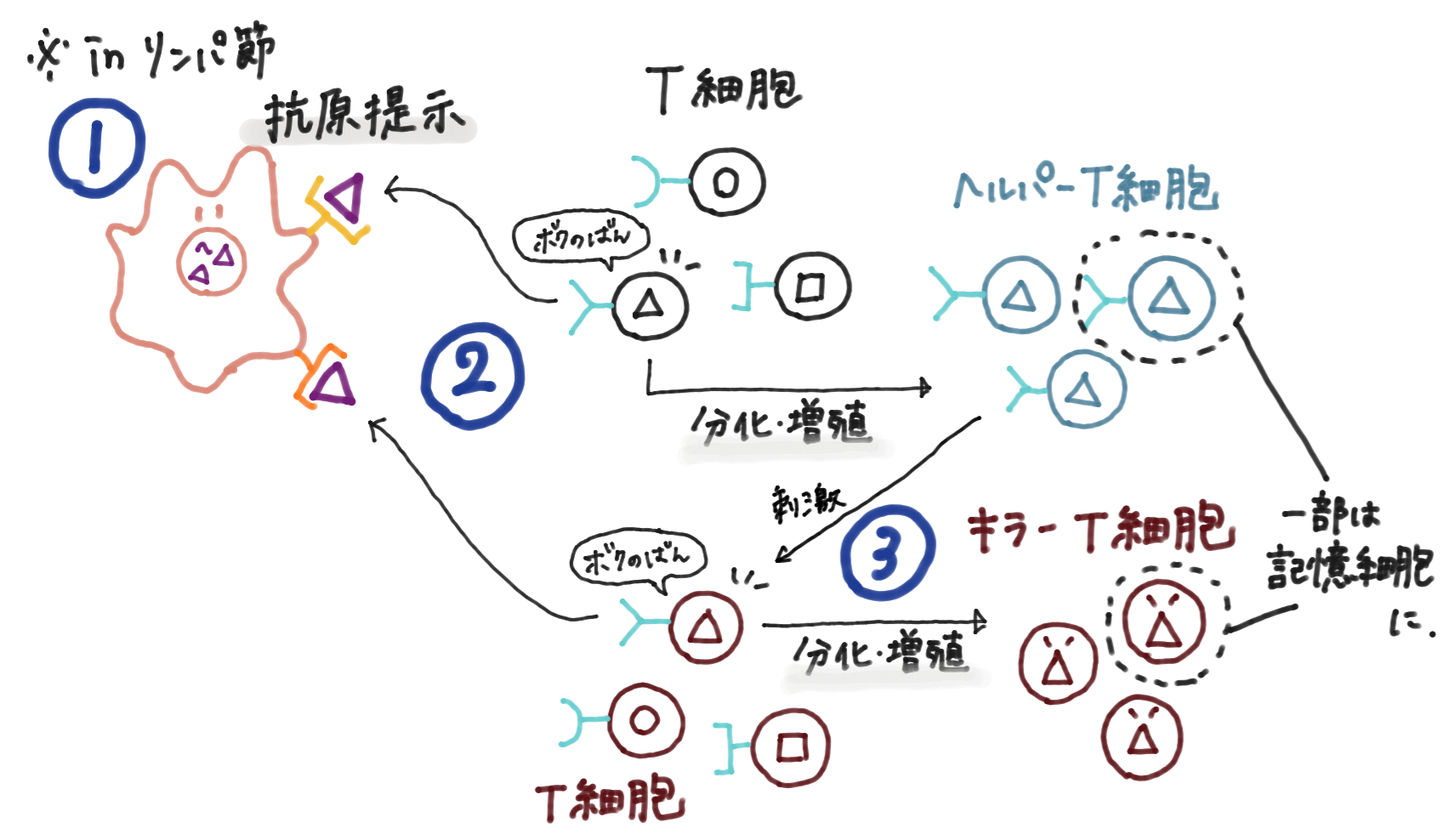 ①免疫細胞(主に樹状細胞)が、リンパ節で、分解した抗原の一部を手に乗せて提示。(抗原提示)
①免疫細胞(主に樹状細胞)が、リンパ節で、分解した抗原の一部を手に乗せて提示。(抗原提示)
②2種類の数あるT細胞のうち、それぞれ抗原の一部と対応した手を持つT細胞が、抗原を認識する。一方はその後増殖し、分化してヘルパーT細胞になる。(一部は記憶細胞になる)
(2種類のT細胞がくっつく樹状細胞の手は異なるので要注意。詳しくは生物で学びます)
③もう一方のT細胞は、ヘルパーT細胞に刺激されることで 増殖・分化が促進されて、キラーT細胞になる。(一部は記憶細胞になる)
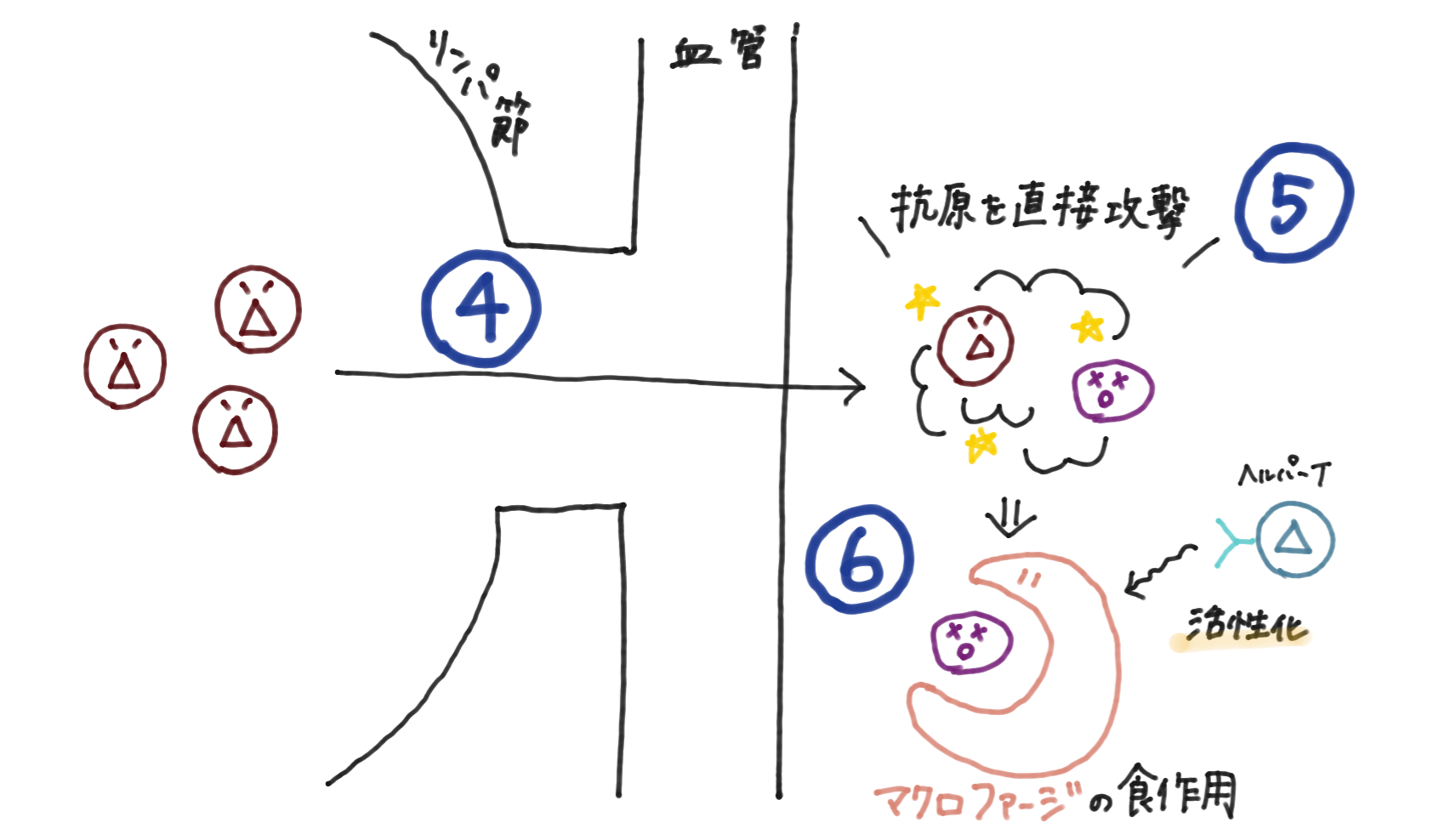
④キラーT細胞はリンパ節を出て、血流にのって異常細胞の場所まで運ばれる。
⑤キラーT細胞が異常細胞を直接攻撃し、死滅させる。
⑥ヘルパーT細胞が活性化したマクロファージが、食作用により抗原を分解する。
細胞性免疫のながれ(生物var)
以下生物基礎と異なるポイントをまとめておく。
【ポイント】
-
手の名前はMHC抗原という。これは2種類あって、ヘルパーT細胞になる方がクラスⅡ、キラーT細胞になる方がクラスⅠの手が持つ抗原断片にくっつく。
-
抗原提示した断片にT細胞が結合した時や、ヘルパーT細胞がキラーT細胞に向かって、「インターロイキン」というサイトカインが出ている。(下図のオレンジ線)
これにより、各細胞の分化や増殖が促進される。
-
T細胞が抗原を認識する受容体を、TCR(T細胞受容体)という。
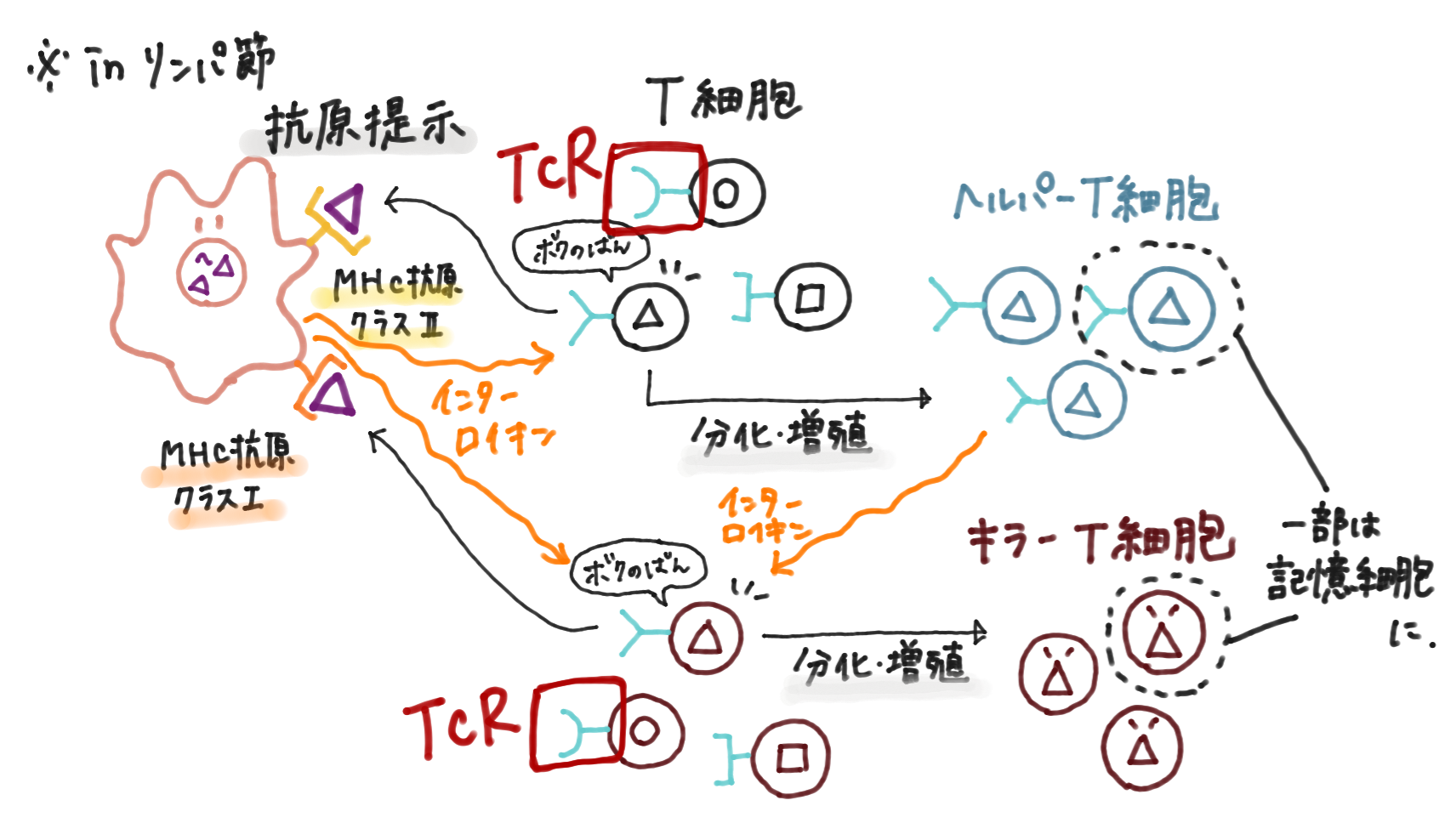
細胞性免疫について、動画で学びたい人は、「おうち生物 36. 適応免疫」をチェック!
この用語を含むファイル
関連動画








