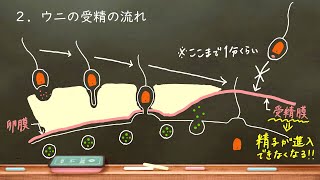ガードンによる核移植実験【クローンの作製】 高校生物基礎
概要
動画投稿日|2015年10月11日
動画の長さ|5:42
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
ガードン教授の核移植実験(ガードン教授は山中教授と同時ノーベル賞受賞)について講義します。クローン生物の作り方です。
語呂「かっくいーガード、全て良い弟子(核移植実験をしたガードン、ほぼ全ての細胞に全ての遺伝子があることを証明した)」語呂になってませんね。すみません。
●山中伸弥教授とジョン・ガードン博士は、2012年、ノーベル医学・生理学賞を同時に受賞した。
●ガードンの実験:
① 白化個体(アルビノ)の上皮細胞(分化した細胞)の核を、別の黒色個体(野生型)の未受精卵に移植した(黒色個体の未受精卵の核は、あらかじめ壊しておいた)。
② 結果、核移植を受けた未受精卵の一部は、完全な個体にまで成長した(白化個体が生じたことから、移植された核の遺伝情報が発現し、発生が起こったことがわかる)。
この実験から、上皮細胞(分化した細胞)の核の中にも個体に必要なすべての遺伝子が揃っていることがわかった。
●1997年にはクローンヒツジのドリーが誕生した。技術的には、ヒトのクローンも作製できるだろうと考えられている。ただし、倫理的な問題から、禁止されている。
●ウィルムットは、クローン羊のドリーを作製した。
①ヒツジの乳腺細胞を低栄養条件で培養した(ふつうは10%のウシ血清を用いる。この時は0.5%のウシ血清が用いられた)。飢餓状態になった細胞は、細胞周期を停止する(細胞はG0期という細胞周期に誘導される。G0期は、最小限の転写のみが起こる静止状態である。どうしてG0期に誘導する必要があるのかについては、まだ完全には解明されていない)。
②①の細胞を、あらかじめ核を除去しておいた卵母細胞(減数分裂第二分裂中期で停止している)と融合させることで、核移植を達成した。
③②を胚盤胞期まで発生させたところで、第三のヒツジ(仮母)の子宮に移植した。そして、クローン羊「ドリー」が誕生した(乳腺細胞の供与体と遺伝的に同一な子羊、ドリーが誕生した)。
*ドリーは、乳腺細胞の供与者(ドナー)であるヒツジと遺伝的に同一の核ゲノムを持っている。しかし、ミトコンドリアゲノムが異なる。これはドリーが、除核した未受精卵の細胞のミトコンドリアDNAを受け継いでいるからである。
*上記のヒツジでの成功の後、マウス、ラット、ネコ、イヌ、ウマ、ラバ、ウシなど、様々な哺乳類のクローンが同様の方法(核移植法)によって作製された。
*最初のクローン作製戦略(ウィルムットらによる)では、核移植は細胞融合によって行われたが、現在では、ドナー細胞から核を単離して、単離した核を卵母細胞にマイクロインジェクション(顕微注入)する方法などがとられている。
*2003年2月、ドリーは6歳7か月で死んだ(当時、朝のニュースで報道されていたのを今も覚えている)。ヒツジの寿命は11~12歳なので、やや短命である。ドリーは、老齢のヒツジに見られる肺炎の合併症に苦しみ、安楽死させられた。ドリーの早すぎる死と関節炎の状態から、ドリーの細胞は正常なヒツジの細胞と比べて、健康的ではなかったという意見がある。これは、最初に移植された核の再プログラム化が不完全であったことが原因であるとも言われている。
●卵細胞内には、分化した細胞の核を初期化することのできる因子が存在した。その因子の追及の過程でできたのがiPS細胞である。卵細胞で発現している(スイッチがオンになっている)遺伝子に注目することから研究が始まり、ついには分化した細胞に多能性(いろいろな種類の細胞に分化できる能力)を獲得させることに成功した。そうして作成された細胞がiPS細胞(induced pluripotent stem cell)である(「再生し機能を回復させる」という、再生医療の道を切り開いた)。
問題:誤った文章を1つ選べ。
①ほぼすべての体細胞には同じ数の遺伝子が含まれている。
②体細胞は、ほとんどすべての遺伝子を失い、必要な遺伝子しかもっていない。
③分化した(特定の機能や形態を持った)体細胞では、多数の遺伝子のうち特定の遺伝子だけが発現している。たとえば筋細胞ではアクチン遺伝子が発現している。
答え:②(③は正しい。水晶体になる細胞ではクリスタリン遺伝子が発現する。このように、ふつう細胞では特定の遺伝子が選ばれて発現する。「ある特定の遺伝子が選ばれて発現すること」を「選択的遺伝子発現」という。たまに問われる。①の例外はB細胞やT細胞である。これらのリンパ球は遺伝子の再編成によってゲノムを改変している。)
問題(発展):人の細胞はすべて同じ遺伝子を持っているが、例外がある。何か。
答え:人の成熟した赤血球には核がない。また、人のリンパ球(B細胞やT細胞)は、遺伝子の再編成が起きている(→利根川進が発見した遺伝子の再編成を参照)ので、他の細胞と一部DNAが異なる(一部が切り取られつなぎ合わされている)。
#生物基礎
#高校生物
#クローン
関連動画
関連用語