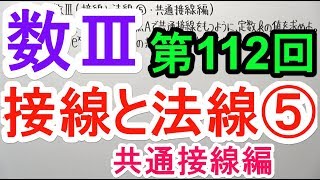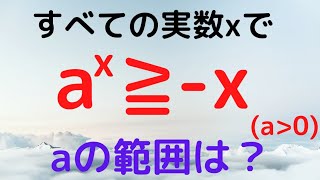微分法の応用4:共通接線《旭川医科大》
概要
動画投稿日|2023年2月8日
動画の長さ|26:35
2017年に東大でも共通接線から出題されました。その時は数学Ⅲの放物線を含む、ともに2次式で、重解判別式を用いるタイプでしたが、今後その形式の出題は期待すべきではないです。
今回は仕事の選び方について、あくまで僕個人が今の時点で感じていることを勝手に書いていきます。参考になれば幸いです。最終的な伝えたい着地点まで2回に分けて書きます。
仕事を選ぶ基準として最も大事なのは、「自分が生まれつき得意なこと」、その次は「他人の役に立っている感覚が得られること」だと思います。
よく言われる「やっていて楽しいこと」というのはおそらく数年で飽きます。ゲームで例えたらわかりやすいかと思いますが、最初は寝食を忘れてハマったゲームでも10年以上飽きずにできるものってほぼ無いと思います。楽しいで探そうと思ったら、10年以上20年50年飽きないゲームを探すのと同じくらい大変だと思います。Youtuberも最初は楽しくてもほとんどは数年で飽きていて、仕事として続けている人が大半のはずです。基本的にどんな仕事も数年で飽きます。
また、安定した職や、今後伸びる業界というのが自分の才能にピッタリであれば良いですが、それらを理由に決定すべきではないです。今後は安定を約束する代わりに激務や給与面の激減の可能性が高いです。
今後伸びると言われる業界というのも40年後の世界の状況が今わかるなら誰も苦労しないです。
ここで僕の話をすると、小さい頃から、ある程度得意なこととしては「絵を描くこと」「算数」でした。このチャンネルのネコの絵は僕が高校3年生のときに保健室で描いたものです。では、算数も絵を描くことも心から好きかというと実際のところ微妙です。数学を教えて誰かの役に立つことは間違いなく大好きですが。
ここで言いたいのは、得意なことと好きなことが重なるとは限らないということと、小学生中学生高校生の学生生活で自分が他人より得意なことは気づいているはずということ、どちらかというと好きなことより、得意なことを努力で最大限伸ばして社会の役に立つべきということです。好きだけでは、それを好きで得意な人には絶対敵わないからです。
好きで得意なことを見つけるのは本当に至難の技だと思います。よく好きで得意なこと、時間を忘れて没頭できることを見つけなさいと言われますよね。
「好き」「得意」「時代のタイミングで高収入が得られる」その3つが重なると最高に輝けますが、今の世界の移り変わりの早さからして、時代のタイミングが合ったとしてもせいぜい10年間で、それら3つとも自分の意志や努力でどうにかなるものではありません。そしてほとんどの場合「好き」は消費活動(他者が作ったゲームを遊ぶなど)で、生産活動で賃金が得られるものに繋げられるものは限られるかと思います。
次回では「他人の役に立っている感覚」が大事だと考える理由を書きます。興味があれば読んでください。
関連動画