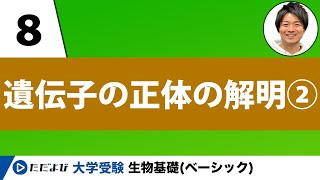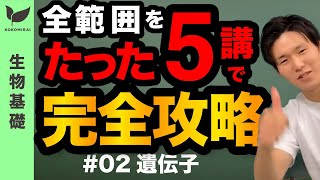高校生物基礎「ハーシーとチェイスの実験」
概要
動画投稿日|2019年10月18日
動画の長さ|6:38
今回はハーシーとチェイスの実験について解説しました!グリフィスの実験、エイブリーの実験についてはすでにアップしているので、これでグリフィス→エイブリー→ハーシーとチェイスの3つの実験の説明が揃いました!!
「形質転換を発見!グリフィスの実験」https://youtu.be/AQGFuNQRRAk
「形質転換を起こす物質はDNA!エイブリーの実験」https://youtu.be/RH6Zo82AcSE
実験の解説
ハーシーとチェイスは「遺伝子の本体はDNAである」ということを証明しました。そこに辿り着くまでの流れを見ていくと、
グリフィス‥肺炎双球菌をつかって「形質転換」という現象を発見した。
エイブリー‥肺炎双球菌をつかって「形質転換を引き起こすのはDNAである」ということを示した。
ハーシーとチェイス‥T2ファージをつかって「遺伝子の本体はDNAである」ということを示した。
という流れでしたね?
それではハーシーとチェイスの実験を見ていきましょう!
まず、つかったのはT2ファージというウイルスです。細菌に感染するウイルスをまとめて「バクテリオファージ」と言い、その中でも大腸菌に感染するT2ファージというウイルスがいます。
ウイルスって「DNA」と「タンパク質」だけでできています。だから「炭水化物」や「脂質」も含まれていないんですね。
ハーシーとチェイスが実験をした当時は、「DNAが遺伝子の本体である!」「いや、タンパク質が遺伝子の本体である!」という、
「DNA vs タンパク質」の論争が続いていたので、DNA約50%、タンパク質約50%をもつT2ファージは実験材料として最適だったんですね!
あと、DNAとタンパク質の構成元素を覚えていますか??
覚え方の動画はこれです↓良ければご覧下さい
「物質を構成する元素を覚えよう」https://youtu.be/bVmD-Q63jpE
DNA C,H,O,P,N (ちょっぷん と覚える)
タンパク質 C,H,O,S,N (ちょっすん と覚える)
2つを見極めるポイントは「P」か「S」です!「P」が存在すればDNAがある!「S」が存在すればタンパク質がある!と言えるわけです。
この実験では、それを決定的にするために、Pでも放射性同位体の32P(通常Pは原子量31)を含んだT2ファージと、Sでも放射性同位体の35S(通常Sは原子量32)を含んだT2ファージを使用しました。これによって他からPやSが入り込んだということも考えられません。
まず放射性同位体の32P(通常Pは原子量31)を含んだT2ファージを使います。
①T2ファージは大腸菌に付着する。
②自分の遺伝物質(DNA?orタンパク質?)を大腸菌内に入れる。
〜遠心分離を行う〜(※遠心分離では、密度の大きいものは沈み、密度の小さいものは浮く。)
その時
・大腸菌は密度が大きいので沈殿する(大腸菌内に入った遺伝物質も一緒に沈殿する)
・その他は密度が小さいので上澄み液になる(T2ファージは上澄み液に含まれる)
その「沈殿」と「上澄み液」を調べた結果、32Pは沈殿の方に多く含まれていた!
→DNAが大腸菌に注入されている、つまり遺伝子の本体はDNA!!
次に放射性同位体の35S(通常Sは原子量32)を含んだT2ファージを使います。
①T2ファージは大腸菌に付着する。
②自分の遺伝物質(DNA?orタンパク質?)を大腸菌内に入れる。
〜遠心分離を行う〜
その時
・大腸菌は密度が大きいので沈殿する(大腸菌内に入った遺伝物質も一緒に沈殿する)
・その他は密度が小さいので上澄み液になる(T2ファージは上澄み液に含まれる)
その「沈殿」と「上澄み液」を調べた結果、35Sは上澄み液の方に多く含まれていた!
→タンパク質は大腸菌に注入されていない、つまりタンパク質は遺伝子の本体じゃない!!
おわり
この動画を含むファイル
関連動画