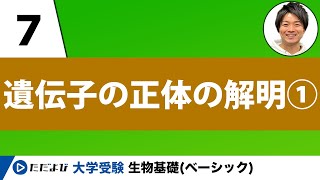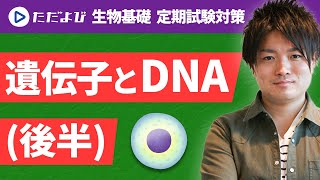エイブリーの実験
エイブリーは、グリフィスの実験を参考にし、
肺炎球菌(肺炎双球菌)を用いて、形質転換はDNAの基づくと証明した。
肺炎球菌
肺炎球菌には、
- マウスに感染させると肺炎を発病する(=病原性がある)「S型菌」
- 感染させても肺炎を発病しない(=病原性がない)「R型菌」
の2種類がある。
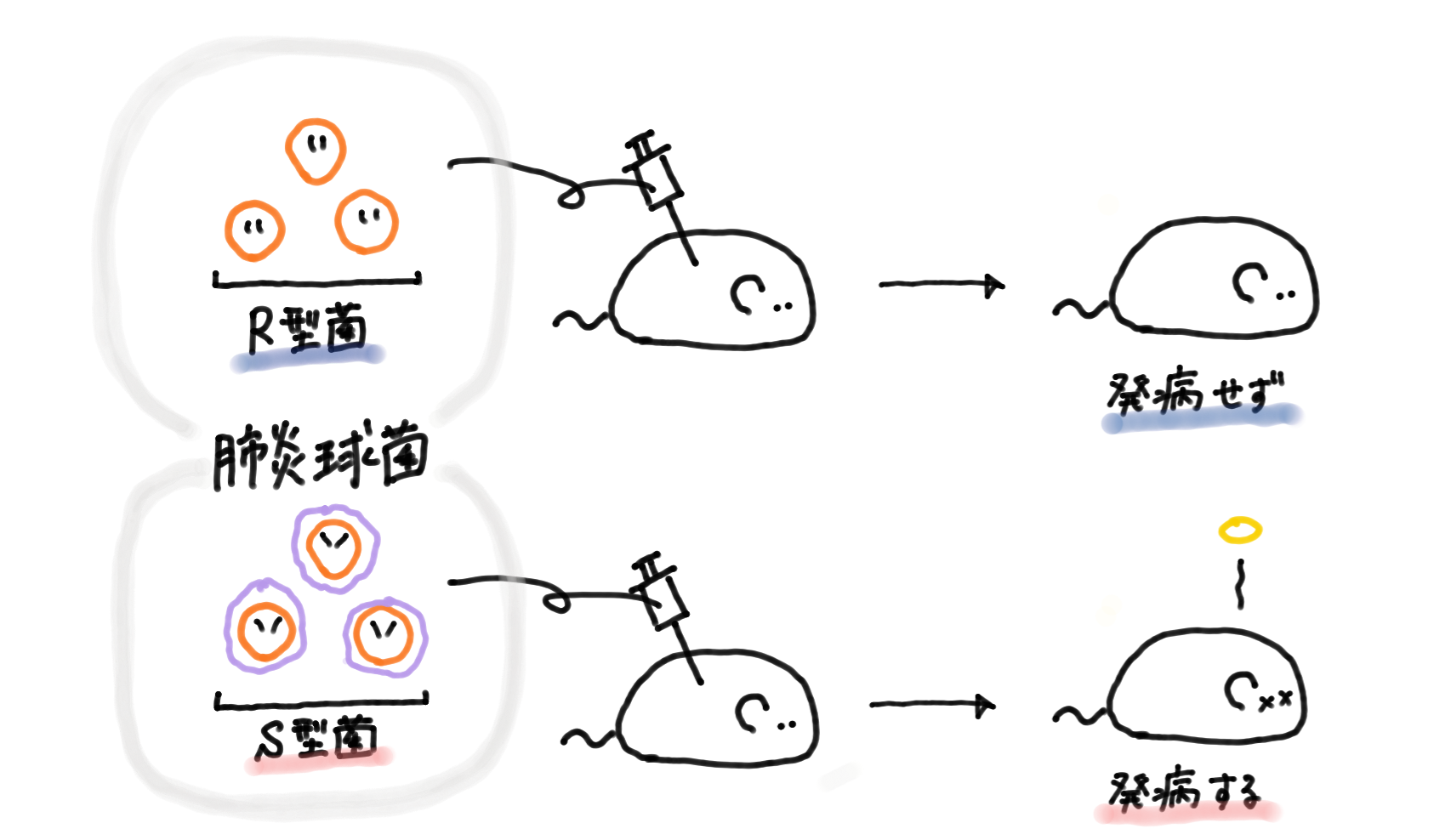
S型菌は殻をかぶっているが、R型菌はかぶっていない。
殻をかぶると悪者になってしまう、というイメージで覚えておこう。
実験の背景
グリフィスの実験では、死んだS型菌とR型菌を混ぜると、
R型菌がS型菌の一部を取り込んで(S型菌の殻をR型菌がかぶって)、
S型菌になった。
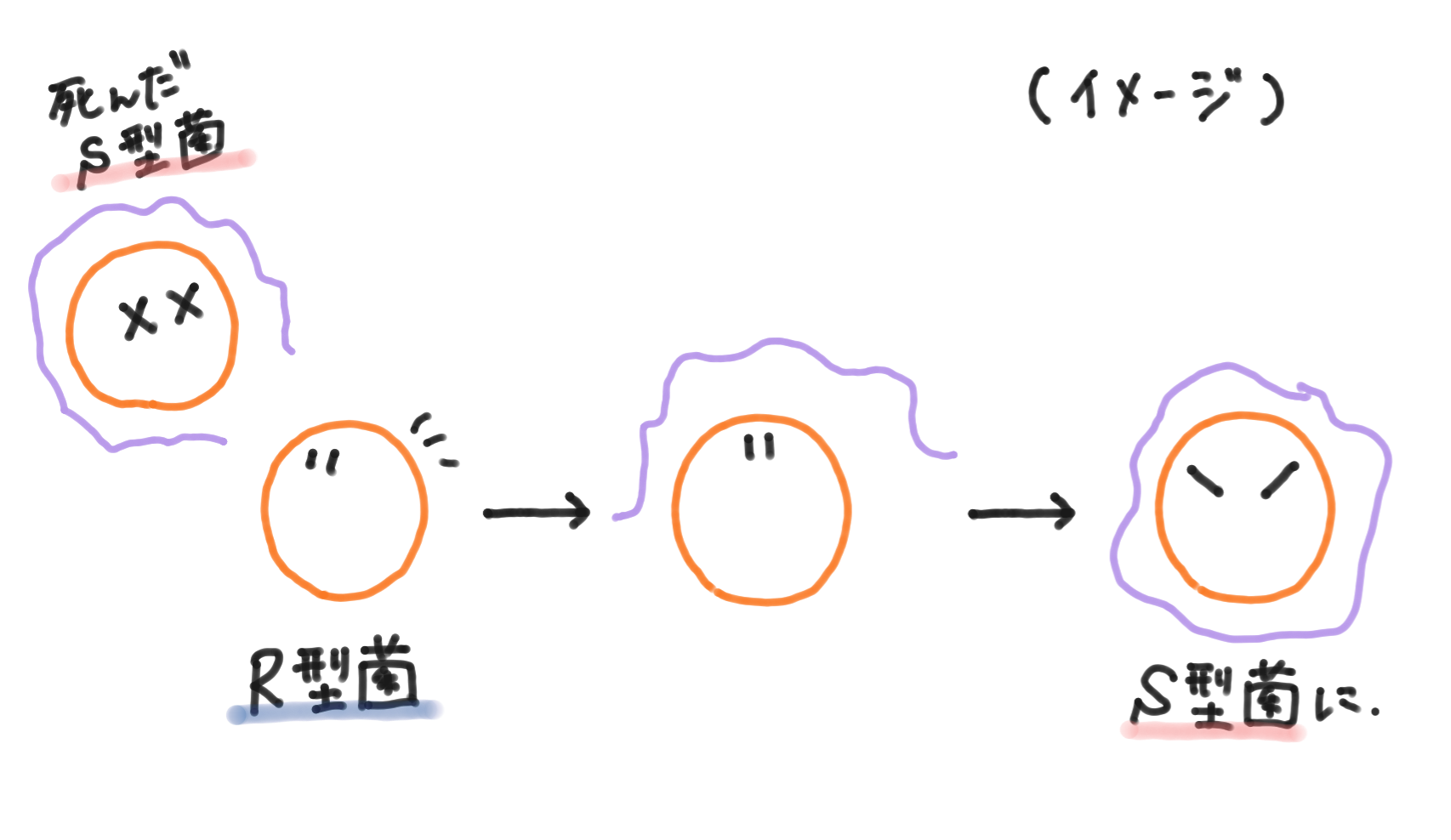
R型菌がS型菌になったのは、R型菌がS型菌の遺伝子を取り込んだからだ。(=形質転換)
では、遺伝子は、具体的に肺炎球菌のどの部分にあるのだろうか?
遺伝子の存在は知られていたものの、それが生物のどこに存在するのかはわかっていなかった。
タンパク質分解酵素とDNA分解酵素を使った理由
一方で、仮説は立てられていた。
遺伝子は、タンパク質か、DNAのどちらかにあると考えられていたのだ。
そこで、エイブリーは、
- タンパク質を分解させたとき
- DNAを分解させたとき
に、R型菌は形質転換するのかを検証したのだ。
(分解した結果、形質転換を起こさなくなるのならば、分解したものに遺伝子が含まれていた、ということになる)
実験方法
①S型菌をすり潰したものと、R型菌を混ぜた。
②S型菌をすり潰したものにDNA分解酵素を加えたものと、R型菌を混ぜた。
③S型菌をすり潰したものにタンパク質分解酵素を加えたものと、R型菌を混ぜた。
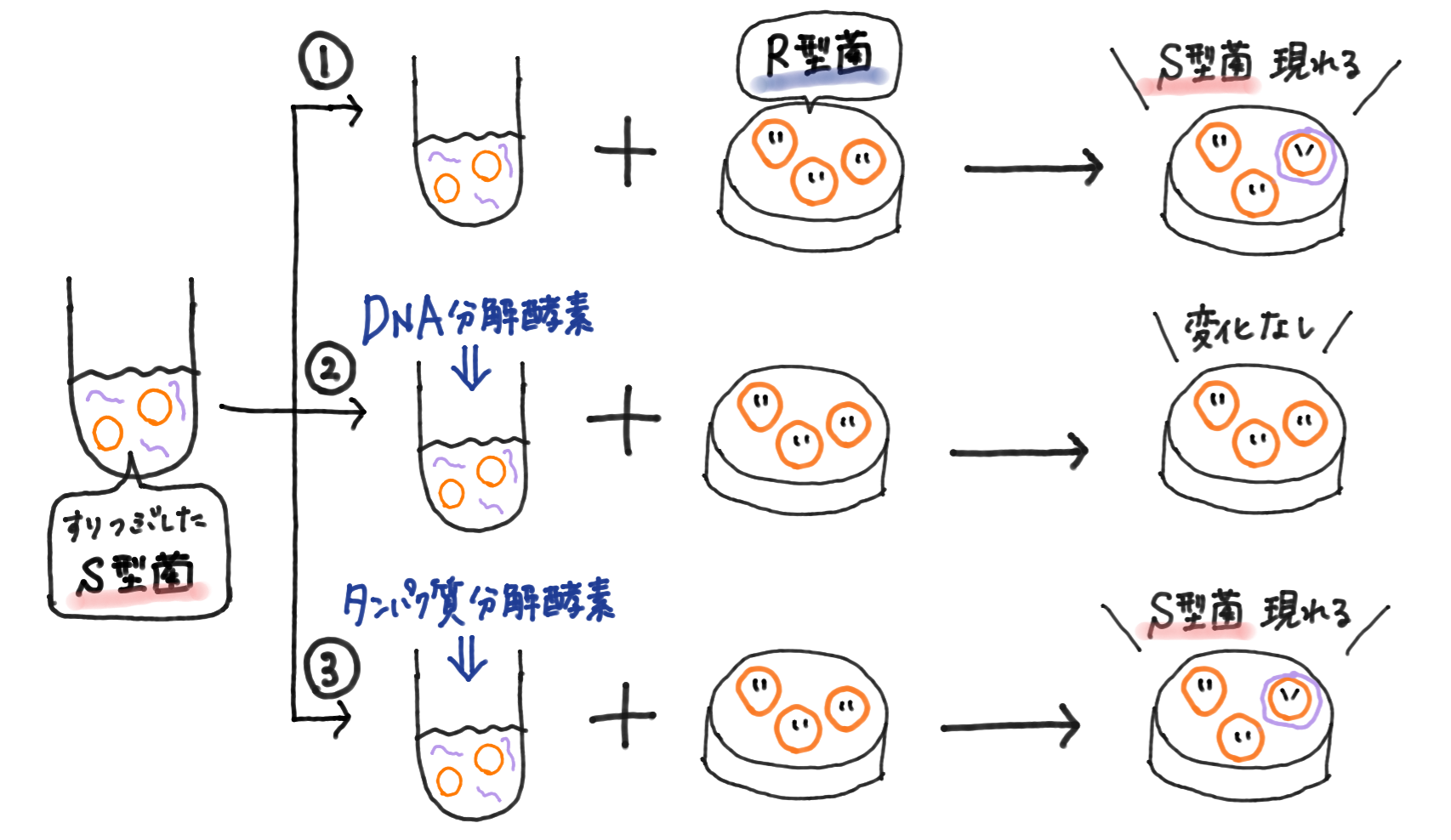
結果
①と③ではR型菌がS型菌の遺伝子を取り込んだが、
②では遺伝子を取り込むことができなかった。
この理由は、②ではDNA分解酵素によりS型菌のDNAが分解されたためである。
DNAが分解されると、遺伝子を取り込むことができなかったことから、
遺伝子はDNA上にある、ということがわかった。
ちなみに
エイブリーらは遺伝子の本体がDNAだと証明したにも関わらず、世間にはあまり信じてもらえなかったそう。
だから、この後ハーシーとチェイスが同様のことを証明する実験を行ったのだ。
エイブリーの顔写真を一度見てほしい。
確かに、彼の顔はどことなくひ弱そうにみえる気がする、、、
(あくまでも私の偏見です)
関連動画