二項定理
概要
二項の和の
また、
なので、二項定理の式の右辺の第1項を簡単に書くと
この式が成り立つ理由としては、まず
このとき、例えば
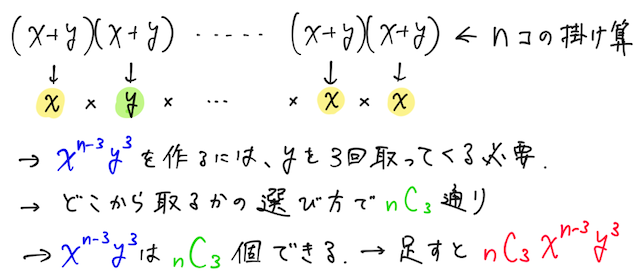
これが、組み合わせの
例
【問】
【答】二項定理より、
であるので、計算すると、
であるから、係数は
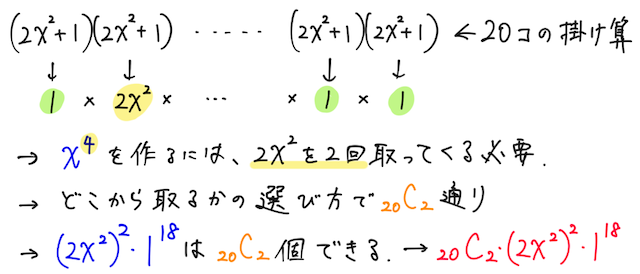
補足
- 初めて見たときにギョッとする定理ランキング上位
- 上の通り式を作れれば、覚える必要はない
- この
- 二項係数については、パスカルの三角形も有名。(例えば、「とある男が授業をしてみた」のはいち先生の動画を参照)
- 二項係数の面白い等式として、二項定理の
関連動画
関連用語





