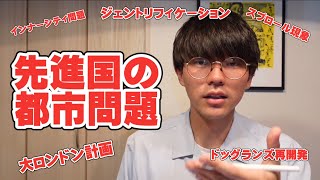コンパクトシティ
簡単なまとめ
ざっくり言うと、市街地を小さくまとめよう!という政策。
特に地方都市では、モータリゼーションの進行、スプロール現象による市街地の拡大などによって市街地が薄く広く広がり、経済活動・行政サービスの効率が悪化していた。
これを解消するため、市街地を中心地に集約しようとするのが「コンパクトシティ」の構想。
政策導入の経緯
モータリゼーションの進展、大店法改正によるロードサイド型店舗の増加、開発規制の過度な緩和などにより、特に地方都市では
- 中心市街地の衰退
- 低密度な市街地の拡大
- 自動車交通への依存
が発生した。
要は、「市街地が薄く広くなって、車がないと移動が不便になった」。
このような街では、
- インフラ整備・行政サービスの効率悪化
- 公共交通の衰退→交通弱者の発生
などの問題が発生するようになった。
また、日本では今後人口が減少していくのが確実で、税収の減少、市街地の衰退、高齢化が進むことから、低密度に広がり高コストな市街地のままだと現状の行政サービスを維持することは難しい。
コンパクトシティのねらい
市街地を集約することで、
- 経済活動・行政サービス・インフラ整備の効率化
- 自動車交通の分担率低減→公共交通の活性化
などの利点がある。
要は、
「低コストで効率よく維持できる街をつくる」
というのが、コンパクトシティ最大の目的。
実際の事例
富山市が有名な事例。
富山市はかつて全国的にも郊外化が進んだ地域で、中心市街地の衰退が問題となっていた。
そこで富山市はLRTを整備するなど公共交通を拡充。公共交通網沿線への居住を推進し、車がなくても徒歩と公共交通で暮らせる人口を拡大した。
その結果、鉄道沿線の人口は増加に転じたほか、中心市街地の地価も上昇したり低下が緩やかになったりと、一定の効果がみられている。
 旧富山港線をLRTに転換した富山地方鉄道線(旧富山ライトレール)
旧富山港線をLRTに転換した富山地方鉄道線(旧富山ライトレール)
関連動画