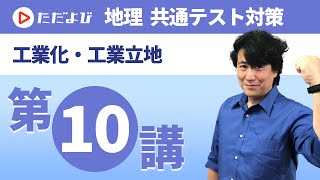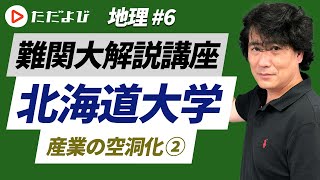工業立地論
工業立地論
「工場をどこに建てたら、製品が一番安く、効率よく作れるか」
これを考えるのが工業立地論です。
作る製品によって、どこに一番お金がかかるかは違います。
輸送費だったり、人件費だったり、土地代だったり、電気代だったり。
何にお金がかかるかによって、工場の立地は様々に変化します。
そして、「〇〇のあるところに工場を建てる」傾向のことを、「〇〇指向型立地」と言います。
原料産出地の近くに工場が建つときは原料指向型立地、労働力が豊富な場所に工場が建つときは労働力指向型立地、といった具合です。
これを理論化したのがドイツのアルフレッド・ウェーバーです。マックス・ウェーバーではありません。
各種工業立地
原料指向型立地
代表例:セメント工業、鉄鋼業、製紙・パルプ
原料重量>製品重量の工業。原料産出地付近に立地し輸送費を抑える。
例えば鉄鋼業では、石炭・鉄鉱石合わせて2~3トンを使ってやっと1トンの鉄ができます。製品のほうが原料より圧倒的に軽いわけです。
臨海指向型
代表例:鉄鋼業、石油化学工業
原料を輸入に頼る場合にみられる立地です。
外国から原料を持ってくる場合はだいたい船を使いますから、港の近くに立地した方が好都合というわけです。
市場指向型
代表例:ビール・清涼飲料、高級アパレル、印刷・出版
水などの普遍原料を使用する工業。市場付近に立地し輸送費を抑える。
例えばビール製造では、主な原料は麦芽、ホップ、酵母、水です。水はどこにでもありますし重いので、できるだけ水を運ばなくて済むところに工場を作りたい。ということで、消費地の近くに工場を建ててしまえということになったわけです。
また、ルイ・ヴィトンなどの高級服飾品、印刷・出版業は流行などの豊富な情報を求めて市場近くに立地する。
労働力指向型
代表例:繊維産業(縫製)、電気機械などの組み立て
製造に大量の労働力を必要とする工業。
例えば縫製産業。服を縫うというのは機械にはできない難しい仕事で、絶対に人の力が必要です。
定価1万2000円のチノパンがあるとしましょう。このうち製造原価は約4200円。このうち1500円が縫製にかかる人件費です。実に原価の1/3以上。高いですねー。
中国で縫製を行ってもこれですから、日本で縫製したとしたら人件費は5倍くらいかかります。そうすると原価は約10000円になり、販売価格は同じ原価率だと3万円になります。こんなの高くて買えません。
アパレルは、こんなにも人件費が価格に影響を及ぼすのです。だからユニクロやH&Mはバングラデシュとかカンボジアとかベトナムとか中国で生産を行うんですね。
また、電子機器の組み立ても大量の労働力が必要ですから、これも中国の得意分野です。みなさんのiphoneやパソコンは中国で組み立てられています。ほぼ確実に。
部品は世界各国で作って、中国に運んで組み立てるといったことがよく行われています。
集積指向型
代表例:自動車産業
自動車1台に何個の部品が使われているか知ってますか?
答えは約3万点です。だから、部品を作る工場が組み立て工場の周りに集まってた方が部品が集めやすいですよね。
特にトヨタは、部品をほしいとき・ほしい量だけ届けてもらうジャスト・イン・タイム方式で生産性を爆上げして天下をとったんですが、これも部品工場が近くにあった方がやりやすいですよね。
臨空港指向型
代表例:半導体などエレクトロニクス産業
半導体(IC)は小さくて軽く、高付加価値であるため製品価格に占める輸送費の割合が非常に低くなっています。
そこで、じゃあ飛行機で運んでしまえということになり、空港近くに工場が立地することとなりました。
この用語を含むファイル
関連動画
関連用語