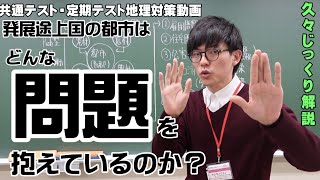都市人口率
都市人口率
全人口のうち都市に在住する人口の割合。
- 社会・経済が発展すればするほど(これをよく反映するのが一人当たりGNI)都市人口率が上がる
- ラテンアメリカは所得の割に都市人口率が高い
という傾向がある。
都市人口率の変化
一般論
農業中心の社会では、ほとんどの人々が田舎で農業をして暮らします。
商工業が発展していくと、都市が大きくなっていきます。都市の所得の高さを見た田舎の農民は都市に出稼ぎに行くようになり、都市に人口が流入していきます(pull要因)。
こうして都市に流入した人口は、第二次・第三次産業の労働力となって都市の発展を支え、第一次産業より儲かるこれらの産業が成長することによって国全体の所得も向上していきます。
多くの先進国はこの道を辿ってきているため、都市人口率が非常に高くなっています。日本では都市人口率が9割を超え、今後もさらなる上昇が見込まれています。一方で、カンボジアなどの未だに第一次産業が主となっている国では都市人口率は3割強と低水準です。
基本的に都市から農村への大規模な人口移動は起こらないので、都市人口率は右肩上がりになる、というのも押さえておきましょう。
ラテンアメリカの場合
ラテンアメリカで都市人口率が高い要因は大きく二つ、
- 入植を進めたヨーロッパ人が都市を拠点に開発を進めたこと
- 植民地時代の大土地所有制が残存し、自給的農業が未発達であること です。
特に二つ目の、自給的農業が未発達というのが大きな要因で、これが農村から都市へ人口を押し出すpush要因になっています。
南米ではごく少数の地主が極めて広大な土地を所有し、多くの農地は大地主によって所有されているため、自営農、家族経営の小農民が少数となっています。地主は農業労働者を雇い、所有する土地を耕作させているのです。
農業労働者としては、耕しているのは自分の土地ではないし、自分は土地を持っていない、そんな状況で田舎にいる理由がないわけです。となれば、職がある都会に行こう、それもできるだけ大きい都会、つまり首都に行けば儲かる仕事があるに違いない、と信じて、田舎から都会、それも首都に人口が集まるのです。
これがラテンアメリカで都市人口率が高い背景であり、かつプライメートシティ問題にも繋がっています。
都市人口率推移の傾向から導かれること
都市人口率の推移は以上に述べたような傾向を持つため、以下のようなことが言えます。
- 発展途上国は都市人口率が低く、先進国は都市人口率が高い
- 同じ国でも、年代を追うごとに都市人口率が上がる
これがわかっていれば、殆どの問題が解けるようになります。簡単ですね。
余談1~人口一位の都道府県の話
明治維新以降藩に代わって道府県が置かれ、各都道府県の人口調査が行われるようになりました。その頃の人口の順位は、今とは全く異なるものでした。
東京府(当時は東京は都ではなく府でした)が初めて人口一位になるのは明治30年で、それ以前は地方の田舎の府県が一位を占めていました。その中でも、新潟県は頻繁に日本一の座に輝いています。
新潟県の特徴といえば、日本有数の米どころ。当時の都市人口率は極めて低く、農村に多くの人が住んでいたため、農業が盛んな地域に多くの人が集まっていたのですね。
そして日本の工業化が進み都市人口率が上がってくる大正以降は、戦時中の一時期を除いて東京府(東京都)が現在まで続くようになりました。
余談2~push要因とpull要因
農村から都市に人口が移動する要因には、
- 農村が嫌になって出ていきたくなる・・・農村から押し出されるpush要因
- 都市に魅力を感じて都市に行きたくなる・・・都市に引きつけられるpull要因
があります。
先進国での都市化はpull要因によるものが多いのですが、ラテンアメリカにおいては特にpush要因が強くみられることが特徴です。
pull要因なら都市に必要な人材を引っ張ってくるだけなので問題は少ないのですが、push要因だと勝手に人口が入ってくるため、簡単に言うと都市で人口が余るのです。都市は多すぎる労働力を吸収できず雇用は飽和、流入してきた人々は満足に職が得られず、無職となった彼らは土地を不法占拠し、バラックを建ててその日暮らしを余儀なくされることになります。これが俗にいうスラムの形成です。
余談3~当てにならない統計
実は都市人口率というのは非常に曖昧な統計です。
え、なんで、と思われる方もいるでしょうが、都市と農村を明確に分ける基準とは何でしょうか? 都市と農村の間にある地域はどっちに入るのでしょうか? そう考えてみれば、「都市」や「農村」がいかに曖昧な言葉であることが分かると思います。
このように農村地域と都市部の正確な把握は不可能であるため、日本では便宜的に「市域を都市とする」という方策をとっています。つまるところ、「〇〇市」に住む人は全員都市の住民とみなす、ということです。
相当無理がある話ですよね。「市内」であっても、ド田舎だしこれ100%農村だろっていう地域も普通にあります。まして日本では平成の大合併以降市が圧倒的に多数派となり、人っ子一人いない深山幽境の地でさえ市に含まれるようになってしまいました。
そんな日本の現状を考えると、日本の都市人口率9割というのはかなり疑問が残ります。実際に「都会に住んでいる」人は、本当はもっと少ないのでしょう。どれくらい減るのか分かりませんが…
この用語を含むファイル
関連動画