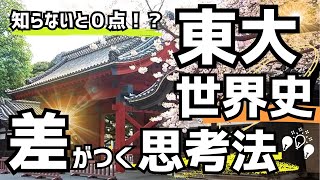戦争の助長要因と抑制要因(東大世界史2006年)
概要
動画投稿日|2023年10月26日
動画の長さ|26:38
東大世界史の難しさは「概念理解」にあります。
抽象的な概念が入っていないと、何を答えて良いのかがわからないということが生じます。
この問題は、東大の世界史でよく問われる概念理解を全部乗っけたような「おいしい問題」です。
概念理解がわかってくると、世界史の勉強法においても「具体→抽象」「抽象→具体」と行き来することが大切であるということが見えてきます。
こうした意味で、東大世界史の過去問の中でも2006年の「戦争の助長要因と抑制要因」は、東大世界史の差がつく一問です。
この問題を経験したか否かということで、東大世界史の得点力が大きく変わってきます。
実は新課程の歴史総合においても、この概念理解は強調されているため、今後の東大で出題される問題においても役に立つと思います。
知的好奇心が触発され、夢中になる東大世界史の良問ですので、動画を視聴しながらぜひ一緒に考えてみてください。
〇世界史入試問題解説(東大、京大、一橋、早慶、共通テスト)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGNV-BpzR5Gp1ArXMZdE23XUB8FysNnOf
〇松山の世界史チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC8R78CtUj0uQOUM2wx-H1-A
①高1授業動画(古代史)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGNV-BpzR5GrNlyZzUl70npjkmccxDDwK
②高2授業動画(中世史・近世史)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGNV-BpzR5GpWUFpHSF2KrKposkdg-QWn
③高3授業動画(近現代史)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGNV-BpzR5GoIlth4k7RyXo0fKP22obiD
解答のポイント
1.三十年戦争
助長①新教諸侯・旧教諸侯の対立に諸外国が国益により介入
②各国が傭兵制をとったことで戦争は長期化、休戦期には略奪が発生
③ウェストファリア条約で主権国家体制が成立、主権国家間の対立が戦争を助長する危険
抑制④グロティウスは『戦争と平和の法』で国際法により国家間の戦争を抑止することを提唱
2.フランス革命戦争
助長⑤革命防衛の必要からナショナリズムが高まる
⑥徴兵制により国民軍を編成したナポレオンが各国を征服し、各国にナショナリズムが伝播
抑制⑦ウィーン体制が成立し、正統主義と勢力均衡の原則の下、ヨーロッパの秩序を再編し、
大国により自由主義・ナショナリズムの抑制
3.第一次世界大戦
助長⑧帝国主義列強の植民地獲得競争
⑨秘密外交により三国同盟・三国協商が成立、こうした同盟関係が多くの国々を戦争に巻き込むことになった。
⑩第一次世界大戦は国力を総動員する総力戦、戦車・飛行機などの新兵器が戦争の犠牲者を増大
抑制⑪レーニンは平和に関する布告で無併合、無賠償、民族自決を打ち出し、講和
⑫ウィルソンの十四ヵ条で軍備縮小、秘密外交の廃止を訴えた。
⑬国際連盟が設立され、集団安全保障の下で戦争を抑止する仕組みが採用
この動画を含むファイル
関連動画
関連用語