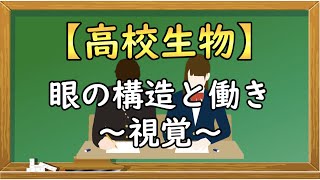暗順応のグラフとロドプシン【眼】 高校生物
概要
動画投稿日|2021年10月7日
動画の長さ|6:22
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
暗順応のグラフ(暗順応曲線)とロドプシン(オプシン・レチナール)について講義します。
語呂「俺たちのロード(オプシン、レチナール、ロドプシン)」
問題:明るい場所から暗い映画館に入ると、はじめは床の階段も見えないが、しばらくすると徐々に状況が見えてくる。このとき、階段を見るのに主に使われている視細胞は、錐体細胞と桿体細胞のどちらか。
答え:桿体細胞
問題:桿体細胞に含まれる視物質を何というか。
答え:ロドプシン
*動画の中で「錐体細胞と桿体細胞が網膜に並んでいる」と言っているが、その並び方は均一ではないことに注意。錐体細胞は黄斑に集中して分布しており、桿体細胞は黄斑(と盲斑)以外に分布しています。
視細胞の分布に関する講義はこちら↓
https://youtu.be/z-yAODgEpGA
*すみません、まるで黒板の上の方から光が差すような手の仕草をしているシーンがありますが、黒板に描かれた桿体細胞の向きを基準とすれば、光は桿体細胞の円板のある方(黒板上方)ではなく、核のある方(黒板下方)からやって来ることになります。教科書で桿体細胞が配置されている向きを確認しておいてください。
●暗いところから急に明るいところに出るとまぶしく感じるが、しばらくすると正常にもどる。これを明順応(めいじゅんのう)という。
●逆に、明るいところから暗い所に行くと、はじめは何も見えないが、しばらくすると正常に戻る。これを暗順応(あんじゅんのう)という。
●ロドプシンについて
・明順応、暗順応には、主に桿体細胞の中にあるロドプシンという視色素(視物質)が関係している。
・ロドプシンはオプシンというタンパク質と、ビタミンAの還元型であるレチナールからなる。
*レチナール(retinal)は「眼の網膜(retina[レチナ])に見出されるアルデヒド(接尾語 –al[アール])」という意味。ビタミンAはレチノール(retinol)とも呼ばれる。レチノールは、「レチナールと構造的に縁の深いアルコール(接尾語 ol[オール])」という意味。
・ロドプシンが多いと、弱い光を受容できる。つまり、光刺激に対する閾値が下がる(=感度が上がる)。
・桿体細胞の中にあるロドプシンに光が当たると、レチナールの構造が変化(シス型からトランス型へ変化)して、オプシンからはずれる(ロドプシンは分解する)。この反応がきっかけとなり、視細胞に電位変化が生じる。
・レチナールは、血液中から供給されるビタミンAからつくられる。ビタミンAが不足すると、夜盲症(暗順応障害を引き起こす疾患)になる。
・いきなりまぶしい所に出ると、桿体細胞のロドプシンが急に反応し、細胞が過剰に興奮してよく見えなくなる。
・ロドプシンが減少することで、桿体細胞の感度は下がってくる(明順応)。
・逆に暗い所では、ロドプシンが足りず、よく見えない。しかし、徐々にロドプシンが合成・蓄積され、桿体細胞の感度が上がる(暗順応)。
・活性化したロドプシンはすぐに不活性になり、さらに、構造変化を起こしたレチナールを放出してしまう。
・構造変化前のレチナールは色素上皮細胞から補給される。
・明るい場所では、ほとんどのロドプシンは分解されてしまっている。暗い場所に移り時間が経つと、だんだん色素上皮細胞から構造変化前のレチナールが補給され、ロドプシンは再合成されて行く。
・ヒトには3種(赤・青・緑)の錐体細胞がある。錐体細胞は黄斑に集中して分布している。それぞれの錐体細胞のオプシンのアミノ酸配列の違いにより、よく反応する色が異なる(錐体細胞の視物質に含まれるレチナールは桿体細胞と同様である。ただ、オプシンに相当するタンパク質部分のアミノ酸配列は異なる。そのアミノ酸配列の違いが、それぞれの錐体細胞が反応する色の違いに繋がっている。)。
・暗順応の前半では錐体細胞の感度上昇が起こり、後半では桿体細胞の感度上昇が起こる(錐体細胞は、かん体細胞より、感度は低いが、応答が速いことが知られている)。
●桿体細胞で光が電気信号に変換されるまで
①光によって桿体細胞の円板膜上にあるロドプシンが活性化し、活性化したロドプシンはGタンパク質(トランスデューシン)を活性化させる。
*トランスデューシンはGタンパク質であり、活性化されると、GDP結合型からGTP結合型に変化する(GDPと結合していたのが、GTPと結合するようになる)。
②トランスデューシンはホスホジエステラーゼ(cGMP分解酵素)を活性化させる。
③ホスホジエステラーゼによって、cGMPが分解され、細胞質のcGMA濃度が下がる。すると、ナトリウムチャネルと結合しているcGMPの量が低下して、ナトリウムチャネルが閉じる。このNa+流入の阻害は、桿体細胞の過分極を引き起こす。
④すると、桿体細胞から放出されるグルタミン酸の量が減少する。この情報が脳へ伝わる。
このように、光のシグナルは細胞膜に迅速に伝わり、細胞膜の過分極を通じて電気的なシグナルに変換される(今回の場合、面白いことに、受容器電位[感覚刺激に応じて受容器に発生する電位変化]は、脱分極ではなく、過分極である)。
noteに簡単な図がある。
https://note.com/yaguchihappy/n/n4e5dd145afbc#309b0bd6-b3a8-4803-95d5-c7470025a8d0
●ロドプシンは赤い。ロドプシンの語源は「rhod=バラ、posing=視覚に関する」である。
●薄暗いところで色がわからないのは、主に桿体細胞が働いているからである(色覚に関与しているのは錐体細胞である)。
●当然(他の動物生理の授業も同様だが)、「我々は錐体細胞と桿体細胞をもつ」と言っても、そんなことにはいくらでも例外があり、さまざまな個性を持つ人がいることは言うまでもない。念のため。
●詩人ゲーテは、明暗調節について研究している。「網膜は、光あるいは闇がそれに作用するのに応じて二つの異なった状態にあり、これらの状態は相互にまったく対立している。」「われわれが強く証明された白い面に目を向けると、眼はくらんで、しばらくは適度に照らされた対象を識別することができない。」「白昼の明るい所から薄暗い場所へ移る人は誰でも、最初は何も識別することができない。」ゲーテ『色彩論』目に対する光と闇の関係より
●錐体細胞の視物質に含まれるレチナールは桿体細胞と同様である。ただ、オプシンに相当するタンパク質部分(フォトプシンと言う)のアミノ酸配列は異なる。
また、そのフォトプシンのアミノ酸配列の違いが、それぞれの錐体細胞が反応する色の違いに繋がっている。
●桿体細胞のロドプシンのオプシンと、錐体細胞のヒト緑などのオプシンを言い分ける時、前者をスコトプシン、後者をフォトプシンと言う。(この説明は岩波生物学辞典とガイトン生理学に基づくが、オプシンやフォトプシンの定義が完全に統一されていない。あまり高校生は気にしなくていい。)
●本来、桿体細胞の視物質をロドプシンと言うのであって、錐体細胞の視物質はロドプシンとは言わない。「錐体の視物質cone photopigments」などとよばれる。錐体細胞の視物質は、ヒト緑、ニワトリ青などと同定された動物名をつけて呼ぶ。
●オプシンについて、桿体細胞と錐体細胞で区別するときは、桿体細胞のオプシンをスコトプシンといい(桿体オプシン rod opsin=スコトプシン scotopsin)、錐体細胞のオプシンをフォトプシン(赤オプシン、緑オプシン、青オプシンなどともよぶ)という。
●錐体細胞は、順応に限らず、視覚に関わる化学反応全般の速度が大きいことが知られている。
●錐体細胞のみの曲線は、桿体細胞機能不全を起こしている夜盲症の方に協力していただいたり、錐体細胞のみが分布する中心窩に光を当てたりした場合に得られる。桿体細胞のみの曲線は、桿体一色型色覚の方に協力していただいたりすることで得られる。
●錐体細胞を持たない方、と言っているのは、正確には、機能不全を起こしていない錐体細胞を持たない方、と言う意味である。そしてそれは、医学では疾患と扱うが、見方を変えれば個性の一つである。念のため。
●暗順応はロドプシンの再生速度のみでは議論できない。背景光およびテスト光の強さ、広がり、波長、時間、瞳孔の大きさ、網膜部位に影響される。
●古生代以前に、動物は色覚を獲得していたと考えられている。6億年前、赤と緑の混合オプシンと、青オプシンがつくられたらしい。
4000万年前、赤と緑の混合オプシンは、赤オプシンと緑オプシンに分かれ、人類を含む旧世界ザルは、赤、緑、青の三色系で世界を見ることになった。
(南米の新世界ザルは、混合オプシンのままで、二色系である)。
赤オプシンと緑オプシンの遺伝子はX染色体上にとなりあって存在しているのは、この2つが遺伝子重複によって生じたからである可能性が高い。
●視細胞の下にある色素細胞層は、広義の網膜に含める。ビタミンAが大量に含まれており、ロドプシンの再生に働く。
#高校生物
#暗順応
#ロドプシン
関連動画
関連用語