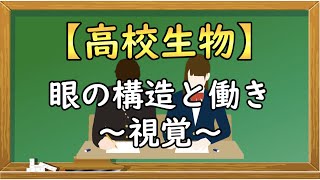暗順応
暗順応とは
明るい場所から急に暗い場所にいくと、最初は真っ暗で何も見えないが、だんだん目が慣れて見えるようになる、という現象を体験したことはないだろうか。そのような現象を、暗順応という。
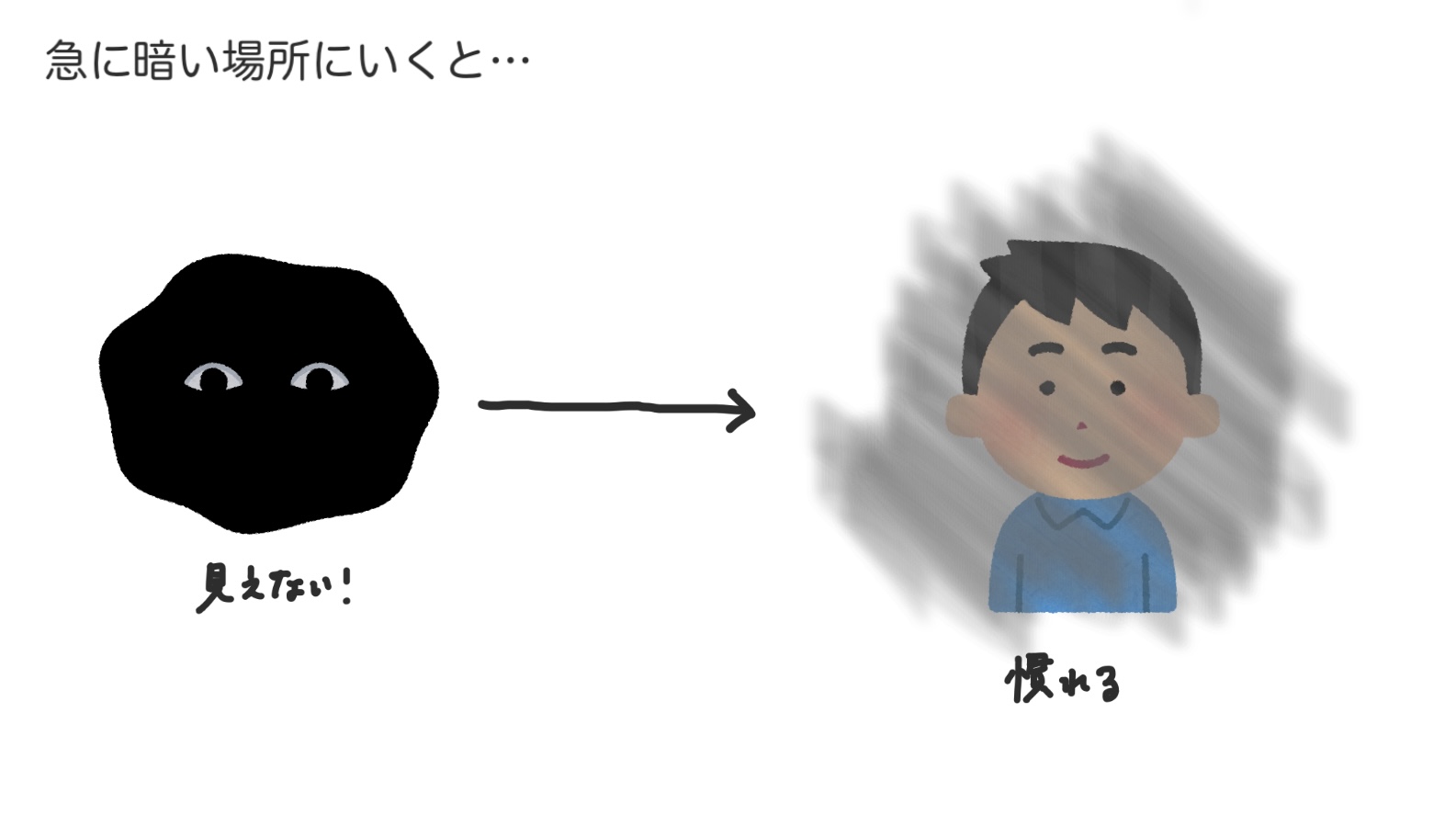
体験したことがない人は、一度明るい部屋から暗い部屋に移動してみよう!
暗順応はなぜ起こる?
暗い場所でだんだんものが見えるようになるのは、だんだん眼の感度が上がるから。
もう少し具体的に言うと、暗い場所では網膜で光を受容する視細胞の感度が上がるのが、原因なのである。
暗順応について、高校生物では、
- いつどの視細胞がはたらくのか
- 視細胞の感度が上がるしくみ
をしっかり理解しておこう!
いつどの視細胞がはたらくの?
視細胞には、
- 明暗と色を感知する「錐体細胞」
- 明暗のみを感知する「桿体細胞」
の2種類がある。
視細胞は2種類とも、暗くなると感度が上がる。
明るい場所では、主に錐体細胞がはたらいている。そのため、明るい場所から暗い場所に移動した直後には、まず明るいときにはたらいていた錐体細胞の感度が徐々に上がる。
そして10分ほど経過すると、今度は桿体細胞の感度が大きく上がる。この時の桿体細胞の感度は、錐体細胞よりも高くなるため、桿体細胞が中心にはたらくようになる。
このように暗所で感度が徐々に上がる様子は、以下のような、
やっと感じられる明るさの閾値が低下する図
で表されることが多い。
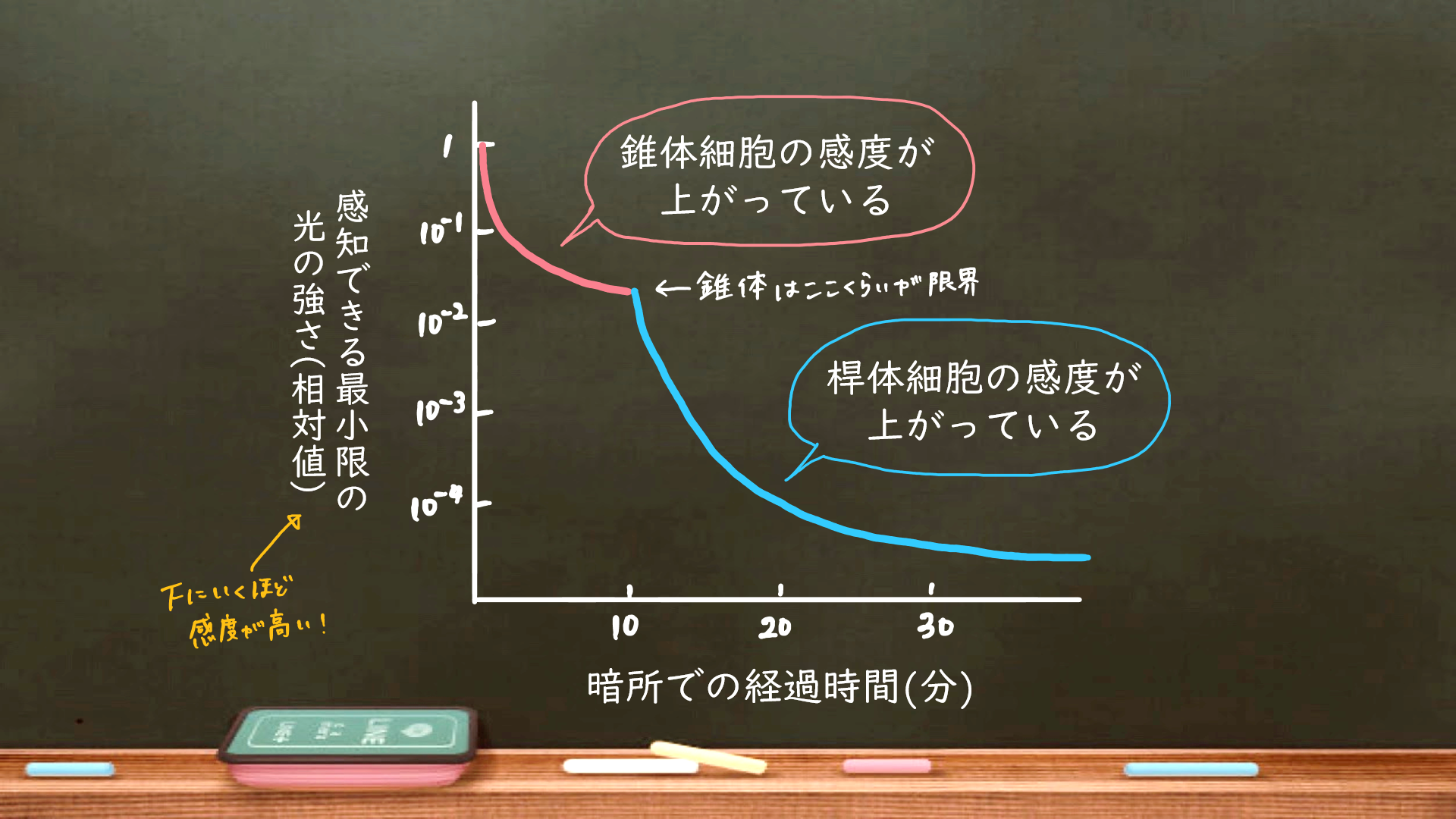
この図から、時間が経つほどやっと感知できる光の強さが低下する、つまり、弱い光が見えるようになっていくことが読み取れる。また、2つの曲線が組み合わさっているが、この左の曲線が錐体細胞のはたらき、右の曲線が桿体細胞のはたらきによるものになっている。
よって、暗順応が起こるとき、始めは錐体細胞の感度が上がり、次にさらに桿体細胞の感度が上がり、桿体細胞が中心にはたらくようになるということを覚えておこう。
感度が上がるしくみ
では次に、桿体細胞がどのようにして感度を上げるのか見ていこう。
桿体細胞には、「ロドプシン」と呼ばれる物質が含まれている。
ロドプシンは光を受容する物質で、このロドプシンが多いほど桿体細胞の感度が上がり、弱い光でも感知できるようになるのである。
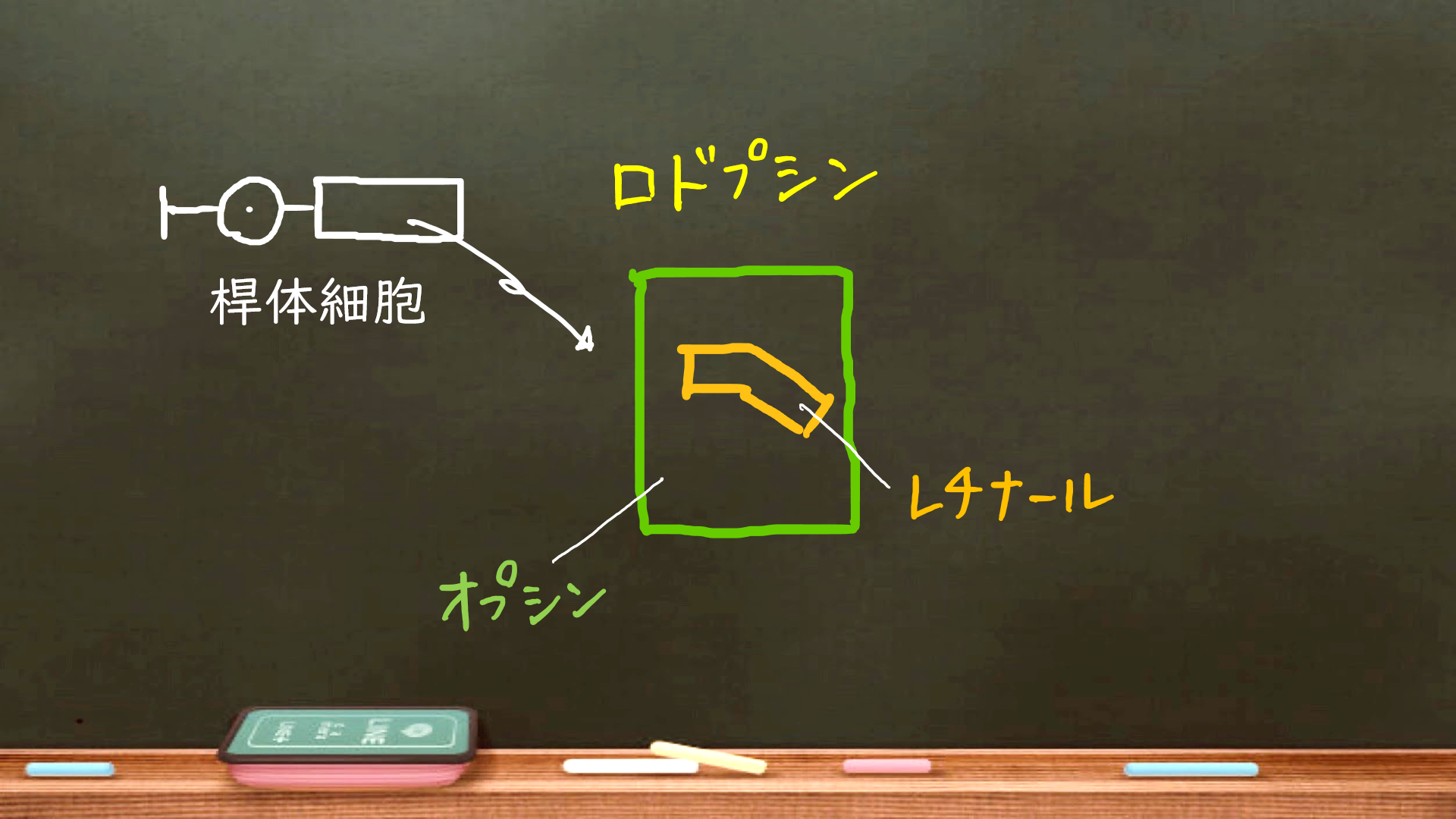 ロドプシンは、オプシンと呼ばれるたんぱく質にレチナールという物質が結合した構造になっている。
ロドプシンは、オプシンと呼ばれるたんぱく質にレチナールという物質が結合した構造になっている。
レチナールは、光を吸収すると形が変わり、オプシンから離れてしまう。そのため、明るい場所では、多くの光を吸収するのでロドプシンが減少し、桿体細胞の感度は下がる。
一方暗所では、レチナールが再びオプシンと結合してロドプシンが合成されるので、だんだんロドプシンが合成され、蓄積されていき、桿体細胞の感度は上がる。
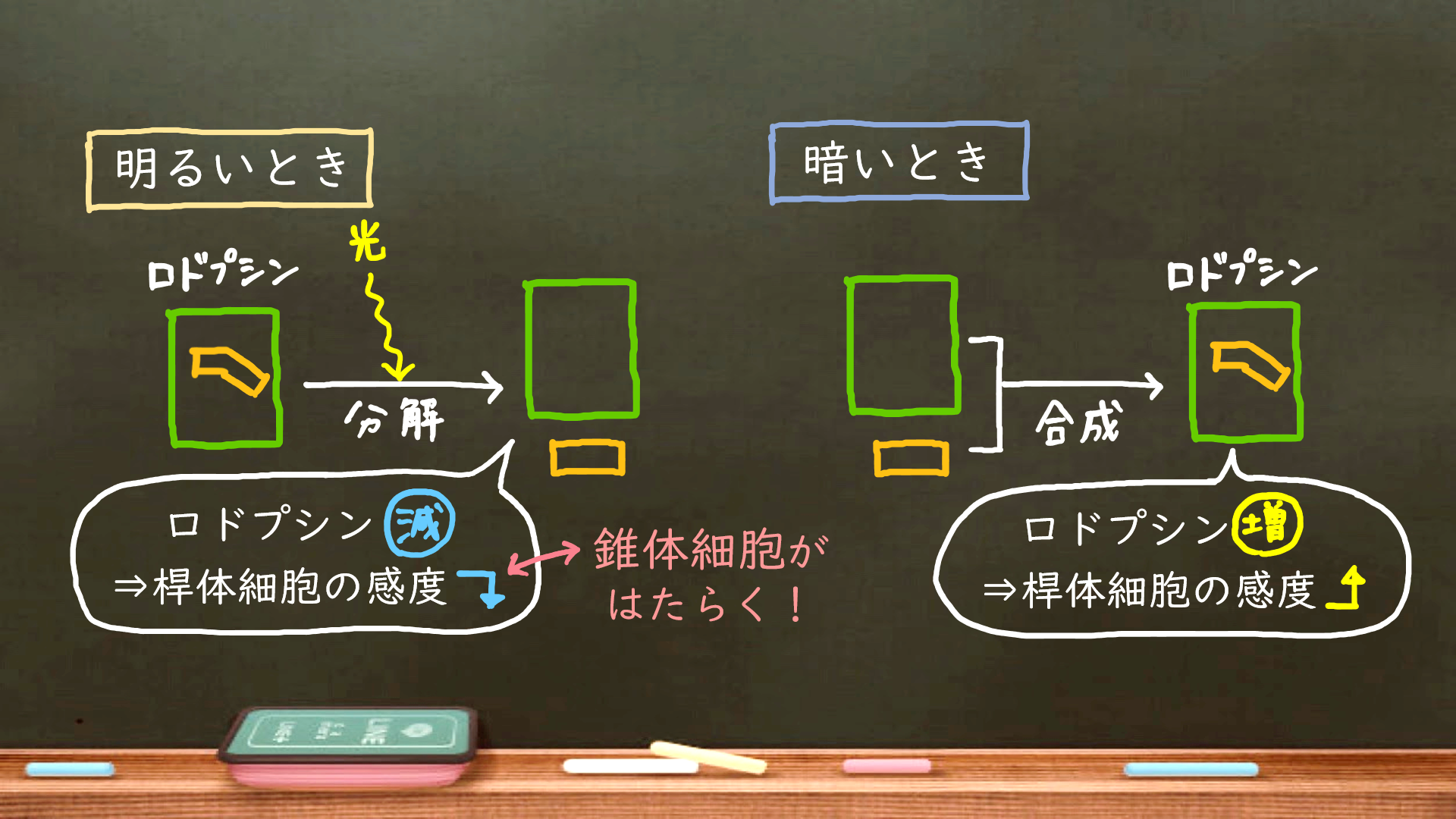
つまり、暗い場所に入るとロドプシンが合成されて増えるため、眼の感度が上がるのだ。
これが、暗順応のしくみなのである。
ちなみに
逆に、暗い場所から急に明るい場所にいくと、最初はまぶしくて物が見えにくいが、時間がたつとまぶしくなくなる。
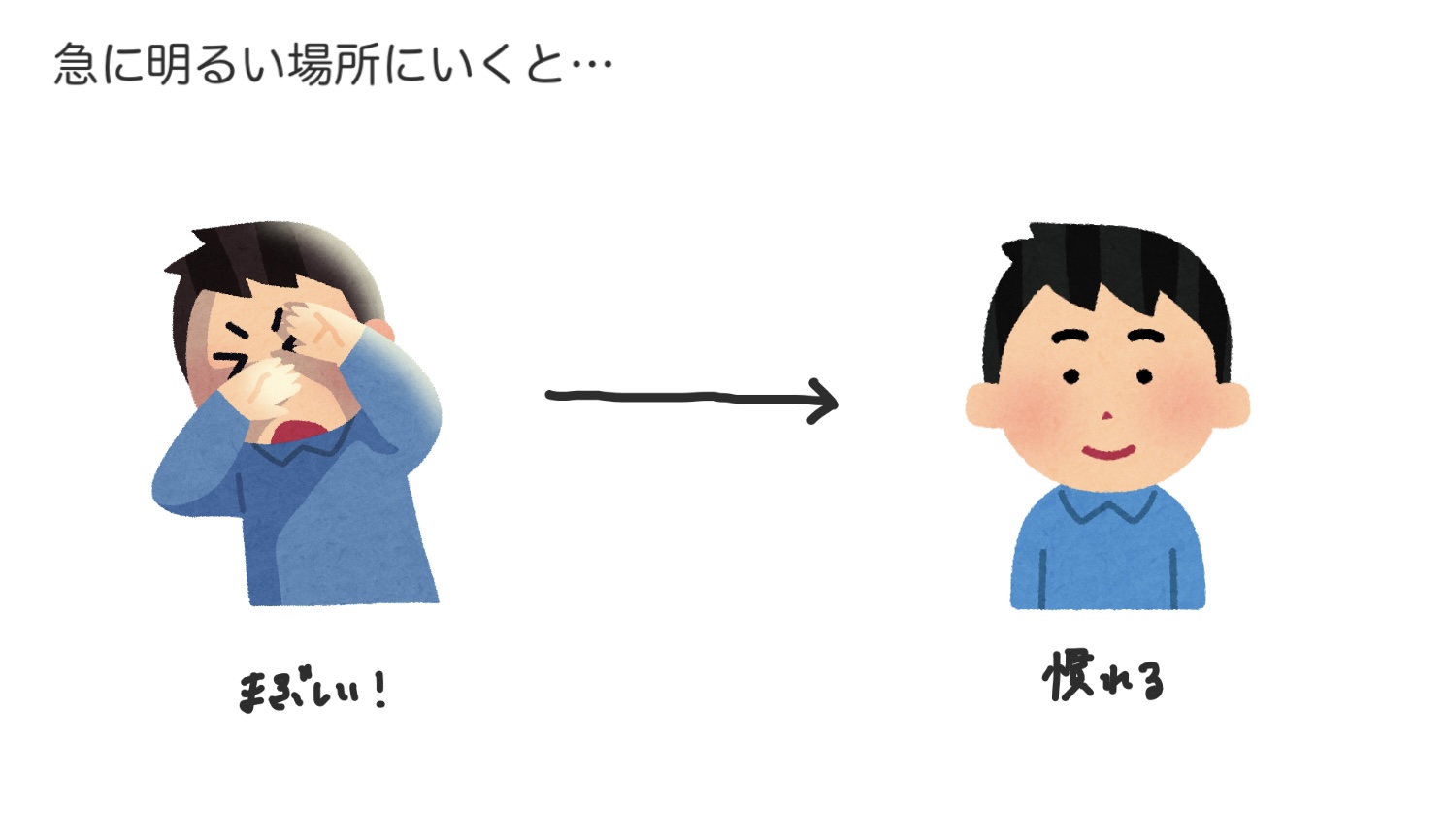 この暗順応と逆の現象のことを、明順応と言う。
この暗順応と逆の現象のことを、明順応と言う。
暗順応と明順応について、動画で学びたい人は、 「おうち生物 暗順応と明順応」をチェック!
この用語を含むファイル
関連動画
関連用語