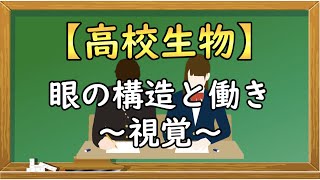視細胞の分布を表すグラフ【眼】 高校生物
概要
動画投稿日|2021年7月10日
動画の長さ|3:09
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
視細胞(錐体細胞・桿体細胞)の分布を表すグラフについて解説します。
語呂に「おお!色々衰退してしまった!(黄斑、色覚に関与する錐体細胞)」
●目に関する基礎講義
眼① https://youtu.be/Cqh2omOMGAY
眼② https://youtu.be/e_ucu7ITikw
暗順応とロドプシン https://youtu.be/tQY6TillY3w
●1個の眼球の網膜には約600万個の錐体細胞と、1億2000万個の桿体(かんたい)細胞が存在している。
桿体細胞は、光に対する閾値が、暗いところではものすごく小さくなる。つまり、薄明下で物を見るときに働く。かん体は基本的に色を識別できないので、薄明かりでは色の識別はできない。(暗順応において、暗所に入った直後はよく物が見えないが、桿体細胞でロドプシンが合成され、ロドプシンの増加が起こると、よく見えるようになる)
●錐体細胞には、青、緑、赤の3種類が存在し、明るいところで色覚に働いている。(ただし、暗所に入った瞬間に、多少閾値は落ちる、つまり多少の感度上昇は起きる)。
●黄斑の中心には、中心窩(ちゅうしんか)という小さな窪みがある。ここに錐体細胞が集中して存在する。
●視細胞がどういう向きで配置されているかもチェックしておこう。図で出題される。
●盲斑(盲点)は視神経の出口であり、視細胞が分布していない(盲斑に光が当たっても感知できない)。
#眼
#生理学
#高校生物
関連動画
関連用語