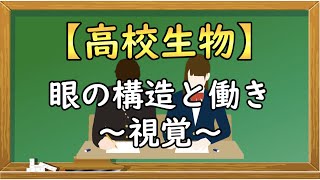【眼②】視細胞・黄斑・盲点(盲斑) 高校生物
概要
動画投稿日|2021年3月11日
動画の長さ|5:16
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
眼の、黄斑や盲点(盲斑)について講義します。
語呂「ガラスの恋、もう、脈はないと知って強くなる(光が入る方から順番にある構造。ガラス体、網膜、脈絡膜、強膜)」
語呂「王の中心は衰退(黄斑の中心は中心窩といい、錐体細胞が集中)」
●錐体細胞(色覚に関与)は黄斑に集中して分布する。
●桿体細胞(薄暗い所でも働くことができる)は黄斑と盲斑(盲点)以外に分布する。
*黄斑は眼球後極のやや耳寄りにある、径2mmほどの領域である。その中心に中心窩(ちゅうしんか)というくぼみがある。中心窩は血管を欠き視細胞が密に分布しているため視力が最も大きく、視軸はここを通る。黄斑と中心窩を同義とすることもある。
●視神経が眼の外へ出ていく部分を盲点(もうてん。盲斑[もうはん]ともいう)という。盲点には、視細胞は存在しない(視神経が貫いている)ので、ここでは光を受容することができない。
盲点の存在が日常の中で自覚できない原因の一つは、両眼視では、盲点が左右の視野の重複している領域に含まれるので、欠損が補われるからである。
問題:2種類の視細胞を答えよ。また、色覚に関わるのはどちらか。
答え:錐体細胞、かん体細胞
色覚に関わるのは錐体細胞
視細胞のグラフ(視細胞の分布) https://youtu.be/z-yAODgEpGA
暗順応(ロドプシンなど)https://youtu.be/tQY6TillY3w
●暗い星を見るときは、その方向をまっすぐ見てはいけない。なぜなら、その星をまっすぐ見ると、その星からくる光は、黄斑に当たってしまうからである。黄斑には、ほぼ錐体細胞のみが存在している。錐体細胞は色を見分けるエキスパートですが、暗いところではよくはたらかない。だから、暗い星を見るときは、まっすぐその星のほうを見ず、少し視線をはずすとよい。網膜の桿体細胞のあるところ(黄斑以外の場所)なら、薄暗い中で感度よく光をキャッチすることができる。
視神経の通路、盲点は、黄斑より鼻側にある(視神経は顔の中央にある脳へ情報を送るから)。
●黄斑=中心窩とすることもある。
●錐体細胞は、青,緑,赤に極大感度をもつ3種類がある。錐体細胞は明所視で色覚を司る。網膜全体で600万~700万個ある。鳥類で発達している。
●かん体細胞は暗所視で光覚を司る。漢字で桿体細胞と書き、桿状、つまり細い棒状であるのでこの名称がある。網膜全体で約1億個ある。夜行性のネコで発達している。
#生物
#黄斑
#盲点
関連動画
関連用語