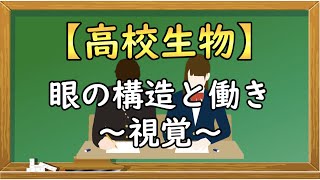【眼①】眼の構造 高校生物
概要
動画投稿日|2021年3月11日
動画の長さ|7:59
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
眼について講義します。
語呂「こう彩が交際(こう彩の断面が、なんだか二つの突起が向かい合って交際しているように見える)」見えないよね、すみません。
●眼の適刺激は光である。
①強膜
眼は、白色の厚い結合組織(強膜)で包まれたほぼ球状の器官である。
*強膜と網膜の間には、脈絡膜(みゃくらくまく)という、血管が豊富な薄い膜が存在する(脈絡膜には豊富なメラニン色素が存在し、光を吸収している[眼球内の光の反射や散乱を防いでいる]。また、脈絡膜には、網膜に栄養を与えるなどの働きがある)。
②角膜
光は、強膜とつながっている角膜を通じて眼球内に入る。
*血管は光を遮るので角膜には血管がない。
③網膜
一番内側の膜が網膜である。
視神経が眼の外へ出ていく部分を盲点(盲斑)という。盲点には、視細胞は存在しない(視神経が貫いている)ので、ここでは光を受容することができない。
*ヒトの眼はカメラ状であり、カメラ眼と呼ばれる(ただし、ヒトの眼は水晶体[レンズ]の厚さを変えてピントを合わせるのに対し、普通のカメラはレンズを移動させてピントを合わせる)。軟体動物であるタコなどの眼では、視細胞の光を吸収する場所の『後ろ(ヒトと逆)』に軸索が位置しているため、網膜には視細胞がとぎれることなく並んでいる。そのため、タコには盲斑がない
*オウムガイなどの眼には水晶体がなく、ピンホール眼と呼ばれる。
*昆虫は複眼を持つ。複眼は、個眼とよばれる光検出器が数千個集まったものである。複眼は、動きの検出に非常に優れている。昆虫が映画を見る時、映像が途切れていることに気付くであろう。昆虫の複眼は一般に短波長の光にも敏感で、紫外線を感じ、偏光感受能力も認められる。
網膜にある連絡神経細胞は、視細胞が受け取った光刺激を調節(コントラストを調節したりなど)している。
色素上皮細胞は、その名の通り色素を含む細胞。光の乱反射を防ぐ(眼の内側は真っ黒に見える)。また、視細胞にレチナールを供給している。
*色素上皮細胞は網膜に含めないことがある。
⓸錐体細胞・桿体細胞
ヒトの網膜には錐体細胞(すいたいさいぼう)と桿体細胞(かんたいさいぼう)がある。
錐体細胞は明るい所ではたらき、主に色覚に関与する(したがって薄暗い所では色が識別しにくい)。
桿体細胞はうす暗い所でもはたらく(明暗を鋭敏に区別する)。
ヒトの網膜には、430nm付近、530nm付近、560nm付近の光をよく吸収する、3種類の錐体細胞(それぞれ、青錐体細胞・緑錐体細胞・赤錐体細胞)がある。
*赤錐体細胞の吸収する波長のピークは、実際は黄色の波長だが、赤色(650nm以上)の波長を吸収できるのは赤錐体細胞のみである。
*脳は、3種類の錐体細胞(赤・緑・青)の読み取りの比較に基づいて色を決定する。たとえば、すべての種類の錐体細胞が同程度に活性化した場合、私たちは「白色」を知覚する(ノートが白色に見えるのは、ノートから来る光が、3種類の錐体細胞を同程度に活性化させるからである)。
⑤水晶体
水晶体(すいしょうたい):透明である。遠くを見る時、近くを見る時で厚さが変化する。水晶体はクリスタリンというタンパク質を豊富に含む。
*水晶体とレンズを同義のように扱うことも多い。厳密には、光感覚器官・発光器官の前に位置する通光・屈折の機能をもつ構造体をレンズといい、そのうち、脊椎動物のカメラ眼のものを特に水晶体という。
⑥ガラス体
ガラス体(がらすたい)は、水とタンパク質からなるゼラチン状の物質である。
*ガラス体は、ぱんぱんに眼球内に詰まっており、網膜を強膜に押し付けてガラス体内にはがれてこないようにしている。
●視細胞のグラフ(視細胞の分布)についての講義はこちら
https://youtu.be/z-yAODgEpGA
●好きな人が近くにいると、ドキドキして、交感神経が優位になり、虹彩のはたらきで瞳孔が大きくなり、黒目が大きく見えてかわいく見えるという説(都市伝説?)がある。
●瞳孔は、虹彩 irisに囲まれた光の入射口で、その大きさは副交感神経支配の瞳孔括約筋(括約は「かつやく」と読む。括約は、輪っか上の筋肉が、閉じてしまる、というような意味)と、交感神経支配の瞳孔散大筋の緊張に基づく。
それぞれの筋肉が収縮すると、それぞれ、瞳孔が縮小、散大する。
*瞳孔括約筋が収縮=瞳孔縮小
*瞳孔散大筋が収縮=瞳孔散大
問題:瞳孔の大きさを調節するのは( X )である。( X )には瞳孔散大筋や瞳孔括約筋があり、それぞれ収縮することで瞳孔を拡張・収縮させる(それぞれの筋肉が収縮したときはもう一方は弛緩する)。( X )に入る語を答えよ。
答え:虹彩(こうさい)
#生理学
#高校生物
#眼
関連動画
関連用語