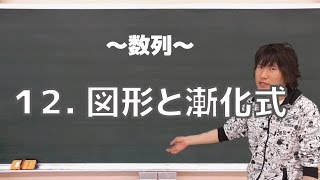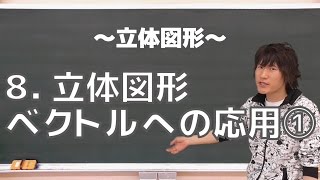ベクトル13:垂線とベクトルの基本表示②《慶応大理工学部2012年》
概要
動画投稿日|2025年7月25日
動画の長さ|33:20
ホームページ:http://mathematics-monster.jp
全講座の問題はホームページから閲覧・印刷可能です。
9月中旬まで授業の撮影をお休みします。ベクトルの続きを急ぐ人は2015年ごろに撮影したものを再生リストかホームページからご視聴ください。
数年前、生徒から「先生は自分の子供に自分の授業を見せたいですか?」というような質問を受けたことがあります。その答えからすると、このレベルの内容を理解できるほど受験勉強に打ち込む前に、なりたいものを見つけてそれに打ち込んでほしい、が本音です。自分の子供が何になろうと子供の人生だから別に構わないことを大前提として、自分の特性がある程度遺伝していることや子供の様子を見ていて、個人的には漫画家とかどうだろうかと思っています。子供は絵を描くのが好きだし物を作るのが大好きです。僕は少なくとも絵を描くのは得意な方でした。ただ僕は、自分の子供ほど、絵を描くのは好きじゃなかったと思います。
また、僕個人の考え方によるところが大きいかと思いますが、長期目線で見て自分が死んだ後も残るものを作ることに僕は興味関心があります。絵を描く仕事において、クレヨンしんちゃん、ドラえもん、コナン、ドラゴンボール、ワンピース、遊戯王など、後世に残っているものの多くは漫画から始まっていて、作者が亡くなった後も親しまれているように思います。スヌーピーなど海外の漫画キャラクターも僕は好きです。もちろん作者の努力や、星の数ほどの漫画家がいる上での、上記の作品であることは間違いないですが。
長期的に変化しないものという点では、数学にも共通するところがあり、数学の授業を撮影して残すという作業は何か物を作るという点で漫画と同じであり、自分が今の仕事を選んだことに悔いはないです。また、デジタルで複製可能という点も大きいです。
この世の中には対面でしかできない仕事と、非対面で複製可能な仕事の2つにざっくり分けることができ、今後の世の中は、基本後者の仕事に繋がらないかで考えるべきだと僕は思っています。例えば、音楽で言ったら、ピアノの先生やオーケストラの奏者は対面で稼ぐ仕事、それに対してシンガーソングライターは自分の楽曲をデジタルデータとして事実上無限に複製しYoutubeにアップして(ひと昔前はCDに複製して売る形)非対面でお金を稼ぐ仕事になります。
自分の向いているものの中からテレビ、SNS、雑誌などメディアを通して低コストで無限に複製できるものを提供する仕事を探すのが望ましいと僕は思います。逆に医療などは対面でしか施せないものがほとんどなので個人的にはどうなのかなと感じます。要するにいつまで経っても自分の時間の切り売りから抜け出せないわけです。
もう一つ言うと、できるだけ個人の色が出る仕事の方がいいと感じます。今後5年で新卒ホワイトカラーの仕事のほとんどはAIに奪われるそうで、AI関連のYoutubeを漁っているとわかりますが、AIがあまりに優秀すぎて正直新卒社員いらないです。なので個人の色が出せる絵や音楽、スポーツ、もの作り、芸能などの方向以外は今後40年を生きていくのは相当厳しいと思います。逆に個人の色が出せる仕事以外は無くなり、40年以内にはベーシックインカムが実現する可能性が結構あると感じます。まあ、考え方は人それぞれですが、一つの意見として。
撮影の仕方に関しても僕自身の考え方が出ています。直近の入試問題をひたすら毎年撮影するのではなく、各単元を20数題セットで残すという考え方や、新しく問題を構成し直すのではなく、2014年当時に選んだものを大事にし問題を差し替えず撮り直す点も長期目線で考えた結果です。差し替えてしまうと定期的に近年の問題に差し替え続けなくてはならなくなるので。さらに、問題を1題ごとで捉えるのではなく、ベクトルにしたら24題セットの構成で各問題の前後の繋がりやストーリー的な見方をしてほしいと思っています。さらに15年後にここで勉強する受験生と10年前にここで勉強した人とが、ここの問題を見て、「ああ、このベクトルの問題やったの覚えてるわ」とか会話が教育現場や親子間であったら面白いです。まあ、15年後一般入試がどれだけ残っているのか疑問なので、僕個人の自己満足かもしれませんが、そういう意図があります。
よくチャットGPTに今後のSNSについてや今後のYoutubeについて質問するのですが、理系の偏差値60以上の高校3年生はやはり毎年3万人程度しかいないから、登録者が年5000人増えれば充分だと返答されました。18歳の人口が105万人程度で大学進学率が60%だから大学に進むのは60万人ちょい、文系理系の比率は7:3だから、理系は20万人くらい。そのうち偏差値60以上は上位15%だから3万人くらいだそうです。その全員が一般入試を受けるわけではないし、文系の超上位層含めて多く見積もって5万人としても、確かに充分すぎます。受験が終わると同時に登録を解除する人が毎年数千人いることや、登録せずに利用する人を考えたら、年間1万人くらいの受験生に利用してもらっているのではないかと思います。ありがとうございます。
僕は短期的に小手先の手法で利用者を無理やり増やしたいとは微塵も思ってないので、今後も数年間は撮り直しを自分のペースでおこなうだけです。もし、これを読んでいる方々で、このチャンネルを知人に勧めたいという方がいたら、広めてもらえると僕は嬉しいです。ではまた9月に!
この動画を含むファイル
関連動画
関連用語