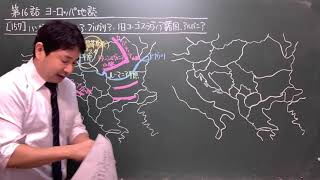カルスト地形
溶食地形
石灰岩質の地盤が水によって溶解してできた小地形。
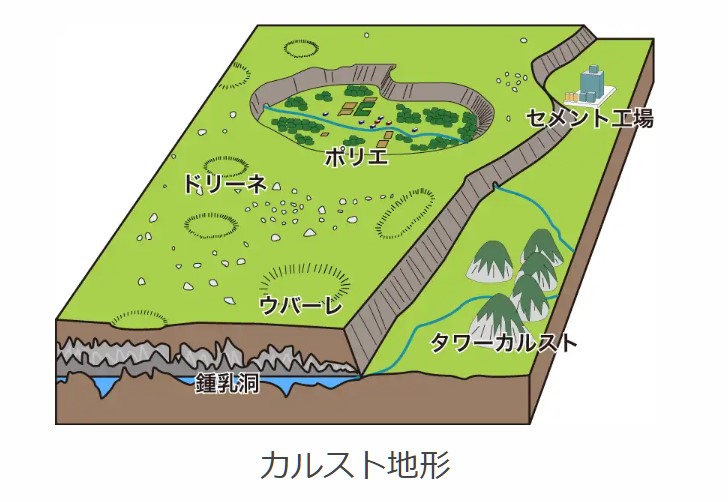 (ちとにとせさんより)
(ちとにとせさんより)
成因
雨水には二酸化炭素が溶け込んでおり、弱い酸性となっている。
酸性の水が石灰岩中の炭酸カルシウムを溶かし、カルスト地形が形成される。
そのため、
- 石灰岩の地盤
- 十分な降水
が成立要件となる。
分布
- 地中海沿岸
- 秋吉台、平尾台など
- 桂林(中国)
- ハロン湾(ベトナム)
などが有名。
地中海沿岸は特に石灰岩の分布が多い。ギリシアやイタリアの街並みや山が白っぽいのは、地盤が石灰岩質だから。これを連想すれば分かりやすいだろう。
また、テラロッサが石灰岩を母岩とする土壌だったことも思い出そう。

分類
ドリーネ
地下の石灰岩が溶食され、空洞ができたことで地面が陥没してできた小さな凹地。
 (ちとにとせさんより)
(ちとにとせさんより)
ウバーレ
いくつものドリーネが連結して形成された、大きな凹地。
湖沼になっているものも多い。
 (湖がウバーレ)
(湖がウバーレ)
ポリエ(溶食盆地)
大きいものは1000km²にも及ぶ、地面が陥没してできた盆地。
湖沼になっているものもある。

タワーカルスト
熱帯や亜熱帯の多雨地域で形成される。
周りの地面が激しく浸食され、浸食を受けなかった箇所が残り形成された。
桂林(中国)、ハロン湾(ベトナム)が有名。
鍾乳洞
溶食によって作られた地中の空洞。

(カレンフェルト)
ピナクルと呼ばれる小さい岩が林立している地形。
この言葉が聞かれることはあまりないので覚える必要はない。

この用語を含むファイル
関連動画
関連用語