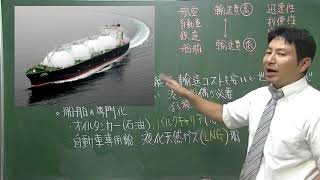運河
概要
運河とは、
「船舶の通行のために人工的に作られた水路」
のことです。
日本ではあまり見かけませんが、世界の交通の中では重要な役割を果たしています。
紅海と地中海を繋ぐスエズ運河、大平洋と大西洋を結ぶパナマ運河は有名であるほか、ヨーロッパには各地に運河が張り巡らされています。
運河の名前を丸暗記することにあまり価値はありませんが、主要なものは場所だけでも押さえておきましょう。
伝統的な運河
運河は古くから開削されており、中国の隋の時代から作られている大運河は有名です。
また、鉄道が実用化される前のヨーロッパでは運河の開削が盛んでした。当時の陸上交通と言えば馬車しかなく、内陸の交通で物資を大量に運ぶ手段が運河以外に無かったからです。イベリア半島の付け根を横断するミディ運河などですね。受験には出てこないので覚える必要はありません。
しかし、それ以降はより高速な鉄道や道路が発達したこともあり、河川・運河を用いた内陸水運は廃れていきました。
近代以降の運河
近代以降もそれまでのように運河の開削は行われていましたが、近代的な技術を駆使した大型の運河も作られるようになってきました。代表的なのがフランスの開削したスエズ運河、アメリカが建設したパナマ運河です。
両運河は世界の大洋を繋げ、航路を大幅に短絡する経路として古くから待ち望まれていたものであり、瞬く間に世界物流の大動脈となりました。今でも現役バリバリで稼働しています。
内陸運河
ヨーロッパは地形が低平であり、河川も多いことから運河の建設に適した地形で、さらに河況係数が小さいため古くから河川交通が盛んでした。
近世(16・17世紀~)以降、物流が盛んになったため、内陸の交通を円滑にすべく運河が大量に建設されました。特に絶対王政期のフランスや産業革命初期のイギリスでは建設が盛んに行われ、フランスなんかは運河と川だけで国内を一周できるくらい国内各地に運河が張り巡らされています。
また、アムステルダムやヴェネツィアなど、都市内の交通路として運河が整備された都市もありました。両都市では道路のように運河が利用されており、救急車として船が使われたりしているほどです。
水平式運河と閘門式運河
多くの運河は水位に差のない水平式運河ですが、水位に高低差がある運河では閘門と呼ばれる設備を用いて船を垂直移動させ、運河を渡らせています。
閘門式運河で有名なのはパナマ運河です。閘門の中に入った巨大な船が上下していく姿は圧巻ですね。
日本だと琵琶湖疏水の大津閘門や東京の荒川ロックゲートなどがあります。家が近い人は見に行ってみてはいかがでしょう。
関連動画