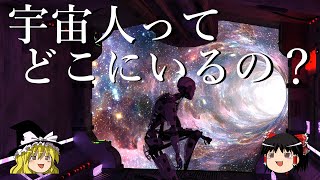【ゆっくり解説】今さらだけど二重スリット実験って何なの?
概要
動画投稿日|2022年7月5日
動画の長さ|21:27
聞いたことあるけど、結局どういう話なのかよくわからない、という皆様へ。
#ゆっくり解説 #ゆっくり科学 #量子力学
=======================
この動画含め、ネット上によくある二重スリット実験の動画は、説明の都合上いろいろとアレンジされています。言ってしまえばフィクションです。ここで軽くネタバラシしておきます。
①皆様も大好きな「どちらのスリットを通ったのか?を観測すると、スクリーンには2本線が現れる」について。この説明がなぜか世の中には溢れていますが、これは「かなり怪しい」ので、この動画では説明していません。ご存じの方は、根拠となる論文をぜひ教えてください。
強いて言えば、「どちらのスリットを通ったのか?を観測すると、干渉縞は消える」は正しいです(参考資料6)。
ただし、これは観測に伴う物理的な影響によるものであって、人の意識が〜という話では全くありません。そういう話を信じたい人はたくさんいますが。
カメラのスイッチをON/OFFするだけで結果が変わる!と言われる方もいますが、それも素人向けにわかりやすく表現されたものです。
量子の世界はカメラでは見えないので、もっとややこしい観測手法になるわけですが、仮にカメラで見るとしても、「光子を観測対象に大量にぶつけて、跳ね返ってきた光子を検出する」必要があります。
この時、観測対象が電子のようなめちゃくちゃ小さいモノであれば、光子をぶつけた時点で、電子の運動そのものがぐちゃぐちゃに変化してしまいます。
このように、相手に物理的なダメージを与えずに「観測」することは絶対に不可能です。そのため、量子のような小さな世界では、観測によって挙動が大きく変わってしまい、結果として干渉縞が消えてしまう、というだけの話です。
②実は、「電子」を用いた二重スリット実験では、「2本の隙間が空いた板」を使いません。「電子線バイプリズム」という、おそらく皆様の想像とは違う実験装置を使います(参考資料7)。
世にある解説記事や書籍などでは、「そんな細かいことを説明しても混乱するだけだよね」というスタンスで、イメージ重視の説明をしています。
③この動画含め、実験→解釈のような説明の順番は、実は全く歴史的な時系列に沿っていません。
この実験は、1800年代のヤングの実験に始まり、
現在でもまだ研究されている歴史の長いテーマですが、「単一電子」の二重スリット実験が実際に成功したのは、1974年と意外と最近です。(参考資料1)
一方で、ボーアとアインシュタインの論争など、
量子力学の解釈に関する議論は、1927年の第5回ソルベー会議(※)で活発に行われました。
なので、二重スリット実験の結果を、それ以前に議論された量子力学の解釈を使って説明するとどうなるのか?という、まあフィクションですね。
(※)ソルベー会議は、科学界のレヴェリー的なやつです。世界中の天才たちを集結して、その時々のHOTな問題を議論します。特に第5回は有名で、参加者27名のうち、17名がノーベル賞受賞者という激アツ会議でした。
=======================
【参考資料】
1.二重スリット実験 量子世界の実在に、どこまで迫れるか
(著)アニル・アナンサスワーミー, (訳)藤田貢崇
2.波動関数のわかりやすい説明
http://www.process.mtl.kyoto-u.ac.jp/pdf/lecture/analize/2015-(2).pdf
3.都合により非表示にします。
4.波と量子
http://www-surface.phys.s.u-tokyo.ac.jp/papers/2011/SuriKagaku201107-Hasegawa.pdf
5.哲学的な何か、あと科学とか
https://noexit.jp/tn/saiMenu.html
6.干渉と識別の相補性
http://www.phys.cs.is.nagoya-u.ac.jp/~tanimura/paper/mathsci2009.pdf
7.HITACHI 二重スリット実験
https://www.hitachi.co.jp/rd/research/materials/quantum/doubleslit/index.html
【音楽】
1.ホシノキセキ
関連動画
関連用語