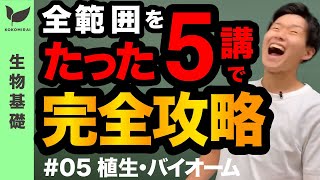バイオーム 高校生物基礎
概要
動画投稿日|2015年9月14日
動画の長さ|8:02
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
(語呂)「お昼にガキが寝てた(オヒルギ、フタバガキは熱帯多雨林によくみられる)」
お昼:オヒルギ
ガキ:フタバガキ
寝てた:熱帯多雨林
(語呂)「びろ~っと蛇があこう(赤う)なる亜熱帯(ビロウ、ヘゴ、ガジュマル、アコウは亜熱帯多雨林によくみられる)」
びろ~:ビロウ
へそが:ヘゴ
あこう:アコウ
(語呂)「雨がチクチク(雨緑樹林にはチークがよくみられる)」
雨:雨緑樹林
チクチク:チーク
(語呂)「関西のシカ食ったでしょうよ(日本の関西には照葉樹林が成立する。シイ、カシ、クスノキ、ツバキ、タ"ブノキは照葉樹林によくみられる)」
シカ:シイ、カシ
食った:クスノキ、ツバキ、タブノキ
しょう:照葉
(語呂)「夏は水飲むなら無難だ(夏緑樹林にはミズナラ、ブナがよくみられる)」
水飲むなら:ミズナラ
無難:ブナ
(語呂)「信用したのに、逃避コメントがしらける。エゾマツトドマツ。(針葉樹林にはトウヒ、コメツガ、シラビソ、エゾマツ、トドマツがよくみられる)」
信用:針葉樹林
逃避:トウヒ
コメント:コメツガ
しらける:シラビソ
*硬葉樹林の代表樹種「オリーブ」、「コルクガシ」は、地中海のリゾートで、ワインの「コルク」を開け、「オリーブ」オイルでパスタを味わうイメージで覚える。
硬葉樹林が成立する場所(地中海など)は、夏はからっと乾燥し、冬は湿潤=リゾート地に最適である(夏からっと乾燥し、冬が湿潤でひどく乾燥しないからリゾート地になる。日本にはそのような場所はほぼない。日本に硬葉樹林が成立しない)。
問題:ミズナラ、ブナなど、冬に落葉する広葉樹が優占するバイオームを何というか。
答え:夏緑樹林
問題:草原、荒原の種類を2つずつ答えよ。
答え:草原→サバンナ(熱帯草原)・ステップ(温帯草原)
荒原→ツンドラ(寒冷荒原)・砂漠(乾燥荒原)
●熱帯多雨林・亜熱帯多雨林(熱帯多雨林と亜熱帯多雨林は区別できないことも多い)
常緑広葉樹が主。熱帯多雨林では、非常に背の高い木や、つる植物や着生植物(他の樹木など、土壌以外のものの表面で固着生活する、すなわち着生する植物)が多い。
熱帯多雨林ではヒルギ、フタバガキが生育。
亜熱帯多雨林ではビロウ、ヘゴ、ガジュマル、アコウが生育。
*熱帯多雨林が成立するような環境は、月平均気温が高く年間降水量も多い、非常に植物にとって恵まれた環境である。
しかし、そこは植物にとっての楽園かと言うと、そうとも言えない。
自分にとって最適な環境は、他の生き物にとっても最適な環境であることが多い。(ディズニーランドがいつも混んでいるのと同じような理屈である。)
したがって、熱帯多雨林では、他の植物に巻きついて生きるつる植物や、他の植物に付着して生きる着生植物など、工夫して生きている姑息な(?)植物が多い。
また、競争の激しい陸上を離れ、水辺にマングローブを形成する植物がいるのも特徴である。ランドが混んでいたのでシーに行ったのである(冗談です)。
*熱帯では気温が高く、分解者のはたらきが活発なため、有機物はすぐに分解され、土壌は薄くなる。
●雨緑(うりょく)樹林
インドなど雨季と乾季がはっきりしている地域(熱帯)。乾季に落葉するチークなどが生育(乾季に落葉=雨季に緑=雨緑)。チーク材は家具材として有名。
●照葉(しょうよう)樹林
常緑広葉樹が主。クチクラの発達した葉(照葉)をもつ。シイ・カシ・クスノキ・ツバキ・タブノキが生育。
●硬葉(こうよう)樹林
夏に雨が少なく冬に雨が多い地域。常緑広葉樹が主。地中海沿岸に見られる。クチクラが厚く硬くて小さい葉をもつ。オリーブ・コルクガシが生育。
*硬葉樹林が成立する場所(地中海)は、夏はからっと乾燥し、冬は湿潤=リゾート地に最適である。
(夏に降水量が多くじめじめして、暑い所はリゾート地にならない)
*硬葉樹林に生育する樹種は、夏の乾燥に耐えるため、小さくて厚く硬い葉をもつ。また、幹も厚い樹皮に覆われている(厚い樹皮からコルクを採るコルクガシが有名である)。
●夏緑(かりょく)樹林
夏に雨量の多い地方に発達。落葉広葉樹(らくようこうようじゅ)からなる(冬に落葉する=冬に茶色=夏に緑)。
日本では本州東半分から北海道に分布。ミズナラ・ブナが生育。
*春、林冠の葉が茂る前に林床で開花するカタクリがみられる。
*夏緑樹林に優占する落葉広葉樹は、夏に葉をつけ、冬に落葉する。夏緑樹林では、夏になると、葉で光が遮られ、林床が暗くなる。カタクリは、夏緑樹林の林床に適応するように進化してきた。 カタクリは(冬を球根で越し、)早春に葉を伸ばし、開花し、初夏には地上部が枯れてしまう(夏緑樹林では、夏に林床が暗くなってしまう。よって夏に葉を展開させてもろくに光合成ができない)。
カタクリは、春先に一瞬だけ姿をあらわすので、「春の妖精(スプリング・エフェメラル)」と呼ばれる。
●針葉樹林
亜寒帯に広く分布。シラビソ、コメツガ、トウヒが生育。北海道ではエゾマツ・トドマツがみられる。
日本に生育する針葉樹には常緑が多いが、シベリアなどにみられるカラマツは落葉針葉樹。
*エゾマツ、トドマツは北海道に見られる。中部地方の亜高山帯にも針葉樹林が見られるが、ふつう、そこにエゾマツ、トドマツは分布しないので注意。
●サバンナ(熱帯草原)
イネ科草本が主体。アカシアなどの樹木が点在。
*サバンナは、もともと熱帯アフリカの現地語で、背の高いイネ科草本の草原に樹木が点在するような景観を指している。乾季には野火が見られる(したがって野火に対して抵抗力のある樹種が多い)。
*サバンナは、年降水量が200mm~1000mmで、はっきりした乾季のある亜熱帯・熱帯地方に見られる草原である。
●ステップ(温帯草原)
イネ科草本が主体。
*狭義の「ステップ」はユーラシア大陸の広大な面積に広がる温帯草原を指す。しかし、「ステップ」という語は温帯草原を指して使われることも多い。温帯草原は、北アメリカではプレーリー、南アメリカではパンパス、南アフリカではベルドと言ったように、地域ごとに呼び名が変わる。
●砂漠
降水量の極端に少ない地域。サボテンなどの多肉植物(茎や葉に水を蓄える)が多い。
●ツンドラ
北極圏など寒帯に分布。地衣類・コケ植物が主体。
●日本のバイオームの水平分布
北海道から針葉樹林、夏緑樹林、照葉樹林、亜熱帯多雨林
語呂「しん か しょ あ」
●日本の中部地方のバイオームの垂直分布
①高山帯ー高山草原(短い夏に一斉に花を咲かせる『お花畑』が成立)
ーーーーー森林限界(中部地方では2500m。北に行くほど下がる。)ーーーーー
②亜高山帯ー針葉樹林
③山地帯ー夏緑樹林
④低地帯ー照葉樹林
(「しん か しょ」の順番は水平分布と同じ。気温が境界線を決めているからである。標高が高い方が気温が下がる)
(北の方が寒いので、それぞれのバイオームの境界線は北の方が下がる。寒い所では寒さに適応している樹種が優占するからである。)
●日本は南北に長いだけではない。山が多い。なので豊かな水平分布だけでなく、豊かな垂直分布も見られる。近年、地球温暖化の影響で、気温が上がり、森林限界が上昇している。コマクサなどの美しい高山植物が絶滅してしまうかもしれない。
●森林限界は中部地方で2500mくらい(テストに出る)。森林限界より高い所には森林ができない。ただ、森林ができないだけで、高山帯にも低木(ハイマツ[地を這うように生える松]、コケモモ)は生育するから注意。
●地理的に異なる領域にある、同一のバイオームに、同じような特徴をもつ生物が生息していることがある。これらの生物種は、ふつう塩基配列レベルでは似ていない。したがって、彼等の形態学的類似性は、収束進化を反映していることになる。たとえば、サボテンとトウダイグサは、同じような形態だが(子供なら見分けがつかないだろう!)、遺伝的に近縁ではない。
*収束進化=系統の異なる複数の生物が類似する形質を個別に進化させること。
●教科書の図で、「硬葉樹林の範囲が、照葉樹林や夏緑樹林と重なってる!」と思った人がいるだろうか。図の縦軸と横軸は年降水量と年平均気温である。照葉樹林などが成立する気候パターンと硬葉樹林が成立する気候パターンは違うが、年降水量、年平均気温で見ると同じになってしまうのだ。
●生態系とバイオームを混同する受験生が多い。
バイオームはそのエリアに存在する『生物集団』を指す(生物集団の中で最もその環境に影響されるのは、移動のできない植物集団なので、植物集団[あるエリアに生息する植物集団は植生とよばれる]によってバイオームは特徴づけられる。大雑把に言えば、バイオームのタイトルには「照葉樹林」など、植物集団の名前がついている。漫画のタイトルが主人公の名前になっているようなもの)。
生態系とは、生物と『非生物的環境(土、光、温度、大気、水等)』をひとまとめにしてとらえた系(システム)のこと(「系」という字には、しくみとか、システムといった意味がある)。生物と非生物が影響を与え合っているというシステムも含む言葉なので、特定の物体を指す用語ではない。物質循環や、エネルギーの移動などのシステムも包括するような用語である。
穴埋め問題では、よくリード文を読み、「生物集団」に注目しているなら「バイオーム」、「生物と非生物、およびそれらが関わりあうシステム」に注目しているなら「生態系」と書こう。
センター試験生物基礎に案の定『アカシア』が出ました。生物名は理論で導けません。語呂合わせで覚えましょう。
#生物基礎
#生態系
#バイオーム
関連動画
関連用語