定期テスト勉強をするかどうかの判断基準
どうも、フジです。
今回は「定期テストをどこまで頑張るべきか」というテーマ。高校生なら誰しも一度は考えることなはずのこのテーマ、私なりにその判断基準を整理しておきたいと思います。
「受験勉強に直結するかどうか」で定期テストを測る
多くの高校生は、定期テストを「受験勉強に直結する知識・価値を得られるか」という観点で評価します。定期テストの勉強をすることで、入試本番の点数に繋がるかどうか、という基準です。
確かにこの考え方は一理あります。
たとえば現代文やコミュニケーション英語などは、授業で扱った文章がそのまま出題され、事前に読み込んでいるのを前提に問題が作られており、まさに「どれだけ定期テスト専用の対策をしてきたか」を測るテストになっています。こんなものは、誰がどう考えても、入試に通じる要素は限りなく薄い。私も当時(そして今も)、そうしたテストの存在意義については正直まったく理解できませんでした。
あれ、でも不思議ですね、
現代文やコミュ英以外の教科、たとえば数学や理科、社会、英語表現などに関しては、定期テスト勉強を放棄している人が多いにもかかわらず、どれも受験勉強的に意味のある内容を扱っているような気がしませんか?
出題形式や制限時間に多少の難点がある場合も少なからずありますが(例えば初見の問題を時間内に解き切るのが不可能な量を出してくる数学のようなケースなど)、とはいえテスト勉強で扱うことになる内容そのものには確実に受験的意義があるはず。なのになぜ、これらの教科についても”定期テスト勉強をやらない”という判断を下す人が多いのでしょうか。
かく言う私自身が、高1の頃からずっと、世界史以外の教科については定期テスト勉強をかなりの程度で、ものによっては完全に放棄していた張本人ですので、自身の経験をもとに考えてみました。
「自分のペースを乱さないかどうか」というもうひとつの基準
振り返ってみると、私は定期テストの是非を「受験に直結する知識を扱うかどうか」だけで判断していたわけではなかったように思います。もうひとつ別の視点、ズバリ「自分のペースを乱さないかどうか」が、私の中で大きな判断材料になっていたような。
ここでいう「ペース」というのは、新しい単元を理解していくペースのことではありません。新しい内容を“理解”していく段階に関しては、私も基本的に学校のペースに合わせていました。定期テスト勉強をしていた世界史はもちろんのこと、地理も学校の授業進度に沿っていたし、高1の頃の英文法や古典文法も学校の流れに従っていました。
ここでいう「ペース」は「自分の中で定着させ、使えるレベルまで錬成していくタイミング」のことです。
私はこの“錬成のタイミング”を、自分でコントロールしたかったのでしょう。今は英単語と英文法に集中したい、今は古文単語と古典文法に集中したい、今は地理の暗記に集中したい。そういう「今自分が一番伸ばしたい領域」に集中的にエネルギーを注ぐ時間を、外部から規定された内容の勉強(つまり定期テスト勉強)に奪われ、ペースを乱されることが嫌だった。
だから、英語表現で扱っていたNextStageも、古文で扱っていた単語帳も、「今はまだ自分のタイミングではないな」と、学校の小テストや定期テストは徹底的に無視していたわけです。暗記教科である地理でさえも同じです。
私は「学校の定期テストのタイミングを利用して全教科科目を同時に少しずつレベルアップさせる」やり方ではなく、「その時点で最も意欲が高い教科に全力を注ぎ、一気にその分野を伸ばす」方針の方が性に合っていた、これは紛れもない事実です。もちろん、受験に必要な知識やスキルを長期的にもれなく回収できるよう、その全貌をある程度把握した上でですが、いつどこに力を入れるかはあくまで自分の判断で決めたいと思っていた。定期テストの存在は、この“自分で選んだ集中のリズム”を壊します。だから私は、テスト週間になるたびに、自分のペースが乱されるとこにこの上ない嫌悪感を抱き、世界史以外の教科に“NO”を突きつけたのです。
唯一、定期テスト勉強をしっかり行っていた世界史は、定期テストのサイクルそのものが自分の学習設計と一致していた、ただそれだけ。もし学習の優先順位が異なっていたら、世界史でさえも定期テスト勉強は不要と判断していたかもしれません。定期テストが自分のペースに合致するか、それとも妨げになるか。結局のところ、そこが一番の分かれ目なんです。
「ペースを乱さない」という視点が、長期的な効率を左右する
この「自分のペースを乱さないかどうか」という基準は、想像以上に重要です。
もちろん、受験に必要な知識を全体として漏れなく網羅することは大前提です。そのうえで、自分の中で高いモチベーションがある分野に集中的に力を注ぎ一気に伸ばしていく、そういうスタイルのほうが性に合う人は、決して少なくないと思います。人によっては「まんべんなく同時進行」が得意なタイプもいますが、私のように「一点集中で一気にレベルを上げるほうが効果が出る」タイプも確実に存在します。
受験勉強においては、「どの勉強が有益か」を判断するだけでなく、「何がどう自分のリズムに影響するか」にも敏感であるべきです。短期的な成果よりも、長期的に継続できるリズムを維持することのほうが、最終的な伸びに繋がるでしょう。自分のペースを守りながら、必要な部分だけを取り込み、長期的にプラスになるような取捨選択を意識していけると、勉強全体の質がぐっと上がるはずです。
というわけで今回は以上。
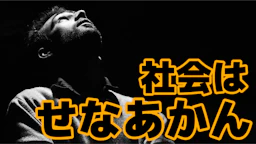
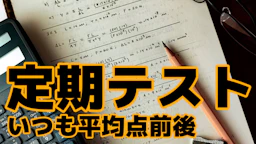
.png?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)

