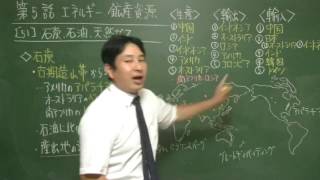火力発電
火力発電
化石燃料を燃焼することで発電する方法。
二酸化炭素の排出が多く、適切な対策をしないと大気汚染物質を大量に放出し、環境負荷が高い。
- 先進国では減少傾向
- 発展途上国では増加傾向
にある。
特徴
- 立地の制約が少ない
- 発電量の調整が容易
- 二酸化炭素・大気汚染物質を排出する
ことが大きな特徴。
立地の制約が少ない
燃料さえあればどこでもできるため、都市部にも立地できる。
また、燃料を輸入に頼る日本のような国では、燃料輸入の利便を図り臨海部に立地することが多い。
発電量の調整が容易
燃料の燃焼量を変えることで発電量を容易に調整できる。
このため、電力供給の調整役としての役割もある。
特に近年、天候による発電量の変動が大きい風力発電や太陽光発電の導入量が増加したため、火力発電による供給量の調整の重要度が増している。
環境負荷が大きい
- 温室効果ガスの排出
- 大気汚染物質の排出(特に石炭火力)
が大きな課題。
特に、石炭火力では大量の大気汚染物質が排出されてしまう。
発展途上国では、環境規制が緩い、または規制が守られないために排煙による大気汚染が深刻で、酸性雨などの環境問題も発生している。
使用する燃料
石炭、石油、天然ガスが利用される。
ただし、現在は石油は火力発電にはほとんど使われていない。
それぞれの燃料には、
- 石炭・・・最も一般的。大気汚染の原因となる
- 石油・・・ほとんど使われない。一部産油国で多く利用する国もある
- 天然ガス・・・クリーンエネルギーとして普及
という特徴がみられる。
石炭火力
最も安いため、途上国で多い。
経済成長に伴う電力需要の高まりに応え、途上国では石炭火力の新設が進んでいる。
難点は、大気汚染物質を大量に放出すること。
先進国の石炭火力発電所は煤煙の除去、脱硫などさまざまな対策を行っているが、途上国ではこれらの対策が追い付かず、大気汚染や酸性雨の大きな原因となっている。
石油火力
石油が安かった1960年代までは一般的だったが、現在では石油価格の高騰によって激減した。
環境負荷も高く、メリットが少ないことから現在石油火力が用いられているのは一部の産油国に留まっている。(日本では石油火力の新設は原則禁止)
天然ガス火力
CO₂排出量が少なく、大気汚染物質をほとんど排出しないことから、クリーンエネルギーとして近年注目を集めている。
欠点は燃料費が高いこと。このため発展途上国ではあまり普及していない。
関連動画