性比
性比
女性100人に対して男性が何人いるかという指標。
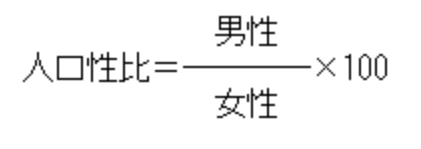
(総務省統計局HP)
- 100超→男性の方が多い
- 100未満→女性の方が多い
ということになる。
現在、世界全体では性比は100を超え、男性の方が多い。
日本の現況
日本全体の性比は95.4で、女性の方が多い。
これは、社会の高齢化が進んだことが要因(詳細は後述)。
また、
- 大都市では比較的性比が高い(男性が多い)
- 地方では性比が低い(女性が多い)
傾向がある。これの主な要因も高齢化の度合いの違いと考えられる。
傾向
100超(男性の方が多い)
- 都市部
- 工業都市
- 中国
- 子供が多く、高齢者が少ない地域(富士山型人口ピラミッドの地域)
は、性比が100を超える(男性の方が多い)ことが多い。
都市部
地方から男性が働きに出ることが多いため、田舎に比べて都市部では男性が多くなる傾向がある。
工業都市
鉱工業(特に重工業)、建設業が盛んな地域は、男性が多くなる傾向がある。
重化学工業が盛んな神奈川県川崎市では、2015年の性比は103.1で、現在よりも製造業が盛んだった1990年代には110を超えていた。
また、建設業が盛んな中東の産油国(ドバイなど)も、男性が多い。
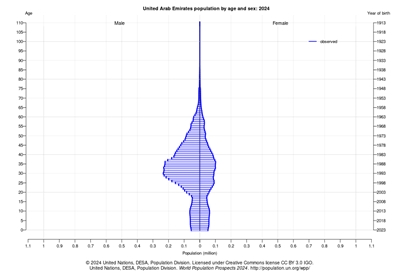 (UAEの人口ピラミッド、UN Population Division)
(UAEの人口ピラミッド、UN Population Division)
中国
中国は特殊な国で、女子の生み控えが起こっていることから、性比が異常に高い。
富士山型人口ピラミッド
自然な状態でも、生まれてくる子供は男子の方がわずかに多く、年齢が上がるにつれて徐々に男女同数に近づいていく。
また、女性の方が平均寿命が長く、高齢者になると女性の方が多くなる(男性が早死にするため)。
したがって、子どもだけみると男子の方が多く、高齢者だけみると女性の方が多い。
そのため、年少人口の割合が高く、老年人口の割合が低い富士山型ピラミッドの国では、男性の方が多くなる傾向がある。
100未満(女性の方が多い)
- 高齢化が進んだ地域
- 田舎
では、性比が100を下回りやすい(女性の方が多くなりやすい)。
高齢化が進んだ地域
先ほど説明したように、平均寿命は女性の方が長い。
つまり、男性は早死にし、女性は長生きする傾向がある。
そのため、年齢が上がれば上がるほど、女性の割合が高くなっていく。
大分県の人口ピラミッドをみると、後期高齢者では、女性が圧倒的に多いことがわかる。
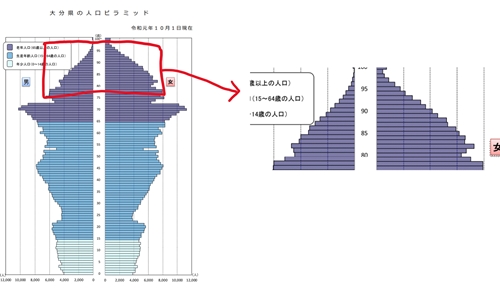 (大分県HPをもとに筆者加工)
(大分県HPをもとに筆者加工)
田舎
若い男性が都会へ働きに出る場合が多く、男性が減りやすいため性比が低くなる(=女性が多くなる)傾向がある。
関連動画








