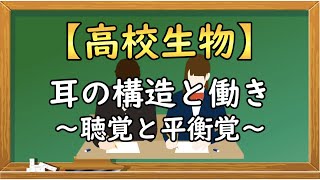【耳②】耳殻・耳小骨・耳管 高校生物
概要
動画投稿日|2021年3月12日
動画の長さ|3:02
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
耳について講義します。
耳の講義③はこちら
https://youtu.be/ZXK74VqOGSo
語呂「自称付き合ってるチューしよう(耳小骨、ツチ、キヌタ、アブミ、中耳。ツチとキヌタとアブミの初めの一文字でツキア、これを付き合ってと読む)」意味ない語呂ですね。すみません。
問題:耳小骨を3つ答えよ。
答え:ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨
問題:耳殻・外耳道が含まれる領域は( )耳とよばれる。
答え:外
●耳小骨ではてこの原理が使われている。
● 鼓膜は外耳道の奥に存在する半透明の薄い膜で、8×6mmの楕円形をしている。鼓膜の内側は中耳である。
●卵円窓は、鼓膜より20倍も激しく振動する。
●うずまき細管の内部のリンパ液を内リンパといい、他のふつうの細胞外液とは異なり、カリウム濃度が細胞外液にしては異常に高い。カリウム濃度がナトリウム濃度より160倍くらい高い。
外リンパをはじめ、ナトリウム濃度が高いほとんどの細胞外液と逆になっている。
●耳管(じかん):ユースタキー管(エウスタキオ管)とも呼ばれる。鼓室内に外気を流通させ、鼓室内の気圧を外気圧に一致させる。
*耳管は鼓室と咽頭をつないでいるが、通常ほとんど閉じている。エレベーターや飛行機で、急激に高い所に昇ると、音が聞こえにくくなる。これは、鼓室と外気の気圧の差によって鼓膜がゆがむからである。ごくんとつばを飲み込むと、耳管が開き、鼓室内の気圧が外気圧と一致し、鼓膜が正しい位置に戻る(気圧変化のために音が聞こえにくくなった時に、つばを飲み込むと治るのはこのためである)。
●耳管が閉じているのには理由がある。耳管を通って細菌が咽頭から鼓室に侵入すると、鼓室、中耳で炎症が起こってしまう。つまり、中耳炎が生じてしまう。
#生理学
#高校生物
#耳
関連動画
関連用語