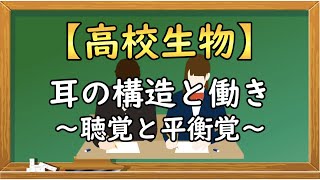【耳①】聴覚に関わる構造など 高校生物
概要
動画投稿日|2021年3月12日
動画の長さ|3:27
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
耳の、主に聴覚に関わる構造について講義します。
耳の講義②はこちら
https://youtu.be/uQKb9BVUhxM
*本講義では耳にある「聴覚に関係する構造」のみを扱っている。耳にある半規管(体の回転を感知)や前庭(体の傾きを感知)は板書していない(半規管や前庭は平衡覚をつかさどっている)。
これらの構造については耳④の講義で扱う。
問題:鼓膜は( ① )耳と( ② )耳を仕切る。空欄を埋めよ。
答え:①外 ②中
●外耳(がいじ):耳殻(じかく)と外耳道(がいじどう)がある。
*ヒトの外耳で最もわかりやすい部位は耳殻(じかく。耳介[じかい]ともいう)である。耳殻は、色々な方向からくる音を集める役割(集音機能)を持つ。
*鼓膜(こまく)は外耳と中耳の境界にある。鼓膜を外耳に含めることもあるし、中耳に含めることもある。
●中耳(ちゅうじ):鼓室(こしつ。中に耳小骨[じしょうこつ]がある)がある。3つの耳小骨には、鼓膜に近い方から、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨と名前が付いている。
●内耳(ないじ):耳の最内部。うずまき管、半規管(はんきかん)、前庭(ぜんてい)がある(聴覚および平衡覚の受容器がある)。
うずまき細管の中には内リンパが入っており、内リンパはナトリウムイオンが多くカリウムイオンが少ない。これは細胞内液とよく似た組成である。
●耳小骨は鼓膜の振動を内耳へ伝える3つの骨で、人体中最小の独立骨である。鼓膜の内側は空気の入った空間となっており鼓室と呼ばれる。ツチ・キヌタ関節、アブミ・キヌタ関節があって鼓膜の振動は1.3倍のテコ比で拡大され、アブミ骨のピストン運動となり内耳へ伝えられる。アブミ骨底は卵円窓という孔にはまっている。鼓膜の面積の方がアブミ骨底の面積より大きく、鼓膜が受けた音のエネルギーは約17倍になって内耳へ伝わる。
●耳小骨は鼓膜の振動を内耳へ伝える3つの骨で、人体中最小の独立骨である。鼓膜の内側は空気の入った空間となっており鼓室と呼ばれる。ツチ・キヌタ関節、アブミ・キヌタ関節があって鼓膜の振動は1.3倍のテコ比で拡大され、アブミ骨のピストン運動となり内耳へ伝えられる。アブミ骨底は卵円窓という孔にはまっている。鼓膜の面積の方がアブミ骨底の面積より大きく、鼓膜が受けた音のエネルギーは約17倍になって内耳へ伝わる。
#聴覚
#高校生物
#耳
関連動画
関連用語