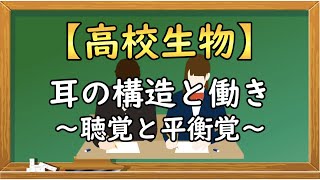【耳③】うずまき管・基底膜・コルチ器 高校生物
概要
動画投稿日|2021年3月12日
動画の長さ|7:50
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
耳について講義します。
語呂「硬い卵は高い(硬いところ、卵円窓に近いところの基底膜は高い音によく共鳴する)」
noteには簡単な図があります。
https://note.com/yaguchihappy/n/n4e5dd145afbc
耳④の講義はこちら
https://youtu.be/iFHgTnFW8zE
●音波の伝わり方について
・耳小骨(ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨)は(覚えなくてよいが、てこの原理によって)鼓膜の振動を増幅して内耳に伝える。
・まず、アブミ骨が卵円窓(らんえんそう)を押し込む。
・圧力波は前庭階を伝わり、基底膜を下方に押す。
・波はうずまき管の頂部まで達し、折り返す。そして圧力波は鼓室階を伝わる。
・基底膜の特定の場所がよく振動する(その上にあるコルチ器を振動させる→興奮の発生)。
・薄膜の正円窓(せいえんそう)が圧力波の最終的な到達地点である。
・(知らなくてよいが、正円窓の膜は、アブミ骨の動きによって形作られる圧力波とは逆位相で前後に振動する。それにより)正円窓で音は消失する。これは、次に来る音波のための装置のリセットに相当する。
・このように、音波はうずまき細管へ直接入らないのにもかかわらず(ウォーターベッドを強く押し下げた時の反応のように)、うずまき細管全体が振動する。コルチ器が感受するのは、まさにこの振動である。
*卵円窓と正円窓が紛らわしいかもしれない。「はじめは卵」と覚えておこう。
*入試では上の説明のように書かれることが多いが、現実には、波は、基底膜の最大振幅の位置でほぼ消失していると考えられている(完全に消失するとは考えにくいので、上の解釈は誤りではない。ただし、前庭階→鼓室階→基底膜のように、順番に移動していくわけではない)。
波のエネルギーは、基底膜の大きな振動に使われると考えられている。
入試問題の中には、振動が伝わる順序を①前庭階②鼓室階③基底膜と説明しているものもある。非現実的な解釈だが、一応高校生は、そのような解釈もあると知っておこう。大学に入ったら生理学の教科書で自分で学べばよい。
●うずまき管の中で基底膜が振動する場所は、音の高さによって異なり、低い音ではうずまき管の頂上部に近い部位が振動し、高い音では逆にうずまき管の底部に近い部位が振動する。このように音の高さによりうずまき管内の異なる場所の聴細胞が興奮するため、ヒトは音の高低を識別できる。
*基底膜は、うずまき管の頂部で「幅が広く・柔軟性がある」。そして、基部で「幅がせまく・かたい」。
●エネルギー保存則を見出したことで有名な生理学者・物理学者のヘルムホルツは、基底膜が、「ピアノと逆のはたらきをしてる」ことに気付いた。ピアノは、多数の振動する弦によって生じた音を組み合わせることで複雑な音を作り出す。うずまき管は、基底膜上で複雑な音を(波長ごとに)分解する。
●聴細胞(有毛細胞)の先端は、ゼラチン質のおおい膜の中に埋め込まれており、その様子は、さながら毛布が細胞を覆うようである。基底膜が振動すると、聴細胞の感覚毛が屈曲する→興奮が生じる。
*前庭階を進行する波は、うずまき細管の内リンパに圧波を発生させる。内リンパの圧波が基底膜を振動させると、聴細胞の感覚毛がおおい膜に押しつけられる(興奮が発生する)。
●動画中で、「正円窓が波を逃がす」と言っているが、実際は、正円窓の膜は、アブミ骨の動きによって形作られる圧力波とは逆位相で前後に振動すると考えられている。これにより正円窓で音は消失する。これは、次に来る音波のための装置のリセットに相当する。
●うずまき管は、幅広い高低音を聞き分けるために、あのうずまき形になったと言われています。
●基底膜は特殊化した細胞外構造(細胞外マトリックスという)であり、極めて薄いのに強く、柔軟性がある。カドヘリンと同様、多細胞動物すべてに共通の特徴であり、動物進化のごく初期に出現したと考えられている。
●音波の周波数と同じ共鳴周波数をもつ基底膜の部位に達すると、基底膜が、大きく振動する。このとき波のエネルギーを消費する。この結果、波は殆どがこの部位で消失する。これより先の基底膜へ進行することはない。我々が歳をとるほど高音(モスキート音)が聞こえなくなるのは、次のような理由によると考えられる。基底膜の前半は、ほとんどの波が通過する。後半になるほど、そこまで進行する波が少なくなる。つまり、前半のほうがより波が通る回数が多くなるので、聴細胞が障害を受ける頻度も上がる(あくまで説です。難聴の原因は一つではありません)。
●コルチ器は基底膜上の聴覚を感受する装置である。覚えなくて良いが、コルチ器には、有毛細胞(聴細胞)のほか、それを支えるなどする支持細胞もある。支持細胞には、柱細胞や、ベンゼン細胞など、さまざまな種類がある。
おおい膜はゼラチン上の塊で、コルチ器の有毛細胞にある不動毛に接している。
●視野だけでなく、聴野もある。人が聴き得る音の周波数の下限は20ヘルツ、上限は20000ヘルツとされている。この範囲を聴野という。また、加齢により、高い音が聞き取れなくなっていくことも知られている。
問題:卵円窓からうずまき管の前庭階のリンパ液に振動が伝わり、( ① )膜が振動する。すると、うずまき細管にある( ② )器にある聴細胞の感覚毛が( ③ )膜に押され、これによって聴細胞が興奮し、聴神経を通じて興奮が伝わる。振動は鼓室階のリンパ液を伝わり、正円窓を揺らすことで、消失する。語群から適切な語を選び、空欄を埋めよ。ただし、同じものを2回選んではならない。
語群[コルチ・おおい・基底膜]
答え:①基底 ②コルチ ③おおい
#高校生物
#うずまき管
#耳
関連動画
関連用語