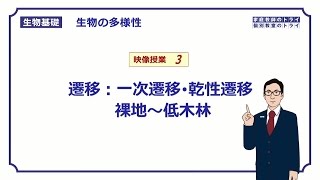遷移 高校生物基礎
概要
動画投稿日|2021年12月23日
動画の長さ|13:47
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
遷移について解説します。
光合成速度の測定についての動画→ https://youtu.be/jqxe19Jtux8
(光合成速度、呼吸速度を上記動画のように測定することで、陽樹か陰樹かを相対的に区別する)
陽樹の語呂「陽気でこなれたクリスマスは赤かしら。反対の黒服脱ぎ捨てるだけ」(陽樹=コナラ、クリ、アカマツ、シラカンバ、ハンノキ、クロマツ、クヌギ、ダケカンバ)
問題:陽樹林から混交林(こんこうりん)、そして極相の陰樹林へと遷移が進む背景について、以下の説明を完成させよ。
「陽樹林が成立すると、陽樹の成木に光が遮られ、( ① )は暗くなる。そのような暗い( ① )では、( ② )点が大きい陽樹の芽生えは生育できない。しかし( ② )の小さい陰樹の芽生えは生育できるので、陰樹が生育し、陽樹林から陰樹林へと遷移が進行する。」
答え:①林床②光補償
問題:極相内に存在するギャップとはどのようなものか。また、ギャップ更新とはどういう現象か。空欄に陽樹または陰樹の語を入れ、以下の説明を完成させよ。
「森林が倒木などにより部分的に破壊されてできる空間をギャップという。ギャップにおける樹木の入れ替わりをギャップ更新という。ギャップが小さい場合は林床に生育していた( ① )の幼木が生育してギャップを埋める。ギャップが大きい場合は林床まで強い光が届くようになり、( ② )の種子が発芽し、強い光の下で素早く成長しギャップを埋める。」
答え:①陰樹②陽樹
(倒木には、寿命、台風、落雷などの原因がある。極相林の陰樹林でも、ところどころ陽樹がモザイク状に存在するのは、上記のギャップ更新の結果である)
●陽生植物(耐陰性が乏しく、明るいところに生育する植物)の内、樹木のものを陽樹という。
*陽「性」ではなく陽「生」と書くので注意。
*耐陰性(たいいんせい):日陰に耐えられる性質のこと(植物が弱光条件のなかで生存・成長する能力)。
●陰生植物(耐陰性が強く、日陰で生育できる植物)のうち、樹木のものを陰樹という。
*陰「性」ではなく陰「生」と書くので注意。
●遷移の初期に侵入する植物をパイオニア植物(先駆植物)という。一般に、パイオニア植物は陽生植物で、乾燥に強く、種子が小さく、その種子は遠くに運ばれやすい。
*遷移の過程では、常に新しい種が別の場所から侵入している。条件が許せば、種は定着する。他種との競争に負けて消滅する場合もある。
●植生の時間的な変化を遷移という。遷移は一次遷移と二次遷移に分けられる。
①一次遷移・・・噴火後など、土壌が全くない状態から始まる遷移。
②二次遷移・・・山火事跡など、土壌がある状態から始まる遷移。土壌中に、埋土種子(まいどしゅし)や植物の地下部(根など)が残っているので一次遷移より短時間で極相となる。(重要)
●陸上から始まる一次遷移を乾性遷移(かんせいせんい)、対して、湖沼(こしょう)から始まる遷移を湿性遷移(しっせいせんい)という。
*乾生遷移や湿生遷移とも書くが、教科書や資料集にあわせて、大学入試では乾性遷移・湿性遷移と書くこと。
●乾性遷移の流れ
①裸地(土壌なし。)
→<地衣類(ちいるい)やコケ類が侵入>
*地衣類は、菌類と藻類(もしくはシアノバクテリア)の共生体である(藻類やシアノバクテリアが、菌体でサンドイッチされているような構造になっている)。地衣類が生育するには、わずかな水と栄養塩類だけがあればよい(岩・樹木の幹・民家の壁など、非常に過酷な環境でも生育できる。)。菌類は藻類やシアノバクテリアに良質な環境を提供し(光合成を行うパートナーを保護し、水分を保持する)、藻類やシアノバクテリアは菌類に光合成産物を提供する。一方、コケ植物は、陸上植物のひとつである(コケ植物・シダ植物・種子植物をあわせて陸上植物という)。
→②荒原(植物がまばらに生える。被度[植物の地上部が地表を覆う割合]は非常に小さい。)
→③草原(エノコログサ・メヒシバ・イタドリ・ススキなどが生育する。)
*エノコログサは日常会話の中では「ねこじゃらし」とも呼ばれるが、テストでは「エノコログサ」と書くように。
*必ずしもコケ植物、地衣類が先に侵入してから、草本が侵入すると決まっているわけではない。いきなり草本が侵入する場合もある)。
*一般に、1年で枯れる一年生草本(いちねんせいそうほん)がまず侵入し、その後、数年生き続ける多年生草本(たねんせいそうほん)が侵入してくる。
*1年以内に発芽・成長・開花・結実を迎え、体は枯死することを一年生といい、一年生の植物を一年生植物(または一年生草本)という。
一方、2年以上個体が生存する性質を多年生といい、多年生の植物を多年生植物と呼ぶ。多年生植物には、かなり多くの草本植物と、すべての木本植物が含まれる。多年生の草本は多年生草本と呼ばれる。
→④低木林(オオバヤシャブシ・ミヤマハンノキなどが生育する。)
*オオバヤシャブシやミヤマハンノキの根には『窒素固定細菌』が共生しており、空気中の窒素をアンモニウムイオンに変化させ、植物に与えている(植物はアンモニウムイオンを使ってアミノ酸を合成できる)。そのため、オオバヤシャブシやミヤマハンノキは窒素などの栄養塩類が乏しい場所でも生育することができる。
→⑤陽樹林(アカマツ・クロマツ・コナラ・クヌギなどが生育する。)
→⑥混交林(こんこうりん。林床が暗くなる→光補償点の大きい陽樹の芽生えは生育できないが、光補償点の小さい陰樹の芽生えは成長できる。)
*混交林は、高木層、あるいは主要林冠層が、2種以上の樹種で構成された森林である。混合林とも呼ばれる。
→⑦陰樹林(スダジイ・アラカシ・クスノキ・タブノキなどが生育。極相となる。)
noteには簡単なイメージ図があります。
https://note.com/yaguchihappy/n/nce491ab1d847
●遷移が進み、全体として安定した植生ができあがった状態を極相(クライマックス)という。
●年降水量や年平均気温によっては、草原や荒原が極相になる。日本では、(海岸や標高の高い場所などを除いて)極相は森林となる。
●代表的な陰樹は、バイオームのところで覚える。各バイオームの代表的な樹種はほとんど陰樹である。極相が陰樹林だからである。
●草本(そうほん)はいわゆる草のこと。対して、木になる植物を木本(もくほん)という。
●雑草として親しまれているメヒシバやエノコログサ(猫じゃらしと呼ばれている)などもパイオニア植物である。動画中紹介したオオバヤシャブシも、木本であるが、パイオニア植物である(窒素固定細菌と共生することで、栄養が乏しい土壌中でも生育できる)。
●陰樹林まで遷移が進み、安定した状態(クライマックス)となっても、台風などの倒木によりギャップ(空間)ができることがある。小さなギャップは陰樹により埋められるが、大きなギャップは、埋土種子として土壌中に残っていた陽樹が発芽し、生育してギャップを埋める。(発展だが、陽樹の種子はそのように光によって発芽制御を受けるものがある。光発芽種子という)。このようにギャップにおいて樹種が入れ替わることをギャップ更新と言う。
*一般に、森林における樹木(特に極相林の林冠を構成している樹木を指すことが多い)の世代交代のことを「更新(regeneration)」といい、ギャップの形成に伴い樹木が更新する現象を「ギャップ更新(gap regeneration)」という。ギャップが出現すると、その下での光環境が急速に改善される。その結果、次世代の個体が急速に成長する。そして競争の結果選ばれた個体がギャップを埋める。
●林冠とは、正確には、多数の樹冠(高木の葉が茂っているところ)が接している部分を指す。つまり、森林において、上を見上げた時見える状態を指す。
●同じ陰樹でも、日陰に付く葉(陰葉)と日がよく当たる所に付く葉(陽葉)では形態が違う。陰葉は薄く広く、葉の内部に柵状組織が発達せず(覚えなくていいが1層程度)、したがって(最大光合成速度と)呼吸速度が小さく、したがって光補償点も小さい。
陽葉は逆に、葉が小さく厚く(柵状組織は3層程度)、光補償点は大きい。陰樹も大きくなると陽葉をつけるので注意。
●「コケや地衣類が進入して荒原になる」と説明しているが、厳密には、荒原は、(環境要因のうちどれか1つが劣悪であるために)植物がまばらに生えるだけになっている状態をざっくり指してそう呼ぶことが多い。
●実際は、窒素固定細菌のもつニトロゲナーゼはN2から2分子のNH3への反応を触媒するが、NH3は水中ではNH4+と平衡状態になっている。高校生はNH3とNH4+の書き分けはそれほど気にする必要はない。問題文にあわせる。
●地衣類について、菌とシアノバクテリアが共生している場合、シアノバクテリアは窒素固定産物も渡す場合がある。
●一次遷移を陸上で起こる乾性遷移、湖沼(こしょう)で起こる湿性遷移に分けることもある。ただし、一次遷移を陸上で起こるものに限定することもある。
●湿性遷移は、①貧栄養湖②冨栄養湖③湿原④草原(以後乾性遷移と同じ)のように進む。
●現在、放置された山が、暗い陰樹林に遷移している(昔は、人が、少しずつ木々を伐採することで、陰樹林にまで遷移が進まなくなっていた)。陰樹林になると、競争に強い種子か生き残れないので、多様性が逆に減ってくる。これが社会問題になっている。ちなみに、人が定期的に少し伐採するなど、中くらいの規模のかく乱によって、多様性が上昇するという説を、中規模かく乱説という。
●一年生草本を「種子の形で年を越す」と書いているが、もちろん、次の年に発芽できる保証はない。正確には、「1年以内に発芽・成長・結実を迎え、体は枯死する」草本とするべきである。
●どうして大島などの小さな島においてコケや地衣類より先にイタドリなどの草本が進入するのかについてはわかっていない。海が近いことが関係しているともいわれる。
Q 極相で安定ってよく言うけど、安定ってどういう風に安定するの?
A.…決まっていない。以下に述べる複雑な事情がある。
そもそも極相は、どこか最終地点を指しているわけではない。
極相群落は遷移の途中相に比べて相対的に安定しているということしか言えない。
それまでの変化が一定方向の傾向のものであるのに反して,極相での変化は、進んだり戻ったり、ある点を中心とした振動であるといえる。
一般に、極相は、生産力,生物量,栄養塩類の蓄積, 種の多様性, 土壌の発達,などが最高レベルに達しているかどうかによって決めることが多い。
しかし、これらの変化がそれぞれ最高レベルに達する時間にずれがある。たとえば、林床の種の多様性は、遷移の進行によって増加するが、極相に近付くと逆に低下する。極相林では林床が暗くなり、競争に耐えることのできる競争に強い種しか生き残ることができないからである。
極相で安定する、とよく言うが、ここで言う安定は、以下のような、様々なバランスが保たれていることをさす。
・繁殖による新個体の加入と,死亡による個体の損失のバランス。
・光合成によって獲得された太陽エネルギーと,呼吸によって開放されたエネルギーのバランス。
・根を通しての土壌からの無機栄養塩の吸収と, 落葉などによる無機栄養塩の土壌への供給のバランス。
*動画中で「進入」という語を使っていますが、「侵入」という語を用いた方がより適切でした(侵入という語には、ある場所から移動してきた種が定着していく、というイメージが含まれるためです)。申し訳ありませんでした。
0:00 遷移の基本
2:26 遷移の詳細
11:03 発展(生物好き専用)
#生物基礎
#生態系
#遷移
関連動画
関連用語