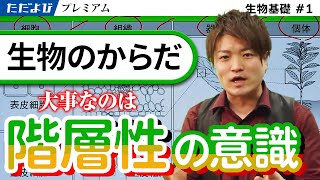植物の体(維管束植物の組織系) 高校生物
概要
動画投稿日|2021年9月25日
動画の長さ|7:52
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
植物の体のつくり(組織系など)について講義します。
語呂「ひょー!いかん!基本はそう死刑(表皮系、維管束系、基本組織系、組織系)」意味ない語呂ですね。すみません。
問題:植物の組織系を3つ答えよ。
答え:表皮系、維管束系、基本組織系
問題:動物の組織を4つ答えよ。
答え:上皮組織、神経組織、筋組織、結合組織
●組織系(そしきけい):ふつう、植物にしか使わない用語である。関連のあるいくつかの組織の集団。その分類方式は統一されていないが、表皮系(ひょうひけい)、維管束系(いかんそくけい)、基本組織系(きほんそしきけい)の3系に分けるの一般的である。
(1)表皮系
表皮系を構成する組織は、単に表皮と呼ぶことが多い。表皮系は、表皮細胞、孔辺細胞などから構成される。表皮細胞はクチクラで覆われている。クチクラには、水の損失を防いだり、病原体から植物体を保護したりする役割がある。表皮細胞には葉緑体がない(虫に食われ、無駄になることが多いためか)が、孔辺細胞には葉緑体がある(気孔開閉に関わる生命現象を活発に行うためか)。
(2)維管束系
木部と師部からなる。木部にある道管は主に水や無機塩類が移動する通路、師部にある師管は主に葉の同化物質が移動する通路である。
*木部には、道管のほかに、木部柔組織などが含まれる(知らなくてよいが、木部柔組織はデンプンや樹脂を多く含んでおり、貯蔵の枠割をもつと言われている)。師部には師管のほかに伴細胞などが含まれる。伴細胞は、被子植物において、師管に接着して生ずる柔細胞である。伴細胞は、タンパク質などの栄養を作り、原形質連絡(植物の細胞はお互いに原形質連絡[細胞膜で包まれた細長い細胞質の糸]でつながり合っている)を通じて師管要素に運ぶと考えられているが、よくわかっていない。伴細胞はふつう、「はんさいぼう」と読むが、「ばんさいぼう」と読むこともある。テストでは漢字で書こう。
*維管束植物は仮道管と道管をもつ。どちらも水を通している(どちらも、機能的に成熟した段階で死ぬ。植物は死んだ細胞を水の通路として利用しているのである)。仮道管はほとんどすべての維管束植物(シダ植物・裸子植物・被子植物)が持つ細胞である(被子植物では仮道管は道管の補助として使われている。)。道管は基本的に被子植物のみに存在する。
*仮道管は長細い細胞で、水は壁孔(へきこう)という孔を通って細胞から細胞へ移動する。道管は、道管要素という、細胞壁だけからなる中が中空の死細胞が何個も連結してできたものである。連結部の細胞壁には、穿孔(せんこう)と呼ばれる孔が存在し、そこを水が通れるようになっている。
*コケ植物にも通水細胞が存在することが明らかになっている。この細胞の獲得が植物の陸上化に大きな影響を与えたことは間違いないだろう(なお、被子植物の通水細胞は道管の細胞[筒状。上下の細胞と繋がって、管状組織を形成する]であり、裸子植物とシダ植物の通水細胞は仮道管[細胞間は連結せず、隣接する細胞間に壁孔とよばれる孔がある。この孔を通して水を輸送する]と呼ばれる組織を形成する)。
*師管は被子植物に見られる、糖を輸送するための組織である(覚えなくてよいが、シダ植物や裸子植物は、師細胞という細胞を使って糖を輸送している)。師部の細胞は、木部の細胞と異なり、生きた細胞からなる。師管は師部要素という細胞がつながってできている。師部要素と師部要素の間には師板(しばん)が存在する。師板には孔(師孔という。師孔は、原形質連絡、あるいは原形質連絡の集合体と考えられている)が空いており、そこを物質が通る。師部要素は、伴細胞と原形質連絡で連結している(伴細胞は通道には関与しない)。伴細胞の役割についてはわかっていないことが多いが、伴細胞の核やリボソームは、伴細胞自身だけでなく、隣の師部要素のためにも機能していると考えられている。。
*「師管」という言葉は、孔の空いた師板が「篩(ふるい)」に似ていることに由来する(高校では「師管」と書くが、一般には「篩管」と書く)。
(3)基本組織系
基本組織系は、維管束植物について、表皮系と維管束系を除いたすべての部分を指す。柔組織、厚壁組織、厚角組織などから成る(厚壁組織や厚角組織の細胞の細胞壁は厚い)。
*厚壁組織は、梨のざらざらした舌触りの原因になっている。
*厚角組織や厚壁組織などの集合を機械組織という(植物体を「機械」的に支持する)。
●組織系とは、一般に、関連のあるいくつかの組織の集団である(維管束植物について使うのが普通である)。その分類方式は統一されていないが、表皮系、維管束系および基本組織系の3系に分けるものが一般的である。
●基本組織系はJ.von Sachs(ザックス。光合成でデンプンができることを発見した植物学者)が命名した。維管束植物について、表皮系と維管束系を除いたすべての部分を指す。一般に、基本組織系は維管束の並んだ環の内側の髄と外側の皮層に分けられる。
●木部には、木部柔組織などが含まれる。木部柔組織はデンプンや樹脂を多く含んでおり、貯蔵の枠割をもつと言われている。
●内皮は、カスパリ―線を持つ特殊な細胞層であり、根の維管束を取り囲んでいる。
●たまに、推理ドラマで、木が大きくなるにつれて枝が上に移動していく、という話がある。しかし、木は全体が伸びるわけではない。茎の先端しか伸びない(茎頂分裂組織が分裂を行う)。
●カスパリ―線は、根の領域にあり、内皮細胞の間に、帯状に存在する。いったん維管束内に入った溶質や水は、カスパリ―線があるため、外に出ることはできない。それにより、根圧が生じる。
●皮層とは、主に、根では表皮と内皮の間、茎では表皮と維管束の間にある部分を指す。植物の基本組織系の主要素である。
●内皮を皮層に含めることもある。
●表皮系を構成する組織は、単に表皮と呼ぶことが多い。表皮細胞はクチクラ(動物の同様の働きをする構造を呼ぶ場合はキューティクルということが多い)で覆われている。クチクラには、水の損失を防いだり、病原体から植物体を保護したりする役割がある。
●動物の結合組織は、中胚葉由来の組織である。コラーゲンなどの細胞間物質に富む。たとえば血液は結合組織だが、細胞成分は血球であり、細胞間物質にあたるのは血しょうである。
●植物にも器官はある。葉や茎、根(栄養器官)と、花(生殖器官)である。
noteには簡単な図がある。
・道管、師管など。
https://note.com/yaguchihappy/n/n84557d4c40bb
・カスパリー線など。
https://note.com/yaguchihappy/n/n99868b1b21fe
#高校生物
#植物
#組織系
関連動画
関連用語