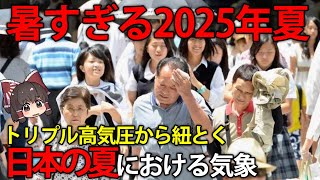農家の分類
農家の分類
農家は、
- 販売農家
- 自給的農家
に分けられ、販売農家はさらに
- 主業農家
- 準主業農家
- 副業的農家
の3種類に分けられます。
農林水産省の定義はこうです。

わかりにくいですね。簡単に言うと、
- 主業農家→農業で生活してる若い農家
- 準主業農家→農業を副業としてやってる若い農家
- 副業的農家→おじいちゃんおばあちゃんがやってる農家
という趣旨です。
広い土地を持ち、農作物を売るためにやっている農家は販売農家、 狭い土地で自分の家で食べるために農業をしている農家が自給的農家です。
ちなみに割合としてはこんな感じです。

補足 ~なぜ、分類が変更されたのか~
さっき紹介した分類は最近作られたもので、少し前までは別の分類方法が用いられていました。それが、
- 専業農家…世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家
- 第一種兼業農家…農業所得を主とする兼業農家
- 第二種兼業農家…農業所得を従とする兼業農家
という分類です。
昔はこれでよかったんです。昔は。 しかし、最近になるとこの分類は役に立たなくなってしまいました。なぜでしょう?
このように、原因を考えさせる問題が難関大学の論述試験で聞かれます。知ってれば瞬殺なんですけどね。みなさんもちょっと考えてみましょう。
分からなかったら、もとのもとまで遡って考えることが大切です。
まず、農林水産省(当時は農林省)はなぜ農家を分類したのかを考えます。 それは、農家の中でどれくらいの人が農業を主な収入源にしているか、ということを知りたかったからです。みんながどのくらい農業で稼いでいて、みんな農業でちゃんと食べていけているのかどうかを知ることで、農業政策を決定できますよね。
では、その「農家」というのはどんな農家かというと、ふつうの会社員と同じように、若い働き盛りの人が職業として農業を営むことを想定しています。決して年金暮らしのおじいちゃんおばあちゃんが暇つぶしで営んでいる農家を想定したものではありません。
ところが、高度成長期以降、農村から都市への人口流出が進んだ影響で、農村から若者がいなくなってしまいました。じいちゃん、ばあちゃん、かあちゃんが農業をやる、いわゆる「三ちゃん農業」というやつです。
あれ、と思った方、鋭い。そう、父ちゃんが抜けていますね。父ちゃんは出稼ぎや近くの職場に働きに出て、農業以外の収入を得ているのです。
このような農家は次第に父ちゃんや都会に出ていった息子の収入を頼りに生活するようになり、農業収入はお小遣い程度、趣味に近いものになっていきました。
こうして日本には大量の第二種兼業農家が生まれ、ほとんどの農家が第二種兼業農家に分類されるようになった結果、分類にほとんど意味がなくなってしまったのです。
若い人で、副業として農業で200万円稼ぎ、一方で本業で300万円稼いでいる農家も、 年金暮らしのじいちゃんばあちゃんが農業で10万稼いでいる農家も、 両方とも第二種兼業農家に分類されてしまうのです。
こうして、分類が実体を反映しなくなり、分類変更がなされたということですね。
関連動画