古典的条件づけ・オペラント条件づけ 高校生物
概要
動画投稿日|2024年1月9日
動画の長さ|4:01
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
古典的条件づけとオペラント条件づけについて講義します。ここの分野は用語の定義が揺れている(高校教科書と動物行動学と心理学で少しずつ用語の定義のニュアンスが異なる)ので、ざっくりしたイメージをつかめればOKです。それで十分大学には合格できます。
● 動物の行動や反応を、ある刺激と結びつける手法・あるいはその過程を、条件づけと呼ぶ。条件づけには、古典的条件づけとオペラント条件づけがある。
● 生体がすでに生得的にもっている反射反応(たとえば唾液反射)に先行して、中立的な新しい刺激(たとえばベルの音)を反復して提示するとする。すると、その生得的な反射反応が、新しい刺激(ベルの音)だけによって誘発されるようになる。このような学習の型を、古典的条件づけという。
例)パブロフの実験・・・犬に肉片を与える時、その直前に特定の音を聞かせた(これを繰り返した)。やがて犬は、その音だけで唾液を分泌するようになった。
● パブロフの犬が獲得した「反射」のように、後天的に獲得される「反射」のことを「条件反射(じょうけんはんしゃ)」という(条件反射:生得的ではなく、一定の条件下で形成された反射)。条件反射は、自然環境においても数多く形成されている(たとえば、レモンの写真を見ると唾液が出てくる)。
*詳細*
肉片(無条件刺激)を犬に与えると、唾液反射が起きる(無条件反射[これは生得の反射である])。肉片を与える際に、ベル(中立刺激=本来唾液の分泌とは全く関係ない刺激)を鳴らすという一連の手続きを繰り返すと、ベルの音だけで唾液を分泌するようになる(条件反射)。ベルのように、条件づけの中で機能を獲得した中性刺激を条件刺激という。条件刺激と無条件刺激の対になった刺激による学習を、古典的条件づけという。
<Q.条件反射は何で学習なの?…経験によって行動が変化しているからである。実験前の犬は、ベルの音を聞いても唾液を分泌しない。繰り返し「ベルの音を聞くと同時に肉片を与えられる」という経験をした、からベルの音だけで唾液を分泌するようになった。>
● 「条件刺激によって喚起される反応」を「条件反応」と呼び、「条件刺激が条件反応を喚起する関係」を条件反射と呼ぶ。
● 「条件反射」の形成と同じ手続きで、「反射以外の行動」も変容する。例えば、ヒトデに、照明を消してから餌を与えるという操作を繰り返すと、ヒトデは、照明を消しただけで活発に活動するようになる。このように、習得される行動は「反射」に限定されないので、刺激の対呈示(2種の刺激を交互に提示すること)と、それによる行動の変容は「条件づけ」と呼ばれるようになった。その後、刺激の対呈示以外の方法でも条件づけが生じることが発見された(オペラント条件づけ)。よって、それ以前から知られている「条件刺激ー無条件刺激」対呈示による条件づけは、「古典的条件づけ」と呼ばれるようになった。
● 「古典的条件づけ」だけでは、ヒトや他の動物が行う「自発的な」行動を説明できない。
スキナーは、スキナー箱と呼ばれる実験装置を開発した。この装置では、動物がレバーを押すと、報酬として餌が出るようになっている。空腹にさせたラットを箱内に入れると、はじめラットは偶然レバーに触れ、餌を得る。これを何度も繰り返していると、やがて自発的にレバーを押すようになる(ラットは満腹になるまでレバーを押し続ける)。レバーを押すという行動と餌が結びついて、レバーを押す頻度が上がる。このように、ある『自発的』な行動(レバーを押す)の後に刺激(餌)が加わることで、その行動が生じる頻度が変化することをオペラント条件づけと言う
● オペラントはスキナーの造語である(操作[英語でオペレートoperate]を意味するオペランドに由来する)。
● 例えば、「幼児が偶然ある行動(例:勉強する)をしたときには親が賞賛し、勉強しないときは賞賛しないことを繰り返すと、その幼児の勉強をする頻度が増す」という行動原理がオペラント条件づけである。これは学習理論の考え方である。知らなくてよいが、操作(英語でoperate)しようとする自発的な行動(先ほどの例では勉強)のことをオペラント行動という(オペラント行動は『制御可能な』行動であり、反射とは区別される。当たり前だが、[パブロフの犬が唾液を分泌するように]幼児の体が何かの合図で勝手に勉強を始めるわけではない)。
● 古典的条件づけでは、行動や反応に「先行する」刺激による制御(ベルを鳴らし肉を与えるという操作は唾液分泌の「前」に行われる)が行われており、オペラント条件づけでは、行動や反応に「後続する」刺激による制御(餌による刺激はレバーを押すという行動の「後」に与えられる)が行われている。
● 動物行動学においては、古典的条件づけを刺激と刺激の連合学習、オペラント条件づけを反応と結果の連合学習とすることが一般的である。高校生は知らなくて良い。
● 何回も試行を繰り返して成功効率を高めていく学習を試行錯誤(しこうさくご)という(試行錯誤学習ともいう)。たとえば、ゴールに餌を置いた迷路を用いた実験などにおいて、初回のゴール達成までには長い時間を要するが、2回目以降ではゴール達成にかかる時間が減っていく。
● 学習による行動変化を数量化し、グラフにしたものを学習曲線という。学習曲線は、一般に、ある行動の頻度や速度などの指標をとり、この変化量を縦軸に、経験量(日数や試行数)を横軸にプロットして作成する。学習曲線には様々な形をとることが明らかになっている。
0:00 条件づけ
0:36 古典的条件づけ
2:17 オペラント条件づけ
#高校生物
#行動
#学習
関連動画

23:49
高校生物【生得的行動と習得的行動】オンラインで高校授業高校で学ぶ生物・生物基礎〜いつでもどこでもオンライン授業〜

15:49
【東京大学】2022年 第1問 Part2【生物】*「ただよび」理系チャンネル

18:53
【生物】動物の行動【第9講】「ただよび」理系チャンネル
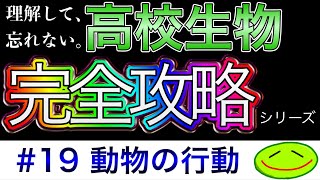
17:03
#19 動物の行動(生得的行動、かぎ刺激、固定動作パターン、定位、走性、太陽コンパス、生物時計、フェロモン、円形ダンス、8の字ダンス、慣れ、脱慣れ、鋭敏化、オペラント条件づけ)#大学受験 #高校生物【受験生物講師】チラコイド

3:49
【知能行動って何?】古典的条件づけ(パブロフの犬)・オペラント条件づけ・知能行動の覚え方・語呂合わせ 学習 動物の反応と行動 ゴロ生物大学入試ゴロ理科
関連用語