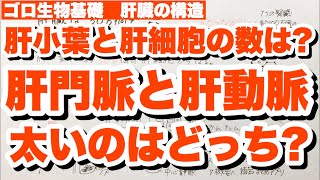肝臓 高校生物基礎
概要
動画投稿日|2021年7月14日
動画の長さ|6:22
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
肝臓について解説します。
語呂「観賞用の50万(肝小葉はひとつの肝臓に50万個程度ある)」
語呂にそのまま50万なんて数値を出してしまってはダメですね。すみません。
問題:肝門脈に流れるのは動脈血か、静脈血か。
答え:静脈血(消化管で酸素は手放している)」
問題:肝臓は何という単位が約五十万個集まっているのか。また、その単位の中心を通る血管を何というか。
答え:肝小葉 、中心静脈
●肝小葉は直径700μm、高さ約2mmの六角柱状の構造物である。ヒトを含む多くの動物では、小葉間の結合組織が少なく、小葉と小葉の境は不明瞭である。
*50万と言う数値は、大雑把な概算であり、本当はテストに出してはいけないはずですが、出ることがあります。
●血しょうのタンパク質は、ほぼすべて肝臓で作られる。そのうちの一つアルブミンは、血しょうの浸透圧上昇などに関わる(つまり、ただ血しょうにあるというだけで意味がある。浸透圧は水を引き込む勢い)。もし肝臓の機能が低下し、アルブミンが不足すると、血液の浸透圧が低下し、血液の外に水が流出する。ひどい場合、腹水を引き起こす場合もある。
●消化管から流れる血液には毒があるかもしれないし、多すぎるグルコースがあるかもしれない。だから、まず肝臓が関所として機能していると考えられる。
●肝臓は血液を貯蔵する。
●非常に大きな臓器で、成人男性で1.5kgということはたまに問われる。
●最も発熱量が多いのは骨格筋で、2番目に発熱量が多いのが肝臓である。
●動物のグリコーゲンは植物のデンプンと似ているが、グリコーゲンの方が枝分かれが多い。
●たくさんのグルコースをグリコーゲンの形にすることで、細胞内の浸透圧の上昇を防いでいる。もしすべてグルコースの形で貯蔵したとすると、すぐに細胞は吸水して破裂してしまうだろう。
●ATPは細胞外へ出れない。我々はグルコース等の形で栄養を細胞から細胞まで輸送している。
●胆汁は脂肪を乳化することにより、脂肪の分解を助ける。乳化は、大きな脂肪滴を小さな脂肪滴に分けることを言う。一つ一つの脂肪滴が小さくなると、その分表面積が増えるので、リパーゼがかなり速いスピードでトリグリセリドを分解することができるようになる。
●異常な高血糖が長く続くと、全身の多くの組織で血管の機能異常がおこり、構造が変化し、組織への血流供給が不十分となる。結果、そのまま対処せずにいると、心臓発作、脳卒中、腎臓病、網膜症と失明、手足の虚血などの原因となる。
●テストにはほぼでないが、肝臓は、驚異的な再生能力を持つ。また、沈黙の臓器と呼ばれ、病気の進行に気付きにくい(自覚症状が出にくい)ことがある。
●覚えなくて良いが、正確には、肝細胞は、肝内胆汁と呼ばれる液体を毛細胆管に分泌する。肝内胆汁が胆管を通過する間に、上皮細胞が重炭酸イオンなどを分泌し、最終的に十二指腸に分泌される胆汁が完成する。
●胆汁は胆汁酸と胆汁色素からなる。胆汁色素はヘモグロビンの分解産物からなるビリルビンからなる。これがやがて便の色になっていく(正確には、腸管内に分泌されたビリルビンは、腸内細菌の作用を受け、さらに還元されてウロビリノーゲンになる。糞便や尿の色は、ウロビリノーゲンが酸化されて生じるウロビリンである)。ビリルビンという用語はたまーに問われる。
●高校生は気にしなくて良いが、正確には、肝小葉付近の三つの管(それぞれ胆管、門脈、動脈)は、小葉間胆管、小葉間静脈(小葉間門脈ともよばれる)、小葉間動脈とよばれる。この3本は一緒にいることが多く、三つ組みなどと呼ばれている。
●肝動脈を流れる動脈血は本来、グリソン鞘という、小葉間胆管や肝動脈、門脈、リンパ管が通る結合組織などを栄養するものだが、それらを流れた後も、まだ多くの酸素を含んでおり、門脈に合流することで肝細胞に酸素を供給している。
●お酒と風邪薬の例はイメージ。正確には、シトクロムP450と呼ばれる酵素群が自身に結合した薬物を酸化している。薬物の組み合わせによっては、一つのP450に対する競合が起こり、それぞれの薬物の代謝が阻害され、薬物の血中濃度が上昇する危険がある(結果、副作用が生じる可能性があるのは、動画中で話した通りである)。
#生理学
#生物基礎
#肝臓
関連動画
関連用語