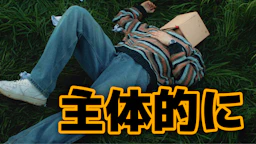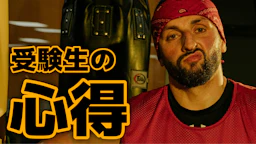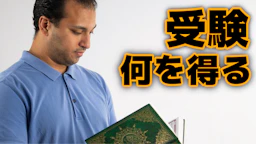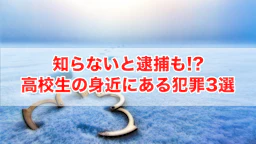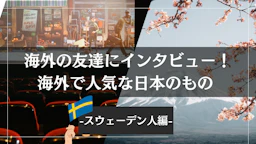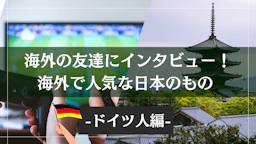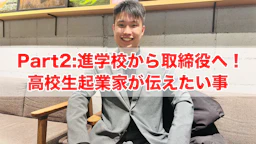いろんな高校の生徒会にインタビューする「突撃!生徒会室」シリーズ、今回は記念すべき第一弾ということで、日本一の生徒数を誇るN高等学校の生徒会長、大杉優宙さんにインタビューしています!詳しくは前回の記事を見てみてくださいね。
第2弾(今回)は、前回からの続きで、「大杉さんがN高生徒会長になるまで」「大杉さんが大事にしていること、自分自身の理想像」を中心にインタビューした内容の記事になります。
シリーズ一覧
- ①自分の熱中できることをしたいとN高へ!
- ②やるなら目指せる限界を!生徒会長の原動力とは
- ③学園生活を誇れるものに!生徒会長が描く世界

(N高生徒会長の大杉さんにインタビューしました!)
- では、大杉さんがN高で生徒会長になろうと思った経緯を聞かせてください!
中等部にいた頃の話に少し戻るんですけど、当時、私は投資部に入っていて、その時すでに、「活動する楽しみ」「自分の知らない新しい価値観とか意見に対面する楽しみ」には気づいていたんです。
ただ、N高に入学してからしばらくは慣れなくて、いろいろな不安も抱えていました。そんな中、夏休みに、様々な活動をしている先輩方と仲良くなる機会があって。そのとき関わった先輩方がキラキラしていたんですよね。
毎年4月に開催される「磁石祭」というN高・S高の文化祭があるんですけど、そんな先輩方の姿に背中を押されるような形で、実行委員と、N高の広報として記事や動画を作るN/S高新聞の実行委員に応募して、採用してもらいました。そこから活動をはじめていった感じです。
生徒会は入学した時から存在は知っていたけれど、もともと自分とは遠い存在に思っていて…。ただ、私が磁石祭の実行委員をしているときに、生徒会の人たちとも関わる機会があり、関わってみたら、遠い存在というよりも、同じ高校生なんだなという実感がわいてきました。そこで、「生徒会って面白いのかも」って考えが浮かんだんです。
ちょうどそのタイミングが高校2年生で、メンターさんとの面談の中で自分の将来の道についても考えていた時だったこともあり、高校生活最後のチャレンジとして、生徒会に応募してみようと思いました。
私が生徒会長になる前年までは、生徒会選挙での得票数が一番多い人が生徒会長になっていました。なので、私は生徒会長にはなれないだろうな、役員になれさえすれば嬉しいな~(笑) くらいの気持ちだったんですけど、今年から会長の選び方も変わったことで、私が任せてもらえることになりました。
- そういう経緯だったのですね。ちなみに、生徒会長の選び方はどのように変わったんですか?
今年は、生徒会役員に選ばれた20人の中から、夏休みに行われた3泊4日の合宿の中で、話し合って役割を決めていくという形でした。
「やるなら目指せる限界を!」ということで、私は会長に立候補しました。その合宿では、自分の強みをアピールして、最終的に生徒会役員の中でのそれぞれの役割を決める流れでした。私は、言いたいことをうまく言葉にできない子の言語化を助けたり、意見が話せずに流れてしまった子の話を後から引き出したりしていました。で、最後話し合って、会長を任せてもらった感じです。
生徒会役員には、会長や副会長の他にも役割があります。たとえば、SNSの発信力がある子や、ファシリテーション能力が高い子もいて、自分の強みが生かせるようにそれぞれ自己PRして決めていきました。
(N高では、「生徒会任命式」というものがあるそうです!)
- 合宿で決めるのはすごいですね!磁石祭の活動に飛びこんだのが最初のターニングポイントだったのだと思いますが、飛び込んでみるときに意識したことはありますか?
確かに一番最初の実行委員に入ったときは不安でした。でも振り返ってみると、そういう役割を経験している先輩と一緒に申し込むなど、何かしら勇気を与えてくださる方と一緒に行動するのが大事だったのかなと思います。
他にも「自分の限界を知りたい」という意識はありました。人によっては、限界を知ることは怖いと思うかもしれないです。でも、憧れた人に対して、この人が持っている魅力を自分も手に入れることができたら、どれだけ自分が輝けるだろう、みたいに考えるといいんじゃないかと思います。
将来やりたいことがあって、そのために「もっとキラキラした自分になりたい」「もっと褒められる自分になりたい」と思う…。それなら、やった方がよくない?と、良い面を考えるという思考は大事な気がします。
- その考え方はとても素敵ですね。大杉さんの中で、将来の自分像は具体的に描かれているのですか?
私がやりたいこととして、「自分の作品を作る」というのがあります。みんなで協力して作るのももちろんいいけど、多方面に自分の才能や努力を伸ばしていって、1つの作品をすべて自分で作りきってみたいという考えが強いです。
その中で、たとえば必要な技術があったら、「その技術を身に付けた自分になるためには?」と、自分自身の理想像を作って考えて…ということをしています。他にも、たとえば将来の自分のために「音楽をデジタルで作る方法を学んでいてもいいんじゃないか」「人前でプレゼンする能力があってもいいんじゃないか」などと考えて、それをもとに行動していますね。
- その理想像は、N高に行って変わったり具体化されたりしたのですか?
そういう一面もあります。
私は、ダンスはもともとK-popがやりたいと思っていました。でも、N高に入ってみると、周りはボーカロイドのジャンルを踊る人が結構多いということに気がつきました。その人たちを見て、SNSでよく見かける『踊ってみた』とかでおなじみの「みんなが真似しやすい動き」もかわいいな、話題になりそうだな、とか思うわけです。
じゃあ、それらの動きや要素を、自分が今までやってきたダンスに合わせてみたら面白そうだな、などとアイデアが膨らんでいきます。
このような感じで、決まった型にとらわれるのではなく、いろんな人から吸収して、刺激を受けて、理想像が変わっていくということはありますね。
- なるほど。大杉さんを動かす原動力みたいなものを知れた気がします!同世代の高校生にアドバイスするとしたら、どんなことを伝えたいですか?
そうですね。アドバイスになるかはわからないけれど、私は、誰しもやりたくないことはあると思っていて、さらにそれは「やるべきだけど、やりたくないこと」と「やらなくていいし、やりたくないこと」に分解できると思っています。
問題なのは「やるべきだけど、やりたくない」ことをどうやってやるかですよね。
なんでやりたくないのかを考えて、その理由が「めんどくさいから」なら、「手間を省くにはどうしたらいいか」を考えるのは有効だと思います。「このやり方ならめんどくさく感じない」とか、「やっとくと将来につながるかも」とか、たとえ嫌なことでも、物事をいろんな方面から見てみるのは大事なんじゃないかと。
自分の得意・苦手を理解し、物事をそれに合わせて形を変えて、自分のやりたいこととして取り組むことで、「やるべきだけど、やりたくない」ことへのストレスが下がるんじゃないかと思います。
私はそれを大事にしています。
- 「やるべきだけど、やりたくないこと」を理解して、なんとか自分のできる形に寄せていく…ということですね。大杉さんにとって「やるべきだけど、やりたくないこと」は何ですか?
あー、私は、N高の課題レポートがやっぱりめんどくさかったです(笑)
でも、この分野について私が学びを深めて、テストでもいい点を取って単位を取得できたら、「もっとやりたいことができる大学が近づくかもしれない」と考えました。あとは、自分のレポートを見て、「勉強している私ってかっこよくない?」って、時には自分にうぬぼれることも大事かもしれません。
最近はその考え方のおかげで、レポートも楽しいなぁって思えるようにもなっています!
- 考え方一つで変わるということですね。全国の高校生にとってもとても役立ちそうです!
今回はここまでです!
大杉さんが生徒会長になろうと思ったきっかけや、その経緯について詳しくお話してもらいました。
「今」だけじゃなく、いつも「将来」を見据えているからこそ、様々なことに挑戦する勇気が起きるし、新しい世界に飛びこんでいく理由もできるんですね…。やるべきだけど、やりたくないことへの対処法もとても参考になりました!
さて、次回は最終回!大杉さんが現在、生徒会長として取り組んでいることを中心にお伝えします。お楽しみに!
「ぜひ自分の高校も取材してほしい!」といったメッセージも大歓迎ですので、マイページからリクエストお待ちしています。
シリーズ一覧
- ①自分の熱中できることをしたいとN高へ!
- ②やるなら目指せる限界を!生徒会長の原動力とは
- ③学園生活を誇れるものに!生徒会長が描く世界