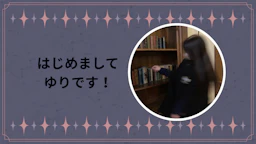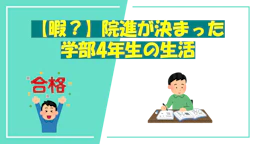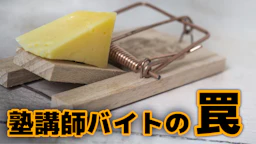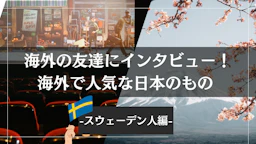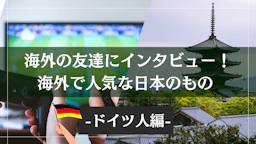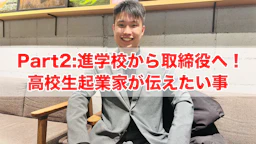こんにちは、しりょかわです〜
最近は海外で学生生活を送る方や、留学をする人が増えてきていますよね。
留学というのは何かと不安が多いので、できるだけ事前に海外の学校生活について情報を得ておきたいですよね。
そこで、高校までの学生生活をアメリカ・日本・イギリスで送った現役慶應義塾生にインタビューしてきました!
内容が盛り沢山なので数回にわたってお伝えしていく予定です。
前回の記事はこちらからどうぞ!
今回は、国際的な大学進学資格である国際バカロレアの実態についてお伝えしていきます!
内容
- イギリスの学校制度
- IB(国際バカロレア)とは?
イギリスの学校制度
中三の途中からイギリスの学校に行かれたとのことですが、イギリスと日本の学校制度は似たりしているんですか?
う〜ん、難しいですね。笑
大学への進学制度という面では大きく異なっていたと感じます。イギリスの高校生は大学に進学するためにA-LevelやIBDP(国際バカロレアディプロマ)という大学進学資格を取得しなければいけないんですよね。だから、高校卒業資格だけだと大学には進学できないんです。
実は私が日本で通っていた中学校もIB校だったので、イギリスでもIBを取得できるインターナショナルスクールに通っていました。
国際バカロレア
国際バカロレア機構(本部ジュネーブ)が提供する国際的な教育プログラム。
国際バカロレア(IB:International Baccalaureate)は、1968年、チャレンジに満ちた総合的な教育プログラムとして、世界の複雑さを理解して、そのことに対処できる生徒を育成し、生徒に対し、未来へ責任ある行動をとるための態度とスキルを身に付けさせるとともに、国際的に通用する大学入学資格(国際バカロレア資格)を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置されました。
現在、認定校に対する共通カリキュラムの作成や、世界共通の国際バカロレア試験、国際バカロレア資格の授与等を実施しています。
(文部科学省I B教育推進コンソーシアムより引用https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/)
IB(国際バカロレア)とは?
IBについて少し詳しく聞きたいんですけど、IBというのは中学校や高校のプログラムもあるということですか?
その通りで、IBのプログラムは3つに分かれています。
- 小学校に相当するPYPプログラム
- 中学校に相当するMYPプログラム
- 高校に相当するDPプログラム
日本の中学校がIB校だったので、日本にいた時からMYPプログラムに取り組んでいました。なので、イギリスではそのままDPプログラムに取り組んでいました。
そして、DPプログラムに合格すれば世界中の大学への志願資格がもらえるという感じです。
DPプログラムではどういったことをするのですか?
DPプログラムでは自分で6科目を選択して学んでいきます。科目は本当に色々あって、私は経済学、地理、生物学、日本語、英語、数学を履修していました。
そして、この6科目以外にEE(Extended Essay)、CAS(Creativity, Action, Service)、TOK(Theory of knowledge)といった修了要件をこなさなければなりません。
なかなか盛り沢山ですね。そえぞれの詳しいことは後で聞くとして、どういった感じで評定がついていくのですか?
まず、IBというのは45点満点なんですね。先ほど6科目履修しなければならないと言いましたが、それぞれの科目で最高7点がもらえます。なので、科目では6×7=42で最高42点もらえます。そして、EE、CAS、TOKがそれぞれ1点ずつで、合わせて最高45点もらえるという感じです。
平均は32点くらいで、40点とかだとオックスフォードのような名門校に進学できる感じです.。
なるほど、その感じだと各科目で満点をとるのはかなり難しそうですね。
日本ではそれぞれの授業が中間試験や期末試験で評定が決まると思うんですけど、IBでの6科目の授業はどのように評定がきまるのですか?
科目の評定はInternal assessmentとExternal assessmentで決まります。
Internal assessment が全体の20%、External assessmentが全体の80%を占めるという感じでした。
Internal assessmentは学校内の試験で、内容は10ページのレポートの作成でした。それぞれの科目につきA4 10ページのレポートを書かなければいけなかったので正直大変でした。
でも、大量のレポートを書いた経験のおかげでレポートへの抵抗は無くなりました。笑
一方で、External assessmentはイメージ的には共通テストに似たものです。その一回のテストで80%が決まります。
External assessmentの結果でいける大学もかなり限られてくるので、試験前はみんなかなり緊張していましたね。
その一回で80%が決まるとなるとかなり緊張しますよね。
それでは、海外の大学進学のためには、Internal assessmentとExternal assessmentで構成される6科目の成績と、EE・CAS・TOKの成績を送るという感じなのですか?
そうなんです、海外の大学に行きたい場合は、専用のサイトに成績と大学の志望動機を提出して、大学からのofferを待つという感じになります。提出できる志望動機が1つだけなので、日本みたいに複数の学部を狙うことができないんですよね。経済を学びたいという感じの志望動機だったら、経済系の学部にしか出願できないという感じです。
大学が学生のスコアと志望動機を見てofferを出すんですね。
そうなんです。ただ、少し複雑なのが本番のExternal assessmentの前に学校で模試があるんですよね。
まず、そのスコアをもとにどの大学に出願するのか決めます。というのも、模試のスコアで足切りがあるんです。
その模試のスコアを提出した時点で大学側からConditional offerとUnconditional offerが来ます。
Conditional offerはExternal assessmentで模試のスコアと同程度のスコアを取ればその大学に合格です、という意味で
Unconditional offerはExternal assessmentのスコア関係なく、その大学に合格、という意味です。
だから、模試のスコアはExternal assessmentと同じくらい重要なんです。
その模試のスコアが返ってくる時はみんなハラハラしてた感じでした...
いかがでしたでしょうか?
10ページのレポートというのは驚きました。大学に入ってからもそんな長いレポートを書くことはなかなかありません。
それを、高校生のうちからやるとなったら正直驚きです。笑
次回の記事ではIBのEE・CAS・TOKとインターナショナルスクールでの高校生活についてお伝えしていきます!
また、この記事も掲載されているokkeという勉強の大きな味方になってくれるアプリの方もぜひダウンロードよろしくお願いします!
- iOSの方はこちら:https://apple.co/3IKMN8x
- Androidの方はこちら:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spesden.okke
最後まで読んでいただきありがとうございます。