社会が嫌いだった私が文系を選んだ理由
前回に引き続き、文理選択についての記事です。
まだやりたいことがはっきりしていない、文系にしようか理系にしようか迷っているという方は、この記事を参考にしていただけると嬉しいです。どちらかを選ばなければならないという現実から締切直前まで目を背け続け、最終的に後悔の残る誤った判断をしてしまうなんてことがあってはいけません。春の段階から文理選択のことを頭の片隅に置いておくことで、そういったことにならないようにしましょう。
前回の記事はこちら。
社会が嫌いな文系
私は「東大入試で高得点を狙えるかどうか」という基準で見て文系を選択しています。
自分の得意不得意は一旦置いておいて、社会(世界史・地理・日本史)という教科だけをみてみた時に、暗記を頑張るだけで得点に結び付くという性質があることに気がつきました。理解能力やセンスなどは問われずただ暗記を頑張るだけで「東大入試で高得点を狙える」わけです。化学基礎や物理基礎が飛び抜けて得意だったわけでもない(かといって苦手意識もなかった)私にとって、このような性質を持った社会は魅力的に映りました。
しかし、実は私、小学生の頃から社会という教科が嫌いだったんです。
中学受験の時は、社会が明らかに足を引っ張っていました。テストに出題されている問題のうち、正解の確信を持って答えを記入できているものはほんの一握りで、選択問題の比較的多い社会は基本的に「運ゲー」だと思っていたほどです。時系列順に並び替える問題は、いつも雰囲気で答えていました。
私が社会という教科を嫌っていた理由は2つだと思っています。ひとつは「暗記が大変だから」。そしてもうひとつが「そこそこ頑張るくらいでは、自分の答えに確信を持てない問題が多いから」。答えに確信が持てないものばかりだと、自分は社会が得意じゃないんだと感じてしまうことが多くあると思いますし、そのせいで社会が嫌いになってしまうのもわかります。ですが、社会という教科の性質上、暗記をとことん頑張れば全ての悩み事は解決するのです。これに気付いた時、「社会は苦手だし文系はちょっと微妙かな...」という気持ちはなくなりました。
もし、自分は社会が苦手だから理系一択だなと思っている人がいれば、「社会が苦手だと感じている」は理系を選ぶ理由にならないんじゃないか?と伝えたいです。ひたすら暗記を頑張ると決意すれば、それは高い確率で高得点につながりますし、立派な受験戦略になり得ると思います。
数学の強い文系
私が文理選択について考え始めた当初は、「数学が得意/理科は普通」と「社会は点がとりやすそう/(社会が苦手)」のふたつを天秤にかけて選ぼうとしていました。「社会は完璧に暗記するだけで全てが解決するから、得手不得手なんてものがそもそもないな」と気がついたは良いものの、ぶっちゃけ「数学が得意/理科は普通」の方が強く、「それでもやっぱり理系なんじゃ...」と思っていました。
そんな中で、学校の先生があるアドバイスをくれたのです。
これが、私が文系の道を志す決め手となりました。
「数学の得意な文系ってめっちゃ強いよ?」
数学が得意な人は、理系を選ぶことが多いです。そのため、文系には「数学が得意ってわけではない/数学は苦手だ」という人が多く集まる傾向があります。つまり、数学が得意だと、そこで周りと大きく差をつけることができるのです。
国語と英語は文系であれ理系であれ同じ水準で頑張る必要があるので文理の選択に影響しない。社会は暗記をこの上なく頑張るだけで得意科目にできる。この2つを考慮した上で、残る数学は既に得意となってくると、文系の学生の中で頭ひとつ抜きん出ることは容易なのではないかと考えることができるわけです。
東大入試でも、数学の得点力が高いと合格はグッと近づいてきます。120点満点の国語や英語、60点満点の社会2科目で他の受験生と20点差をつけるのは至難の業なのですが、20点×4題で80点満点となっている数学においては一瞬で20点の差をつけることができてしまいます。
文系がいいなと思っている人はには、ぜひ早いうちから数学を磨いてほしいと思います。そして、数学が得意な人は安直に理系を選ぶのではなく、文系を選ぶことも視野に入れてほしいです。

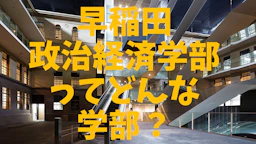
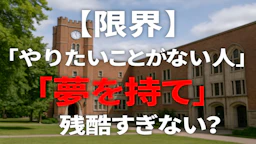

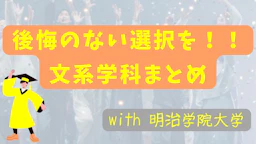
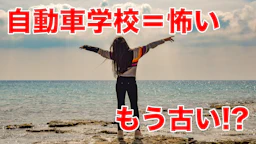
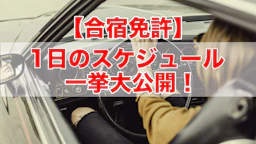


.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)