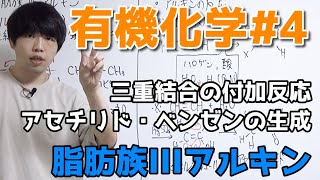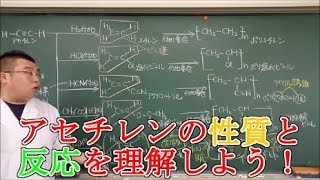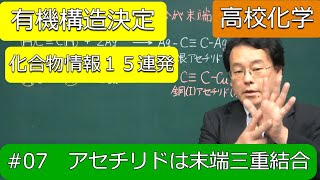アルキン
概要
「アルキン」とは、炭素

アルキンはアルカンからを4個引き抜いた構造なので、炭素数が個であるアルケンの分子式は

二重結合を持つアルケンと同様、電子が密集する三重結合を狙った「付加反応」が起こりやすいです。また、アルキンは三重結合に直接くっつく水素

詳細
アルキンとは
アルキンとは、三重結合を持つ鎖式炭化水素のことです。高校レベルで名前を覚えておいてほしいのは主にアセチレンだけです。

ちなみに、硬い三重結合を持つアセチレンは燃焼熱が大きいため、金属の溶接をするバーナーの燃料として使われています。
アルキンの反応
(1) 付加反応
アルキンは、アルケンと同様で結合に電子が密集しており、この電子を狙った付加反応が起こりやすいです。アルケンのとき同様、ハロゲン、酸、水、水素が付加反応することを覚えておきましょう。

ただし、アルキンの付加反応では2点ほど注意があります。
まず1点目に、アセチレンに酢酸を付加させると、合成高分子の材料などである「酢酸ビニル」が生じます。起こっていることは塩化水素

続いて2点目に、アセチレンに水を付加させると「ビニルアルコール」が生じます。しかしビニルアルコールは非常に不安定なので、即座にアセトアルデヒドに変化してしまいます(*補足1)。

特に後者はイレギュラーな現象が起こっているので、注意して 覚えておきましょう。
(2) アセチリドの生成
アルキンに直接結合する水素

この反応は、三重結合に直接結合する水素でしか起こらないため、末端にある三重結合
(3) ベンゼンの製法
アセチレン3分子を付加反応させることでベンゼンになります。より具体的には、赤熱した鉄管(鉄触媒)中にアセチレンガスを通すことで反応が起こります。

実験室のアセチレンの製法
炭化カルシウム
先ほど(2)で説明した通り、アセチレンは比較的
とはいえ、アセチレンの
[画像]
補足
- (*補足1)詳しくはケト-エノール互変異性をチェック!ちなみにこの反応は、昔はアセトアルデヒドの工業的製法として用いられていました。しかし水銀系の触媒が必要であり、その水銀が有機物と反応して一部漏れ出すことで、「水俣病」という公害が広がることになりました。そこで現在では、
・ 触媒を用いてアセチレンを直接酸素で酸化する「ヘキスト・ワッカー法」が用いられています。 - (*補足2)アルカン、アルケン、アルキンの水素
が外れる電離定数は、順に約 、 、 です。一応これの納得感を得るために、全然厳密じゃないイメージだけの説明をしておきます。 が外れると、炭素に非共有電子対が残ることになります。となったとき、アルカンは隣に別の 結合の共有電子対があり、反発を受けて不安定です。一方、アルキンの隣の電子対は180°反対側の となり、反発が小さくなって相対的に安定です。よって、電離した形が安定なアルキンの方が電離しやすくなります。 こんなヤバい雑説明よりちゃんと知りたい場合は、軌道を理解した上でsp混成軌道のs性と酸性度の関係を調べてみましょう。
関連動画