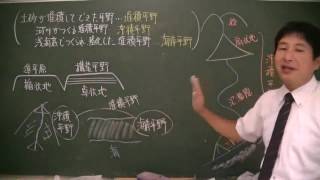火山災害
火山災害
主な火山災害には、以下のようなものがある。
- 溶岩流
- 火砕流
- 津波
- 火山灰の降下
- 土石流
- 気候への影響
溶岩流
溶岩の粘性が低い、溶岩台地や楯状火山でみられる。
現在では、ハワイのキラウエアが有名。

火砕流
火山砕屑物と高温の火山ガスが混合して地表を流下する現象。
溶岩の粘性が比較的低い、成層火山や溶岩円頂丘などで主にみられる。
火砕流は非常に高速(時速約100km/h)で流れ下り、流路の建造物などを破壊し埋め尽くす。
平成6年に長崎県の普賢岳で発生した火砕流は甚大な被害をもたらした。
 (出典:気象庁HP)
(出典:気象庁HP)
津波
大規模な火砕流が海に流れ込んだ時や、大規模な海底火山の噴火が起こった時などに津波が発生することがある。
2018年ではインドネシアで火山性地滑り、2022年にはトンガで海底火山が大噴火し、津波が発生した。
土石流
火山噴出物(岩石、火砕流、火山灰、軽石など)が河川などを堰き止め、それが一気に決壊することで大規模な土石流が発生することがある。
火山灰の降下
火山灰は2mm以下の小さな火山噴出物で、火山噴火の際は広範囲に降り積もる。
道路や鉄道、水道、電気など社会インフラへの影響のほか、農作物の葉に火山灰が積もり、生育不良を引き起こすこともあるなど、農業への影響が大きい。
気候への影響
特に大規模な噴火が起きた際は、火山灰やエアロゾルが成層圏に到達、全地球的に広まることで太陽光が遮られ、気温が低下することがある。
浅間山の噴火による天明の大飢饉、フィリピン・ピナツボ山の噴火による1993年の冷害などが代表的。
食料生産に悪影響を及ぼし、食料不足を引き起こす。
対策
日本では、噴火の危険性が高い火山はGPSを利用して常時観測されており、噴火を事前に予測できるように対策されている。
また、GISを活用したハザードマップの作成も積極的に行われており、防災計画や避難計画などに役立てられている。
関連動画