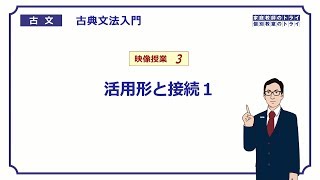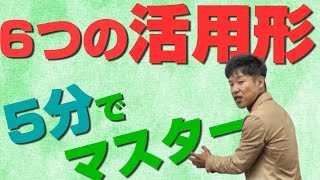活用
活用
例えば、「愛す」という動詞のあとに「ず」という打消の助動詞がくっつくと、「愛すず」ではなく「愛さず」になることはぼんやりとわかると思う。
このように、ある語句の後に別の語句がくっついたとき(これを接続という)、言葉の形が変化することを 「活用」 という。
活用する語は、用言+助動詞、つまり動詞・形容詞・形容動詞・助動詞の4つ。これを意味の通り「活用語」という。詳しくは品詞の辞書を確認しよう。
古文では、下のように6種類の活用形がある。
未然形
未だ然らざる(まだそうなっていない)、という意味で、順接の仮定(もし〜ならば)を表す表現と相性がいい
連用形
用言に連なるという意味
終止形
文を終止させる
連体形
体言に連なるという意味
已然形
已に(すでに)然る(もうそうなっている)、という意味で、確定(〜ので、〜だけれども)を表す表現と相性がいい
命令形
命令する形そのもの
補足
鋭い方はお察しの通り、中学で勉強する現代文の6種類の活用と1個だけ違っていて、「仮定法」のところが 「已然形」 という活用形になる。
なんでこの漢字を使ったの?と聞きたくなるくらい読み方がわからないけど、「いぜんけい」 と読む。一文字目の「已」は、己(おのれ)とも巳(み=へび)ともちょっと違う。中途半端な漢字。
あとは現代文の活用と同じ。
この用語を含むファイル
関連動画
関連用語