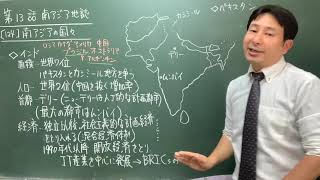緑の革命
緑の革命
緑の革命とは、簡潔にまとめると
高収量品種の開発・導入によって、主に発展途上国において穀物生産量が増加した現象
のことを指します。
大事なのは3点あります。
- 「発展途上国において」
- 「高収量品種の開発・導入」
- 「穀物の生産量が増加」
という点です。
時期的には戦後の話なので、そんなに新しい話題ではありません。字数に余裕があったら「第二次世界大戦後、」などと付け足しておくのも良いでしょう。
「緑の革命って何ですか?」と問われたら、この3点が採点基準になります。必ず覚えましょう。
説明になってなくね?
すみません。これは論述用の形式的な説明であって、皆さんが知りたいのはこの一段階向こうですよね。こんなのはどこの参考書にも単語帳にも載ってます。私が作りたい辞書はこんなものではありません。
というわけで、ひとつひとつ紐解いていきましょう。
戦前の発展途上地域
現在でこそ庶民が米や小麦を食べられるのはいたって普通ですが、戦前はそうではありませんでした。米や小麦が食べられるのは、先進国の人々や発展途上国の富裕層に限られていたのです。
では発展途上国の庶民は何を食べていたのかというと、雑穀です。粟とか稗とかそういうやつです。
これは、ひとえに米や小麦の収量が少なかったからです。米や小麦だけでは足りなかったので、雑穀を作って食べるしかなかったわけです。
このままでは、将来予想される人口増加に食料生産が追いつかず、飢餓が発生してしまう。そう考えたアメリカ合衆国やFAO(国連食料農業機関)は、穀物の増産を図るべく、国際稲研究所などを設立し、穀物の品種改良に着手しました。
高収量品種の開発
そうして、従来の品種よりも収穫量がかなり多い品種が開発されました。これで世界の食糧問題は解決する! と、研究者は大喜びです。
この新しい品種は、食料が不足気味だったアジア諸国で大ヒットし、インドや東南アジアなどで盛んに導入されて米の生産量が急速に増えました。庶民でもおいしいお米が食べられるようになり、食糧問題は解決に向かい始めました。
光と影
しかし、これでみんなハッピー! …というわけにいかないのが世の中というもの。満を持して登場した高収量品種にも、弱点がありました。それは、
- 灌漑設備が必要・・・水を常にあげないとすぐ枯れちゃう
- 大量の肥料が必要・・・従来の稲より栄養がたくさん必要
- 農薬も必要・・・病気や虫害に弱い
という点です。
これって、どれもお金がかかるものですよね。灌漑設備を作る、つまり田んぼまで水路を引っ張ってくるということですが、水路を作るには当然お金がかかる。肥料を買うにもお金がかかる。農薬を買うにもお金がかかる。
結局、高収量品種を導入するためには多額のお金が必要ということになってしまいました。
ですから、その元手のお金が払えない本当に貧しい農民は、高収量品種を導入することができませんでした。結果、貧しい農民はいつまでも高収量品種を導入できず、貧しいままです。
一方、それまでもお金持ちだった農家は、灌漑設備を作り、農薬や肥料を買って、高収量品種を育ててたくさん収穫を得ることに成功しました。米がたくさんとれれば、余った分を売ることができ、もっと収入が増えます。そうして、もともとお金があった農家はどんどんお金持ちになっていきました。
お金持ちはもっとお金持ちに、貧しい農家は貧しいまんま。その結果、農家の貧富の格差が拡大するという負の側面も、緑の革命は生み出してしまったのです。
まとめ
緑の革命とは、 「高収量品種の開発・導入によって、主に発展途上国において穀物生産量が増加した現象」
で、
- 農家の貧富の格差の拡大
などの問題も起こった。
アメリカ合衆国への影響
これはそんなに大事ではないのでコラム程度に読んでください。
アメリカ合衆国は、意外に思う人もいるかもしれませんが世界有数の農業国です。世界最大と言ってもいいかもしれません。
そんな米国は戦後、食糧難が続いていたアジアや戦災で疲弊したヨーロッパへ小麦などの農作物を大量に輸出し、ウハウハでした。景気がよくなった農家は、もっと収穫量を増やそうとお金を借りてきて大型の機械を買ったり、高収量品種の種をたくさん買ったりと、設備投資に積極的でした。
ところが、この緑の革命によってアジアの穀物生産量が上がり、中国も生産責任制の導入で穀物生産が増加、アジアがあまり穀物を買ってくれなくなりました。さらにヨーロッパも共通農業政策で農業生産力を大幅に向上させ、穀物をアメリカに頼らなくてもよくなったのです。
困ったのはアメリカです。大きなお得意先を二つも失ってしまった米国は、自由貿易をヨーロッパや日本に強く求めて穀物を買えと言ってみたりと躍起でした。その努力もあり、ヨーロッパも共通農業政策を見直し、日本も農作物の輸入規制を緩和したりと多少の改善は見られましたが、かつてのような好景気はしばらく戻ってきませんでした。
さらに困ったのは農家です。農家にしてみれば、好景気がしばらく続くと踏んで、借金までして大規模な設備投資をしたわけです。設備投資の回収には20年とか30年とかそれくらいの長期間がかかりますので、この農業不況は致命的でした。
その結果借金が返せなくなり、借金の担保として土地や機械などの資産を銀行や穀物メジャー(穀物メジャーは金貸しもやる)に奪われ、自作農から小作農のような立場に転落する農家が相次いで発生しました。
これは米国で社会問題にもなり、けっこう大変な事態だったそうですが、受験にはまず出てきませんので覚えなくていいです。
関連動画
関連用語