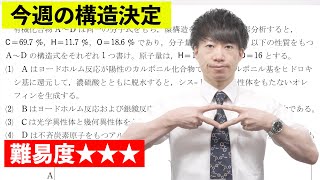シス-トランス異性体
概要
「シス-トランス異性体」とは、二重結合などが回転しにくいことで生じる異性体のこと。たとえば2-ブテンでは、下図の赤線の二重結合のラインに対し、同じ側にメチル基を持つシス-2-ブテン、赤線を跨いで反対側にメチル基を持つトランス-2-ブテンが存在します。
また二重結合に限らず、環構造のせいで結合が回転できない場合もシス-トランス異性体が存在することがあります。たとえば1,2-ジブロモシクロプロパンでは、以下のようなシス-トランス異性体があります(*補足1)。
詳細
シス-トランス異性体のイメージ
単結合で繋がれた原子は簡単にくるくる回れます。だから、下図のように官能基を入れ替えても、回転させれば同じものになりますね。
一方、二重結合で繋がれた原子は見るからに回転が難しそうです。ちょうど、たこ焼きを2本の爪楊枝で刺せば回転せずに食べやすいのと同じです(*補足2)。これによって、C=Cにくっつく官能基の位置によってシス-トランス異性体が生じることがあります。
しかし、たとえばエタン
少しハイレベルな理解
結合の仕組みを思い出して、もう少し正確に考えてみます。単結合は「σ結合」によるもので、σ結合は結合軸を回転軸として原子を回転させても結合に変化がありません。よって簡単に回転することができます。
ただし正確には、C-Cに結合する官能基の影響が存在します。たとえばブタンの場合、真ん中のC-Cが回転することで左右のメチル基の位置が変化します。そしてできることなら、左右のメチル基はできるだけ遠くにいた方が嬉しいです。なぜならメチル基はいくつか電子対を持っていて電気的に反発するからです。
しかし、ほとんどの場合その影響は限りなく小さいので、普通はその程度は無視して回転できます(*補足3)。
一方、二重結合は1つのσ結合と1つの「π結合」からできています。σ結合を軸に回転させるとπ結合が壊れてしまうため、二重結合は簡単には回転できません。
ただし、σ結合に比べてπ結合の方が切れやすい(エネルギーが高い)ため、熱や光のエネルギー(と触媒)を加えてπ結合のみを一時的に切ることができます。よって、熱や光によってシス-トランスが入れ替わる異性化が起こることがあります。入試問題でもさらっと回転させてくることがあるので、頭の片隅に入れておきましょう。
環構造によるシス-トランス異性体
また二重結合でなくても、環構造によってシス-トランス異性体が生じる場合があります。たとえばジクロロシクロプロパンでは、環構造によってC-Cが回転できずに以下のような異性体が生じます。
ちなみに、今回のC-Cの炭素は共に不斉炭素原子なので、これらはシス-トランス異性体ではなく鏡像異性体と数えることもできます。
補足
- (*補足1)1、2の炭素を不斉炭素原子と捉えれば、鏡像異性体と捉えることもできます。
- (*補足2)子供の頃、関西に旅行に行った時に食べたたこ焼きが妙に美味しかった記憶があるのですが、やっぱり関西のたこ焼きは違うのか思い出補正なのか、今だにわからないままです。
- (*補足3)たとえばナフタレンなどのような巨大な構造がくっついた場合、官能基がぶつかってしまうためC-Cが回転できなかったりします。実は単結合でもそのような場合はシス-トランス異性体が生じることになります。
関連動画
関連用語