酸素解離曲線
そもそも
酸素は体内で、赤血球中のヘモグロビンという色素により全身に運ばれる。
ヘモグロビンが酸素を持った状態を「酸素ヘモグロビン」と言う。
酸素ヘモグロビンは全身のいたる場所に酸素を届け、酸素を届けた酸素ヘモグロビンは、また「ヘモグロビン」に戻る。
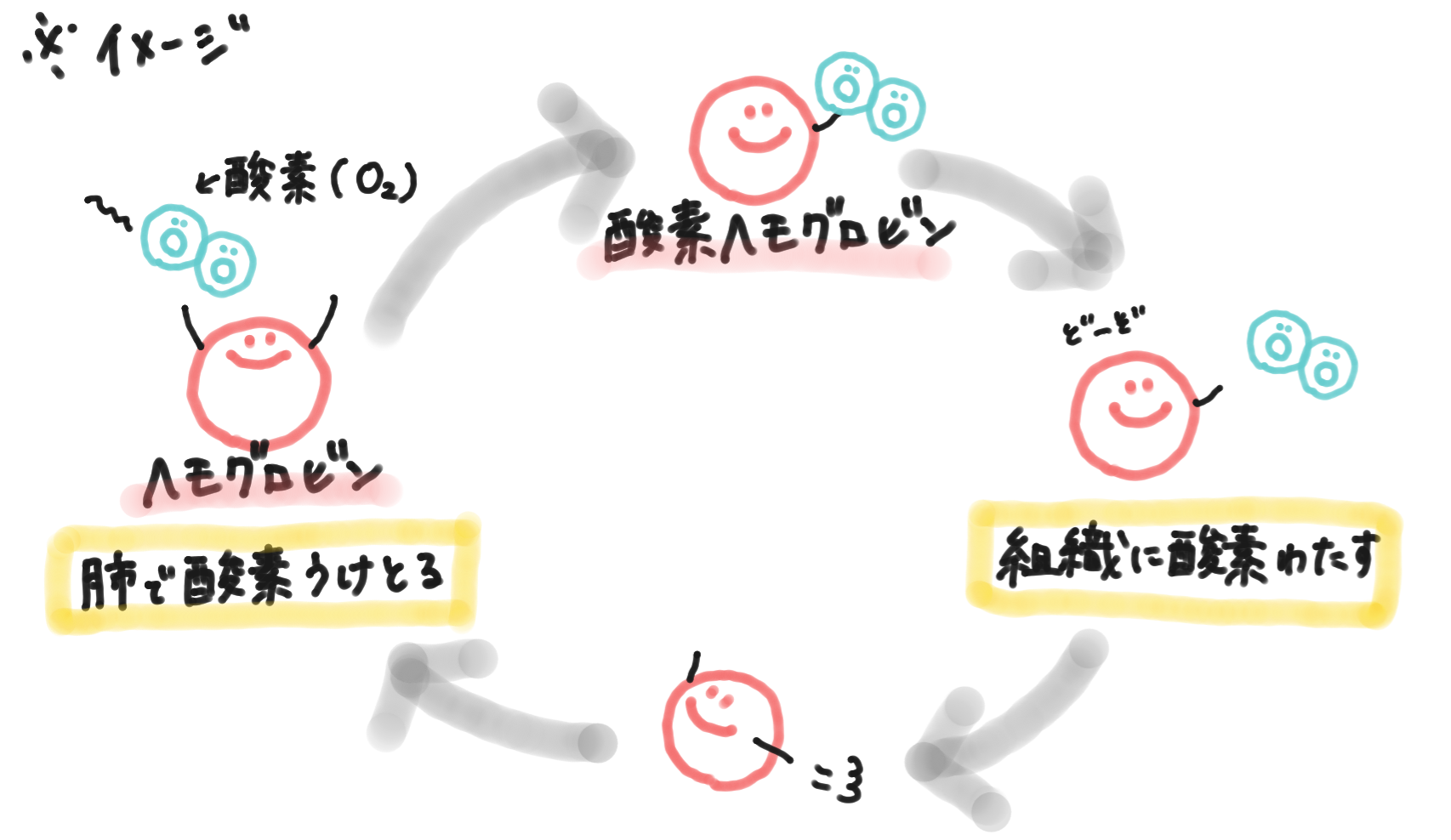 そう、体内には、「ヘモグロビン」と「酸素ヘモグロビン」が存在しているということだ。
そう、体内には、「ヘモグロビン」と「酸素ヘモグロビン」が存在しているということだ。
酸素解離曲線とは
酸素解離曲線とは、ヘモグロビン全体のうち、どれくらいの割合が酸素ヘモグロビンとなっているか、を表したグラフである。
横軸は酸素の量となっている。
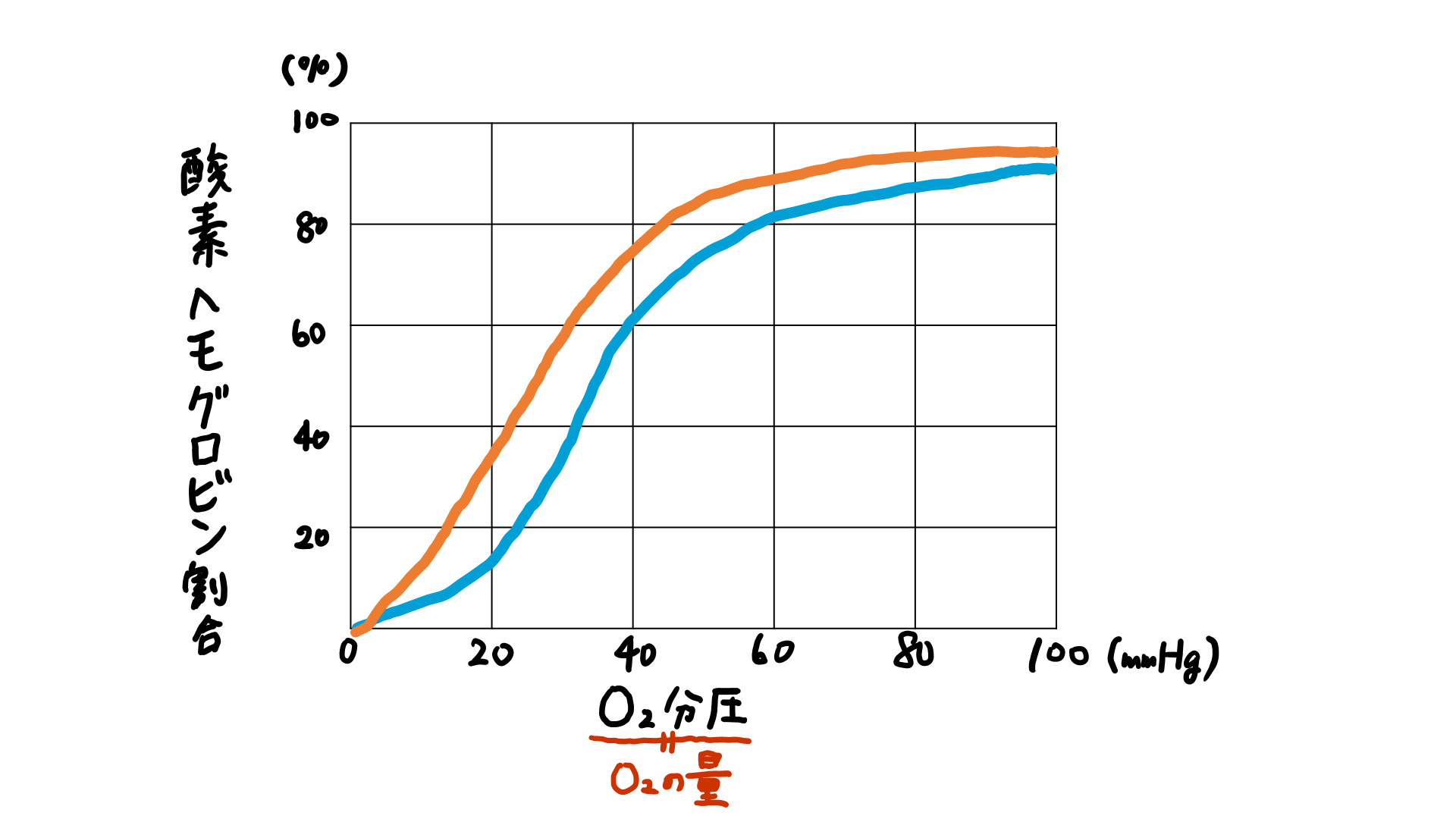
何がわかるの?
図から酸素濃度が低くなると、酸素ヘモグロビンの割合が小さくなることが読み取れる。
このことから、酸素濃度が低くなると、酸素ヘモグロビンが酸素を解離するということがわかる。
簡単に言えば、酸素ヘモグロビンは、酸素が少ないところに酸素をお届けしているということである。
図の見方
酸素解離曲線では、一般的に
- 肺胞
- 組織
2つの曲線が記してある。
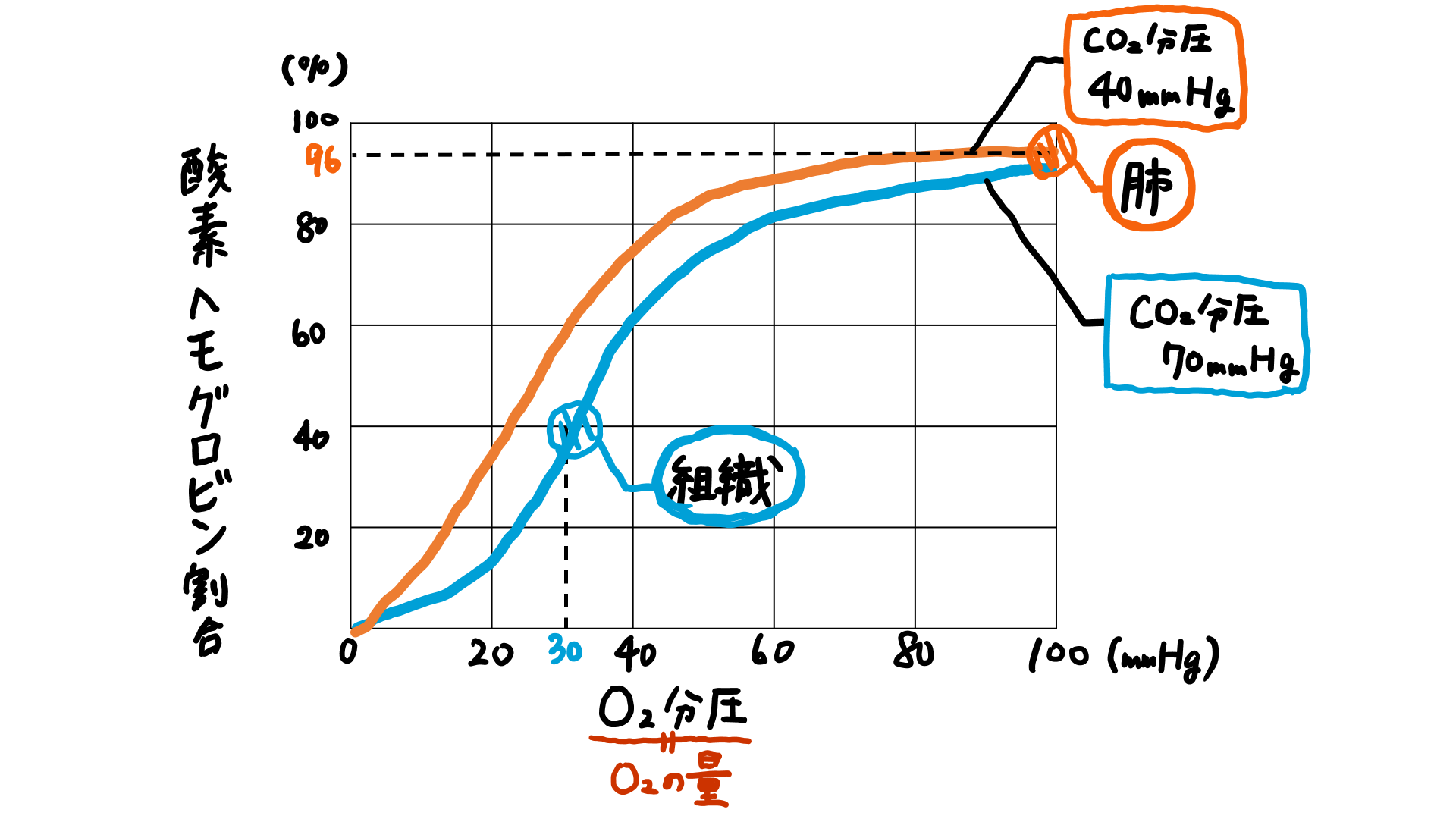 これらをどのように読み取るのか、実際に上の図と以下の例題を用いて見てみよう。
これらをどのように読み取るのか、実際に上の図と以下の例題を用いて見てみよう。
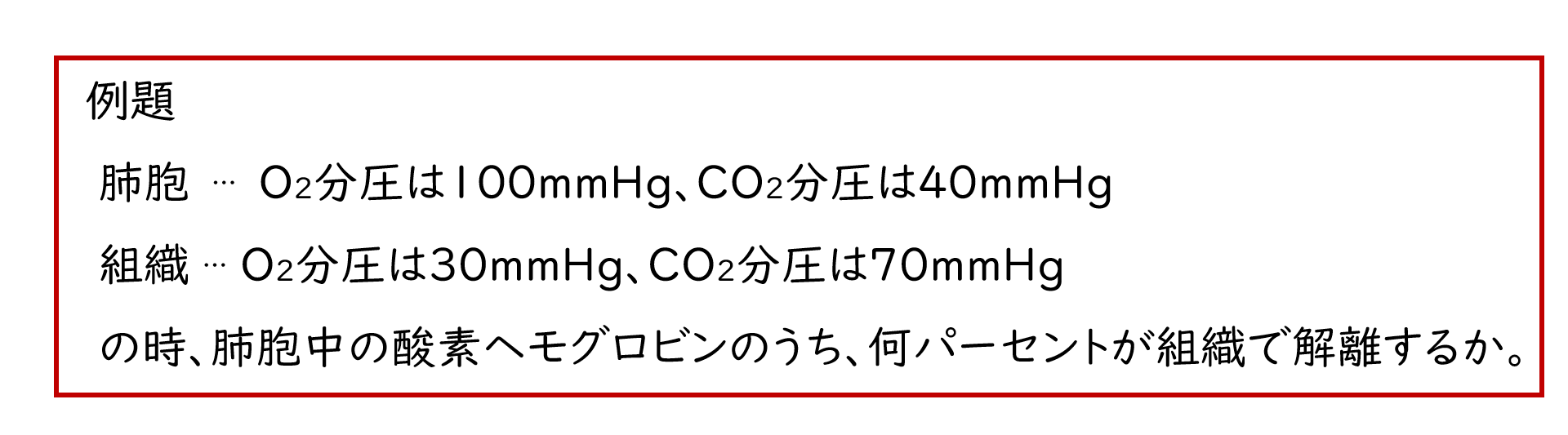
【解き方】 読み取る数値は、上図に大きく丸で印をつけた部分である。
肺胞はCO2分圧が40mmHgなので、オレンジのグラフを見る。
肺胞の酸素ヘモグロビンの割合は、96%
一方で組織ではCO2分圧が70mmHgなので、青のグラフを見る。
組織の酸素ヘモグロビンの割合は、40%
ということは、
56%の酸素ヘモグロビンが、組織で酸素を離した、すなわち、解離したということになる。
しかし、これはまだ答えじゃないので注意!!!!
今聞かれているのは、 「肺胞中の酸素ヘモグロビンのうち」
つまり、96%のうちの何%が解離したか。
なので、
よって、58%が答えになる。
この手の計算問題はよく出題されるため、しっかりと把握しておこう!!
関連動画
関連用語




