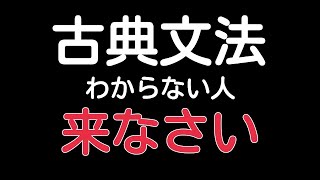音便
音便
例えば日常会話で、動詞の「書く」に助詞の「て」をくっつけたときに、活用表通りに「書きて」と言うのではなく、「書いて」の方が言いやすいはず。
「これ明日学校に出さないといけないから書いてね」といったイメージ。
このように、単語の中のある音が、発音しやすいように変化し、活用表と違う文字になることがある。これを音便(おんびん) という。
古文では下の4つがあるので、どの文字に変化することを何音便と言うか押さえておいて、あとは読んだときのリズムで判断していこう。
覚え方は補足にて。
イ音便
名前の通り、「い」に変化する音便のこと。語尾の「き・ぎ・し」などが変化する。
例:泣きて → 泣いて
ウ音便
名前の通り、「う」に変化する音便のこと。語尾の「ひ・び・み・く」などが変化する。
例:思ひて → 思うて
(「ひ」が「い」になってイ音便になりそうだけど、「う」に変わるので注意)
撥(はつ)音便
撥音とは「ん」のことで、撥音便は「ん」に変化する音便のこと。語尾の「び・み・に・る」などが変化する。
例1:飛びて → 飛んで
例2:あるなり → あんなり → あなり
※ ラ変活用をする活用語のあとに、推定の助動詞「なり」「めり」が付く場合は撥音便となり、しかも「ん」が省略されることがある。
促(そく)音便
促音とは「っ」のことで、撥音便は「っ」に変化する音便のこと。語尾の「ち・ひ・り」などが変化する。
例:走りて → 走つて
※ 古文では「っ」は「つ」と書く(読むときは「っ」)
補足
きっと全国の95%くらいの高校生は、撥音便と促音便が、どっちがどっちか覚えられないという悩みを抱えている。
覚え方としては、
- 撥(はつ)音便が「ん」
- はつ・ん
- は・ん・つ(ん を中へ)
- パンツ
- は・ん・つ(ん を中へ)
- はつ・ん
- 促(そく)音便が「っ」
- そく・っ
- そ・っ・く・(す)(っ を中へ)
- ソックス
- そ・っ・く・(す)(っ を中へ)
- そく・っ
とムリヤリ下着名に語呂合わせできる。
関連動画