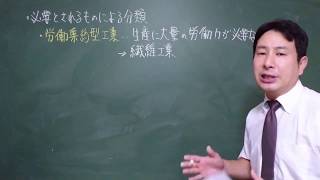集約的・粗放的
サラッと流しがちだけどけっこう大事
「集約的」「粗放的」という単語。農業を分類するうえで非常に重要な概念で、いろいろなところに出てくるのですが、いまいちイメージをつかみにくいという人が多いようです。
逆にこれが分かってしまえばかなり有利になります。系統地理でせいぜい200語程度しかないこのokedic地理で私がわざわざ一つの用語として取り上げたのは、この用語がそれだけ重要だからです。
集約? 粗放?
普段耳慣れない言葉ですし、意味を掴みづらいのはある意味当然ではあるでしょう。ですからまずは大まかなイメージを持ってほしいと思っています。
誤解を恐れずに非常にざっくり言うと、
- 集約的・・・狭いところでめっちゃがんばる。家庭菜園みたいな感じ。
- 粗放的・・・広々したところで大雑把にやる。アメリカの農家みたいな感じ。
といった感じです。細かいところは後々詰めていくので、まずは大雑把に捉えておいてもらえれば十分。
「集約度」という概念
この記事の見出しは「集約的・粗放的」ですが、「粗放的」というのは「集約的」の対義語ですから、実質的には、どの程度集約的なのかという「集約度」を理解していれば事足りるわけです。集約度が高ければ集約的、低ければ粗放的ということになります。
そして、この「集約度」を評価するうえで、特に高校農業地理で扱う評価基準が労働集約度と資本集約度の二つです。
労働集約度
耕地の単位面積当たりにどれだけの労働量を投下するか、という指標です。 例えば1haの農地があったとして、10人の人間が毎日8時間農作業をしている畑と、一人で毎日3時間仕事をしている畑では投下されている労働量が全く違うことが分かりますね。
この場合、
前者は「労働集約的(労働集約度が高い)」、
後者は「労働集約度が低い」と言えます。
(なぜか、「労働粗放的」と言うことはないんですよね…)
一般的に、機械化が進んでいない地域は多くの農作業を人力で行わなければならないため投入する労働量が多く、労働集約的農業となる傾向があります。逆にアメリカやオーストラリアなど機械化が進行している地域では単位面積あたりに投入される労働量は極めて小さく、労働集約度は低くなります。
当然と言えば当然の話なんですよね……私の父方の実家は農家で父は今でも米を作っているのですが、稲を刈るときなんか人力と機械を比べたら作業効率に雲泥の差があります。何十年も農家をやっている近所のおばあちゃんでも一把刈るのに1.2秒かかるのですが、その間にコンバインは10把ほども刈ってしまい脱穀まで済ませてしまうのです。圧倒的な差です。コンバインと同じことをしようと思ったら今の数十倍の助っ人を呼んでこなければなりません。機械の有無で必要な労働量が全然違うって、こういうことなんです。
資本集約度
耕地の単位面積あたりにどれだけの資本を投下するかという指標です。資本とはつまりお金です。
農業にはお金がかかります。種を買い、肥料を買い、農薬を買い、農機具も買わなければなりません。トラクターって高いんですよ。普通の車と同じかそれ以上の値段がします。
極端な例を挙げると、野菜工場なんかは建設するのに平均して3億円(!)もかかるそうです。このように、大きなコストをかけて農業を行った場合は「資本集約的」と言えるでしょう。
一方で、ほとんどお金をかけない農業も存在します。肥料はあまり使わない、機械化も進んでいない、農薬も使わない、となったらあまりお金はかかりません。このような農業は「資本集約度が低い」といえます(またもや、「資本粗放的」とは言いません。なぜなんでしょう)。
ではなぜお金をかける農家が存在するかと言えば、その方が一人当たりの耕せる面積が増えたり作物がよく育ったりして儲かるからです。あるいは、日本のように土地が狭い国では収穫量を増やすためには単位面積当たりの収量を増やさなければなりませんから、肥料を大量に使ったりします。逆に貧しい発展途上国の農家は肥料や農薬、機械を買うお金もなかったりします。
まとめよう!
だいぶ説明が長くなってしまったのでまとめましょう。覚えて帰ってほしいことが3つあります。
- 二つの「集約度」・・・労働集約度と資本集約度
- 労働集約度=単位面積あたりに投下された労働量
- 資本集約度=単位面積あたりに投下された資本
これだけ分かっていてくれれば大丈夫です。
この用語を含むファイル
関連動画
関連用語