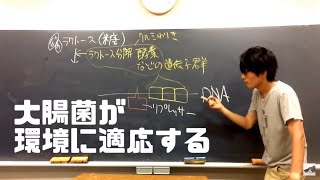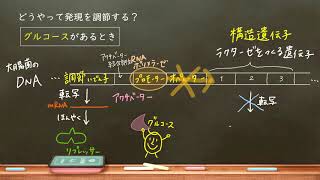オペロン説①(トリプトファンオペロン) 高校生物
概要
動画投稿日|2015年7月12日
動画の長さ|7:07
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
オペロン説について講義します。
語呂「じゃあ、物をペロペロする(ジャコブ、モノー、オペロン説)」
語呂「プロのオペはこうだぞ!(プロモーター、オペレーター、構造遺伝子はこの順番で並んでいる)」意味のない語呂ですね。すみません。
覚え方「ひとつのオペレーターに制御されるから、オペ ロン という。オペロンはもともとオペレーターに制御されるひと単位という意味。」
覚え方「転写を促進するからプロモーターという。実際、遺伝子組換え技術を用いてプロモーターを強力な配列に取り換えることで転写速度を上げることもできる」
「環境から受け取ることができる唯一の指令は、調節タンパク質の介在によるものであって、それはひとつの信号、すなわち進行または停止である。それゆえ、遺伝のメッセージの読み取りは、喫茶店のジュークボックスが出す音楽に似ている。ボタンのひとつを押すことによって、その機械のレコードの中から聞きたいと思うレコードを選ぶことができる。」ジャコブ『生命の論理』
*リプレッサーはタンパク質部分でDNAに結合します。板書のようにトリプトファンは馬鹿でかくないし、トリプトファンがDNAに結合することはありません。板書は不正確です。念のため。(実際は、トリプトファンオペロンのリプレッサーは、アロステリックタンパク質であり、トリプトファンとの結合によってその立体構造を変化させ、DNAとの親和性を高める。結果、リプレッサーは強くDNAに結合し、構造遺伝子の発現を抑制する)。
オペロン説の発展的な講義はこちら。
https://youtu.be/6AosmRAJ0vg
●リプレッサーが結合するDNA領域をオペレーターという。
●調節タンパク質によって発現が調節され、酵素などをコードしている遺伝子領域を『構造遺伝子』という。以下にポイントをまとめておく。
①遺伝子の中には、他の遺伝子の働きを調節する調節遺伝子という遺伝子がある。
②調節遺伝子から調節タンパク質(リプレッサーなど)がつくられる(調節遺伝子は調節タンパク質のアミノ酸配列をコードしている。調節遺伝子が転写・翻訳され、調節タンパク質が合成される)。
③調節タンパク質はDNAのオペレーターに結合することで、構造遺伝子(酵素などのタンパク質を支配する遺伝子)を発現を調節する
なお、調節タンパク質には転写を抑制するもの(リプレッサーという)と、活性化させるもの(転写活性化因子とよぶことがある)がある。
●もともと、「単一のオペレーターによってまとめて転写が調節される遺伝子群」の単位を、「オペロン」と呼んでいた。「オペロン」の「オペ」は「オペレーター」の「オペ」である。
●リプレッサーがDNAのオペレーター」に結合していると、RNAポリメラーゼがプロモーターに正しく結合できず、転写は抑制される。
●実際は、トリプトファンオペロンの場合は、オペレーターはプロモーターの内部にある。ラクトースオペロンの場合、プロモーターとオペレーターは重なっている(厳密には、オペレーターの1つはプロモーターと隣り合っており、もう一つのオペレーターはlacZのコード領域内にある。四量体であるリプレッサーは、2か所のオペレーターに同時に相互作用し、その結果、DNAのループが形成される。すると、RNAポリメラーゼとプロモーターの結合が抑えられる)。
●オペロン説が発表された当時、リプレッサーは単離されておらず、それがRNAなのかタンパク質なのかさえわかっていなかった。
<Q.ラクトースとかトリプトファンって何?…ラクトースの別名は乳糖。哺乳類の乳にも豊富に含まれる糖。トリプトファンはアミノ酸の一種。>
●トリプトファンオペロン(宿主がトリプトファンを多く食事を含む食事をしている時など、トリプトファンを大腸菌が自分で合成する必要がない場合は、トリプトファン合成にかかわる酵素の発現は抑制されている):リプレッサーがトリプトファンと結合し、活性化される(オペレーターとの親和性が上がる)。活性化したリプレッサーによって、トリプトファン合成酵素(トリプトファンの合成にかかわる数種類の酵素の遺伝子群)の遺伝子の転写が抑制される。
●ラクトースオペロン(ラクトースがあり、グルコースがない場合のみ、ラクトース分解にかかわる酵素群が発現される):グルコースがなくラクトースがあるとき、リプレッサーがはずれる(ラクトースが変化したアロラクトースがリプレッサーに結合する。すると、リプレッサーの立体構造が変化し、リプレッサーのオペレーターに対する親和性が下がる)。その結果、構造遺伝子の転写が活性化される。
●ラクトースオペロンのCAPによる調節:細胞内にグルコースが豊富にある場合、別な仕組みが働き、ラクトース分解に関わる酵素群の転写は抑制されることが知られている(細胞内にグルコースがないとき、大腸菌はcAMPを生産する。cAMPがCAP[環状AMP受容タンパク質]というタンパク質に結合すると、CAPはDNAに結合できるようになり、ラクトース分解に関わる酵素群の転写を活性化させる[オペロンをONにする])。
つまり、①グルコースがなく(CAPが活性化し)、②ラクトースがある(リプレッサーがオペレーターからはずれる)時にのみ、オペロンがONになる。
*ジャコブとモノーが提示したオペロンのモデルは「グルコースとラクトースが両方存在している培地で生育している大腸菌がラクトース分解酵素を発現しないのはなぜか」という疑問に触れなかった。実際は、上述のように、CAPが関係していた。
●ラクトースオペロン、トリプトファンオペロンにおいては、調節タンパク質=リプレッサーと覚えて問題ない。真核生物では、ふつう、遺伝子の発現調節に、転写を活性化する調節タンパク質も多くかかわる。(大学内容なので覚えなくてよいが、大腸菌のアラビノースオペロンの調節遺伝子の生成するタンパク質のように、そのままではリプレッサーとして負の制御を行うが、アラビノースと結合するとオペロンの転写を積極的に行わせるような正の制御物質となる場合もある。)アラビノースオペロンについてはnoteを参照せよ。
●ジャコブとモノー(2人ともフランス生まれ)は大腸菌において、関連した一連の生合成経路をコントロールする遺伝子は、染色体上にランダムに配置されているのではなく、一つのグループをつくって存在することを明らかにし、このユニットを「オペロン」と命名した。彼らは、DNAからリボソームへ情報を伝達する分子(mRNA)の存在も予測していた。
●原核生物のmRNAは合成され次第リボソームが結合し翻訳がはじまる。しかし、真核生物のmRNAには、スプライシングが終了したことをあらわす目印があり、その目印が付加されない限り核から出られない。真核生物では、スプライシング(や、大学で学ぶが、5'キャップの付加、ポリAテールの付加[ポリアデニル化])が終了しない限り、未熟なmRNAは核から出れず、翻訳のステップに進むことは出来ない。
●入試に合わせて動画のように説明したが、たとえば「リプレッサーのみでオペロンが調節されている」という定説はすでに覆されている。たとえば、トリプトファンオペロンにおいて、実際はトリプトファン濃度の上昇による転写減衰(attenuation:プロモーターから始まり転写減衰域付近まで転写されてきたmRNAの合成が、細胞内トリプトファン濃度がある程度以上高い時はその位置で終末する)が関わっている。実際の話は大学で学んでほしい。
●一般に、原核生物のmRNAは複数のタンパク質の情報を含むが、真核生物のmRNAは1つのタンパク質の情報しか含まない。
*以下の問題は、トリプトファンオペロン、ラクトースオペロンの両方について学んでから解いてください。
問題:大腸菌において、ラクトース分解にかかわる酵素は、培地にグルコースがなくラクトースがある場合、ふつう①合成される ②合成されない どちらか?
答え:①(グルコースがある時はグルコースを優先的に使うが、グルコースがなく、ラクトースがある場合はラクトース分解に関わる酵素を発現する)
問題:大腸菌において、一般に、トリプトファン合成にかかわる酵素は細胞内にトリンプトファンがあると合成①される②されない どちらか?
答え:②(自分でトリプトファンを合成する必要はない)
問題:リプレッサーのように、遺伝子の発現を調節するタンパク質のことを一般に何というか。
答え:調節タンパク質(調節タンパク質は転写因子ともいう[大学では転写因子と言うことが多い]。調節タンパク質をコードしている遺伝子を『調節遺伝子』という)
問題:リプレッサーなどの調節タンパク質(遺伝子の発現を調節するタンパク質を調節タンパク質という)をコードする遺伝子を何というか。
答え:調節遺伝子
(リプレッサーなど、転写を調節するタンパク質は調節タンパク質とよばれる。リプレッサーという調節タンパク質は、DNAのオペレーターという領域と結合し、転写を抑制する。高校ではあまり習わないが、転写を促進する調節タンパク質[アクチベーターなどと呼ばれる]もある。調節タンパク質をコードしている遺伝子領域を『調節遺伝子』という。)
問題(発展):ある変異Xが起きた大腸菌がいる。
この変異Xをもつ大腸菌は、ラクトースの有無にかかわらず、常にラクトース分解酵素を発現している。
この大腸菌に、リプレッサー遺伝子(調節遺伝子)が入ったプラスミドを新たに導入したが、変化はなく、常にラクトース分解酵素を発現してた。正しいのはどちらか。
①変異Xは調節遺伝子に起きた変異であり、正常なリプレッサーがつくれない。
②変異Xはオペレーターに起きた変異であり、そのオペレーターにリプレッサーが結合できない。
答え:②(①ならば、正常なリプレッサーをつくる調節遺伝子を別に導入すれば、そのリプレッサーがオペレーター[リプレッサーが結合するDNA領域]に結合し、ラクトース分解酵素の発現を止めるはずである。②のように、オペレーター[リプレッサーが結合するDNA領域]に変異がある場合は、今回のように、新しい正常なリプレッサーをつくる調節遺伝子を導入しても、それがくっつく場所が壊れているので、意味がない。リプレッサーは壊れたオペレーターにくっつくことができず、ラクトース分解酵素がずっと発現しっぱなしになってしまう)
#遺伝子
#オペロン説
#高校生物
関連動画