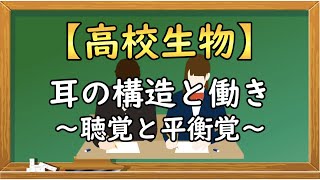【耳④】前庭・半規管
概要
動画投稿日|2023年9月2日
動画の長さ|5:49
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
平衡覚に関わる、前庭と半規管について講義します。
耳の講義③はこちら
https://youtu.be/ZXK74VqOGSo
*noteに簡単な図があります。
https://note.com/yaguchihappy/n/n4e5dd145afbc
語呂「前提が傾く(前庭は体の傾きを感じる)」
問題:(1)体の回転を感知する場所および(2)体の傾きを冠とする場所は、以下の内どこか。1つずつ選べ。同じものを選んではならない。
①半規管 ②うずまき管 ③前庭
(1)①(2)③
●傾きや回転などの感覚を平衡覚(へいこうかく)という。
●耳は、音受容器であると同時に、平衡受容器でもある。
●前庭(ぜんてい)は、耳石(じせき。平衡石ともいう。小さな炭酸カルシウムの結晶)で体の傾きを受容する。
*耳石は重い(知らなくてよいが、周囲の液体や組織に比べて2~3倍の比重がある)。この耳石の重みは、有毛細胞の感覚毛を重力の方向に曲げる。前庭はこのような仕組みで体の傾き(重力の方向)を検出している。
●耳石は、耳石膜(糖タンパク質[有毛細胞の周りにある支持細胞が分泌したもの]からなる)というゼラチン状の物質の上にある。耳石膜の下部は、有毛細胞の感覚毛を覆っている。
*前庭について、正確には、板書で示したような構造物(有毛細胞と支持細胞からなる感覚上皮)を平衡斑(へいこうはん)といい、体の傾きだけでなく、直線方向の加速、減速も感知している(たとえばエレベーターや乗り物が加速・減速をする時の感覚)。前庭の中にある球形嚢(きゅうけいのう)と卵形嚢(らんけいのう)という2つの場所に、それぞれ平衡斑がある(2つの平衡斑はほぼ直交している[球形嚢は垂直、卵形嚢は水平])。卵形嚢、球形嚢と半規管をあわせて前庭器といい、前庭神経を通じて脳へ平衡覚を伝えている。
●耳石の成分は、生物種によって異なる。脊椎動物では耳石は炭酸カルシウムからできており、細胞が分泌して出来上がるが、エビ・カニなどでは水底の砂粒を取り込んで、それを耳石とする。
●半規管(はんきかん)は、リンパ液の流れで体の回転を受容する。板書は適当に描いているが、半規管は、xyz平面に配置されている(したがって「三半規管」とも呼ばれるが、教科書に合わせて、大学入試では書かないほうが良い)。よって、回転運動を三次元で検出することができる。
●3つの半規管のそれぞれには膨大部というふくらみ(少し広い部屋のような部分)があり、そこに有毛細胞がある。有毛細胞の感覚毛はクプラと呼ばれるゼラチン状の物質に埋まっている(クプラは板書していない)。
*クプラも、前庭の耳石膜のように支持細胞によってつくられると考えられているが、よくわかっていない。
*頭部が回転を始めると、リンパ液は慣性のために取り残され、頭部の回転方向とは逆方向に移動し、クプラが押されて感覚毛が倒れる(自転車に乗っているとき、自転車の進む方向とは逆方向に風を受ける。クプラも、回転方向とは逆向きの力を受ける。そんなイメージでとらえておこう)。
*回転の終了時には、リンパ液は慣性のためにしばらく流れ続けるため、感覚毛は回転開始時とは逆方向に倒れる。
①回転開始時:回転方向とリンパ液の動きは逆向き。感覚毛は、回転方向とは逆向きに倒れる。
(リンパ液は、体の回転方向と同じ方向に加速されていく。やがて同じ体の回転と同じように回転するようになる→②へ)
②回転中:回転方向とリンパ液の動きは同じ向き。からだの回転と同じようにリンパ液も回転するので、感覚毛は傾かない(等速で動くバスではよろめかずに立っていられることを思い出そう)。
③回転停止時:体が回転を停止しても、リンパ液は回転していた方向と同じ向き(①と逆向き)に動き続ける(感覚毛は①と逆向きに倒れる)・・・目が回っている感覚が生じている状態。
(動画中のバスに乗っている時のたとえ話は、覚え方の参考として話している。実際は、感覚毛は、慣性により取り残されたリンパ液がクプラを押すことにより曲がると考えられている[体が加速され回転し出しても、リンパ液はもとの位置に留まろうとするから、体に対してリンパ液の相対的な動きが生じる。やがてリンパ液も体の運動方向と同じ方向に加速され、体と同じ速度で回転するようになる。その後、体が停止しても、リンパ液は慣性により同じ方向に運動を続ける。バスの中の高校生の挙動は、リンパ液に似ている]。また、観測者がどこにいるかによって見える運動は異なるので、厳密には動画の説明は正確ではないが、高校生物では気にしなくてよい。)
●前庭、半規管がキャッチした情報は、前庭神経(ぜんていしんけい)によって脳へ伝えられる。
●有有毛細胞は静止状態の時でも神経伝達物質(主にグルタミン酸と考えられている)を放出しており、感覚ニューロンの活動電位が一定の頻度で発生している。
①有毛細胞の感覚毛がある方向に傾くと、神経伝達物質の放出量が増え、感覚ニューロンにおける活動電位発生頻度が増加する。
②有毛細胞の感覚毛が①とは反対向きに傾くと、神経伝達物質の放出量が減り、感覚ニューロンにおける活動電位発生頻度が減少する。
●現実には、黒板に書いた構造物が内耳に存在するわけではない。よく問題に出てくる黒板に書いたような内耳は、実際は、骨迷路の鋳型である。内耳は、正確には、側頭骨の内部をうがつ骨迷路(緻密骨で囲まれた複雑な形の管腔。うずまき管、前庭、骨半規管よりなる)と、その内部にある膜性の膜迷路からなる(膜迷路は、軟らかい膜性の閉鎖管で、中に内リンパを満たす。膜迷路は、骨迷路中にほぼ同形をなしておさまっている[うずまき管の中にうずまき細管が、前庭の中に卵形嚢・球形嚢が、骨半規管の中に半規管がおさまっている])。骨迷路と膜迷路の間には外リンパがある。
0:00 内耳
0:30 前庭
1:40 半規管
3:18 発展(感覚毛が倒れる向き)
#耳
#前庭
#半規管
関連動画
関連用語