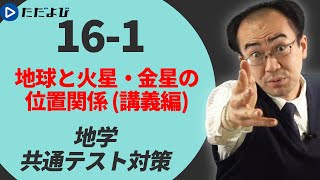原始太陽系に起こった謎の大激変【後期重爆撃仮説】
概要
動画投稿日|2020年3月29日
動画の長さ|8:03
これまで数十年にわたって、太陽系の初期には天変地異「後期重爆撃期」が存在したと考えられてきました。しかし、ここ数年の研究で、そのシナリオが根底から覆されようとしています。最新の研究からわかった、科学界を二分する大論争について、専門家の視点で解説します。
(目次)
0:00 後期重爆撃期とは何か?
1:17 なぜ「後期」なのか?
2:04 なぜ天体衝突が再び急増したのか?
3:34 後期重爆撃を支持する証拠
4:10 パラダイムシフトが起こりつつある
5:42 軌道力学からも否定されつつある後期重爆撃
6:43 生命の起源との関連
(参考文献)
Dynamical evidence for an early giant planet instability.
R.S. Ribeiro et al. (2020) Icarus 339, 113605.
https://doi.org/10.1016/j.icarus.2019.113605
【音楽素材】
https://www.bensound.com/
【画像素材】
NASA, ESA, 国立天文台
【字幕説明】
本日紹介するのは、2019年12月23日に、イカルス誌に掲載された、
後期重爆撃期に関する記事です。
後期重爆撃期とはそもそも何でしょうか。
話は1970年代、アポロの時代にさかのぼります。
当時、アメリカのアポロ探査、そしてソ連のルナ探査によって
月面から多くの岩石が持ち帰られました。
その石を研究者たちが調べたところ、ほとんどの岩石が、
40億年前から39億5千万年前の間に、形成されていたことがわかったのです。
このことは、太陽系が誕生した46億年前からおよそ6億5千万年たってから、
ごく短い期間の間に月面で大量の天体衝突が起きたことを意味しています。
この現象は当初「月の大激変」と呼ばれましたが、
後に「後期重爆撃期」と呼ばれるようになりました。
なぜ「後期」なのでしょうか。
それは、大激変が起こった時期が、太陽系が形成されてから、
ずいぶん後のことだったからです。
太陽系が誕生したのは約46億年前のことです。
この当時の太陽系は、無数の微惑星や岩石が漂っていて、
それぞれが衝突して合体することで、惑星ができていったと考えられています。
しかし1億年もすると、ほとんどの岩石は失われ、
太陽系は比較的平穏な状態に落ち着いたと考えられていました。
しかし月の岩石のデータは、太陽系ができてから約6億年後に、
天体衝突が再び増加していたことを示していたのです。
なぜ、一度落ち着いたはずの天体衝突が、再び増加したのでしょうか?
このことを説明するために様々な仮説が出されてきましたが、
最も有力なのが、2000年代に提唱された「惑星移動仮説」です。
これによると、木星と土星は、太陽系が形成された直後は、
現在の位置とは少し異なる場所にありました。
木星と土星は、太陽系では最大級の惑星であり、重力が桁外れに強い惑星です。
そのため互いの重力によって、だんだん軌道が不安定になっていきます。
そして太陽系が誕生してからおよそ6億年後に、惑星の大移動がおき、
その時に多くの小天体が影響を受けて、内側や外側に弾き飛ばされました。
内側に弾き飛ばされた小天体が月面に大量に衝突し、
大激変を起こしたのです。
この惑星移動仮説は「ニース・モデル」と呼ばれ、「後期重爆撃期」と共に、
学会では過去数十年、主流の考え方でした。
月でこのような大量の天体衝突があったということは、
太陽系の他の惑星、地球や金星、火星などにも大激変が生じていたはずです。
ただし地球の場合、プレートテクトニクスによって、
地表がどんどん更新されてしまうため、
これほど古い時代の岩石は現在残っていません。
また金星、火星、水星からはまだサンプルが持ち帰られていないため、
これらの惑星の岩石の形成年代はまだよくわかっていません。
そのため、後期重爆撃期は月面サンプルのデータに依存している点が、
唯一の弱点ではありましたが、他に反論できるようなデータもなかったため、
標準的なシナリオであり続けてきました。
しかし、このシナリオがここ数年で、根底から覆されようとしています。
アポロの時代から50年ほど経ち、現在は当時よりも分析機器が進歩しています。
2010年代に最新の装置を用いて、あらためてアポロの試料を分析したところ、
従来のデータよりも、岩石の形成年代がばらけていることがわかったのです。
最も古いもので43億年前、
新しいものだと「後期重爆撃期」で考えられてきた期間よりも後だったりしたのです。
さらに、これまで多数の天体衝突があったと解釈されてきましたが、
実は、雨の海を作った巨大な天体衝突によって吹き飛ばされた岩石が、
月面の他の場所に再衝突することで、
見かけ上、多数の天体が衝突したように見せかけていただけの可能性が出てきたのです。
つまり、地球や月に大量の小天体が降り注ぐような、
「後期重爆撃」は存在しなかった可能性がでてきたのです。
この可能性は、惑星の軌道進化を研究する人たちには喜ばれました。
軌道力学のモデルでは、後期重爆撃が起こってしまうと、
地球や火星、金星の軌道が乱れてしまい、
現在のような円軌道にはならなくなってしまうからです。
さらに2019年12月23日に、衝撃的な論文が公開されました。
これまで「後期重爆撃」をサポートする側であった、
ニース・モデルを提唱した研究者らが、
一転して後期重爆撃を否定するような論文を出版したのです。
この論文によると、木星や土星が移動するような、
軌道不安定を遅い時期におこすのは非常に難しく、
むしろ太陽系が形成してから1億年以内に起きやすいことが示されました。
このことは、大量の天体が地球や月に衝突したのは、
太陽系が形成してからおよそ1億年以内の話であり、
それ以降は比較的平穏であったということです。
他にも、この新しいシナリオによれば、
なぜ火星は他の固体惑星に比べて小さいのかや、
小惑星帯がなぜこんなにコンパクトなのかも説明できるとのことです。
後期重爆撃が存在しなかったとなると、生命の起源についても、大きな再考を迫ることになります。
これまで、太陽系が形成してから数億年の間は、地球の表面は大量の天体に爆撃されるため、
生命が存在するのは難しいと考えられてきました。
しかし後期重爆撃が存在しなかったとすると、どうなるでしょうか。
地球が誕生してから比較的早い段階で、生命が誕生していた可能性が出てくるのです。
現在確認されている最古の生命の痕跡は35億年前のものです。
しかし、それらの生命の化石は、比較的複雑な形状をしており、
もっと単純な生命から既に数億年かけて進化した後の姿ではないかと考えられています。
このように、後期重爆撃期が存在したかどうかは、惑星の進化や生命の起源に深く関わる、
非常に重要なテーマです。
これに関してはまだまだ議論が続いており、今後も続報をお届けしたいと思います。
それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル、登録お願いします。
#惑星科学チャンネル #PlanetaryScienceChannel #行星科学频道
関連動画
関連用語