私の付箋の使い方
どうも、フジです。
みなさんは勉強をする時、付箋を使用することはありますか? 既にうまく活用できている人もいれば、付箋を使って勉強効率が上がるなら使いたいけどどうすれば…という人もいるかと思います。
ただ闇雲に貼り付けるのでは当然意味がありません。
今回は、現役で東大に合格した私が、高校生の時にどう付箋を使っていたのかを紹介しようと思います。
こんな記事を書いといて言うのもどうかと思いますが、付箋の使い方に正解はありませんし、合う合わないで効果も変わってきますから、結局のところ自分で試行錯誤するのがベストなんですよね。なので、この記事はあくまで参考程度に!
数学ではわからなかった問題に!
ぶっちゃけ数学では有効な使い方が思いつきませんでした。
が、一応、青チャートのわからなかった問題に付箋をピッと貼り付けてはいましたね。
数学で付箋が活躍できなかった理由は2つあります。
1つは、「わからなかったところだけ復習」というのをあまりしていなかったから。私は基本的に、数学は単元ごとに復習するようにしていました。そうすることによって、その単元の問題が出題されたときに、解法の選択肢が頭に浮かびやすくなるんです。わからなかった問題をピンポイントで解き直そうとすることがなく、いつも特定の単元のページをペラペラとめくりながら復習をしていたので、付箋は使っていませんでした。
そしてもう1つとして、「あの単元のこの類の問題はまだできるようにしてないな」というのを、いつも思い出しながら把握するようにしていたので、付箋をつけて目立たせる必要がなかったというのもありましたね。
過去問演習を始めてからも、付箋を使用する機会はあまりありませんでした。過去に解けなかった問題をピンポイントで解き直すのではなく、始めのページからペラペラと巡っていって、それぞれの問題について軽く「これはこんな感じに進めたら解けたよな」みたいなことを確認した上で、「あ、これってどういう方針でやるんだっけ」と立ち止まることになった問題を解き直す…みたいな復習方法を取り入れていたんですよね。難しかった問題の番号部分に印をつけるくらいのことはしていた気もしますが、とにかくわざわざ付箋を使うことはなかったですね。
初っ端から付箋使わない話をしちゃってすみません。
付箋はそもそも復習効率を上げるために使用するものだと認識していますが、数学の復習に関しては、特定の問題をピンポイントで解き直すことはあまりオススメできないので、付箋を使うにしてもお気持ち程度…になってしまいますね(笑)
次回は英語です!
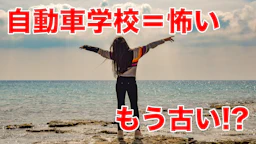
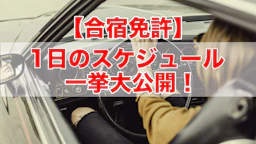


.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)




